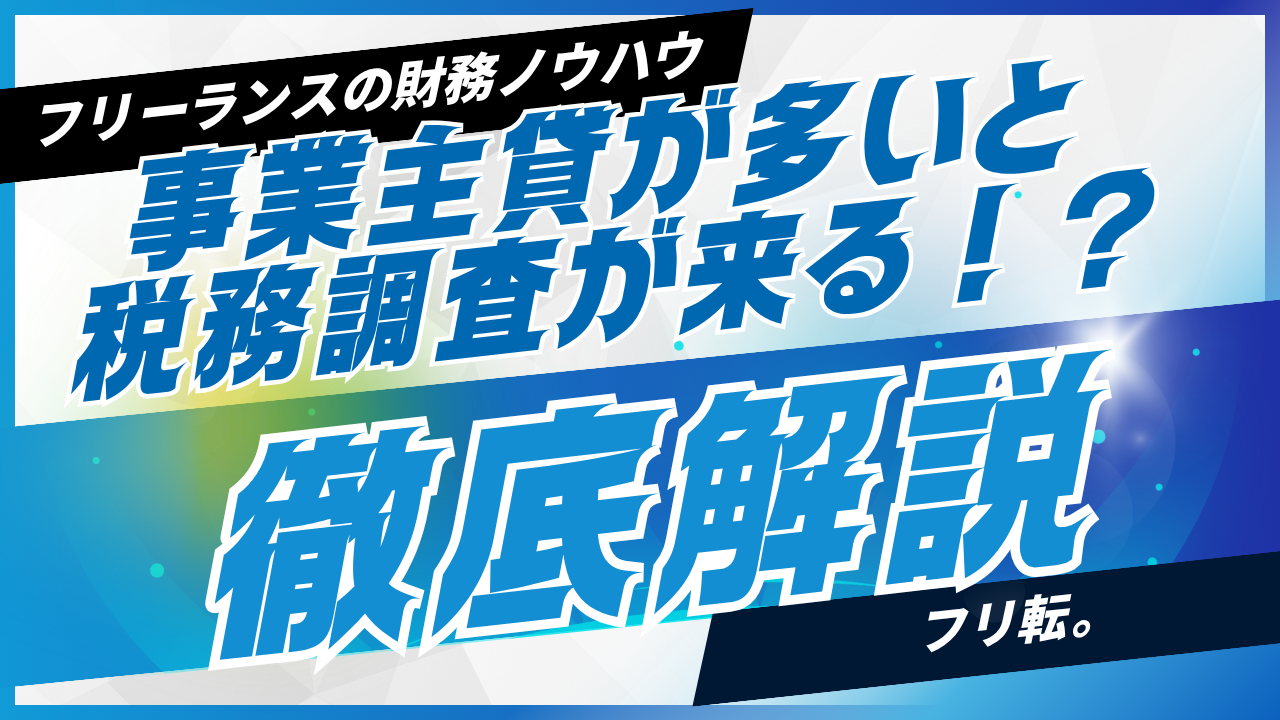個人事業主3年目の私も、開業当初は事業主貸を適当に処理していました。「生活費を引き出したら使えばいい」程度の認識でしたが、これが大きな間違いでした。
危険です。所得に比べて金額が大きすぎると、税務署から「売上、隠してませんか?」と疑われるんです。実際、知人の飲食店経営者が税務調査で相当苦労したのを間近で見ました。
銀行融資でも「この人、お金の管理できてないな」と判断されて審査が通らなくなります。私も融資申し込みの時、事業主貸の金額について説明を求められて冷や汗かきました。
この記事で分かること
- 事業主貸が多いと起こる3つのリスク
- 税務調査で目をつけられない記帳のコツ
- 銀行から信頼される管理テクニック
開業1年目の人へ:事業主勘定って何?
個人事業主だけが使う、ちょっと特殊な勘定科目です。
会社員時代は給料をもらって生活してましたよね。懐かしいです、あの頃は。でも個人事業主には給料という概念がありません。事業で稼いだお金から直接、生活費を引き出します。そのお金の出入りを記録するのが「事業主勘定」なんです。
法人なら会社と個人の財布は完全に別。これ、すごく分かりやすいですよね。でも個人事業主は事業とプライベートのお金が行ったり来たり。だからこそ、きちんと記録しないと税金の計算がめちゃくちゃになってしまいます。
使い分けはシンプル
事業主勘定には2種類あります。私も最初は混乱しましたが、慣れれば簡単です。
| 勘定科目 | 使うタイミング | 具体例 |
| 事業主貸 | 事業→個人へお金が流れる | ・生活費を引き出した・事業用カードで私物を購入・事業口座から所得税・住民税を支払った |
| 事業主借 | 個人→事業へお金が流れる | ・自分の貯金を事業資金に投入・個人カードで事務用品を購入・事業口座に利息が入った |
所得税や住民税は経費じゃありません。個人の税金ですから、事業主貸として処理します。毎月25日に20万円引き出していても、それは給料じゃなく事業主貸。ここ、けっこう勘違いしやすいポイントです。
事業主借を使うのはこんな時
- 自分の貯金を事業資金として投入した
- 個人カードで事務用品を買った
- 事業口座に利息が入った
こう使い分ければ、確定申告の時に正確な所得計算ができます。私の場合、freeeを使い始めてからこの辺がすごく楽になりました。
事業主貸が多いと起こる3つのリスク
リスク1:税務署から目をつけられる
これは絶対に避けたい事態です。
事業所得が年170万円なのに、事業主貸が200万円。この30万円の差額、どこから来たんでしょう?税務署はこういう矛盾を見逃しません。「売上を隠して、現金で生活費に回してるんじゃないか」と疑います。
知人の飲食店経営者の話ですが、事業用の現金をそのまま生活費に使っていたんですね。帳簿上の売上は少ないのに事業主貸だけ多いという不自然な状態でした。税務調査が入って、過去3年分の帳簿を全部調べられたそうです。結局、修正申告に加えて過少申告加算税と延滞税。精神的にもかなり参ったと言ってました。
もし悪質と判断されれば重加算税まで課されます。調査対応には膨大な時間がかかりますから、日頃から適切な記帳が本当に大切です。
リスク2:銀行融資が通らなくなる
これは私自身が経験したので、よく分かります。
銀行の融資担当者は、貸借対照表の事業主貸を必ずチェックします。私が初めて融資を申し込んだ時、担当者から「事業主貸の金額が大きいですね。この理由を教えていただけますか?」と聞かれて、正直焦りました。
事業主貸が多いと「稼いだ以上にお金使ってるじゃん」と判断されるんです。「この人、資金管理できてないな」「融資しても私的に使われそう」。そう思われたら終わり。審査は通りません。
実際、私の場合は「子どもの入学金で一時的に引き出した」と説明して、領収書も見せて何とか理解してもらえました。でも、それ以降は事業主貸のタイミングと金額にすごく気をつけるようになりましたね。
融資を受けた直後に多額の事業主貸があると、「融資金を流用した」と疑われます。契約違反で一括返済を求められるリスクもあります。融資後しばらくは事業主貸を控えめにすることが賢明で、これは特に重要なポイントです。
あと、事業主貸が多いと元入金(個人事業主の資本金みたいなもの)がマイナスになることがあります。これは完全に赤字。融資審査で致命的です。
リスク3:経理が破綻する
これも実際に経験して痛感した問題です。
事業主貸を多用すると、どこまでが経費でどこからが私費なのか、境界線が曖昧になります。事業用カードで家族の食事代を払って「接待交際費」、旅行費用を「出張費」。開業1年目の私は、こんな無理な処理をしてました。今思い返すと冷や汗ものです。
税務調査で否認されたら、追徴課税の対象です。
同じく開業したばかりの友人は、事業主貸の処理が曖昧で、確定申告直前に数百件の取引を手作業で仕分け直してました。徹夜続きで本当に大変そうでした。口座やクレカは事業用と個人用で明確に分けるべきです。開業時から徹底すべき最重要ポイントです。
複式簿記での正しい仕訳方法
正直、最初は「複式簿記」って聞いただけで拒否反応がありました。しかし会計ソフトを活用すれば、思ったより簡単に対応できます。
複式簿記では、すべての勘定科目が「資産・負債・純資産・収益・費用」に分類されます。事業主貸は資産の部で借方(左側)が定位置、事業主借は純資産の部で貸方(右側)が定位置です。
覚え方のコツは「事業主貸=事業主にお金を貸している」「事業主借=事業主からお金を借りている」とイメージすることです。私もこのイメージで理解できました。
具体的な仕訳例
ネットショッピングで生活用品1,000円を事業用口座から払った場合:
| 借方(左側) | 貸方(右側) | ||
| 事業主貸 | 1,000円 | 普通預金 | 1,000円 |
普通預金は資産なので借方が定位置。でも支払いで減っているから、定位置の逆である貸方に来ます。最初はこれが分からなくて、何度も間違えました。
逆に、家計用の口座から5万円を引き出して事業用の現金として入れた場合:
| 借方(左側) | 貸方(右側) | ||
| 現金 | 50,000円 | 事業主借 | 50,000円 |
現金は資産で借方が定位置。増えているので定位置通り借方です。慣れればパターンが見えてきます。
税務調査で指摘されない4つのルール
ルール1:所得と事業主貸のバランスを毎月チェック
事業所得が300万円なのに事業主貸が500万円。差額の200万円、どう説明します?
- 配偶者の収入で生活してる
- 相続で得た資金がある
- 以前の貯蓄を取り崩してる
こういう状況の場合でも、具体的な理由を説明できないとマズイです。私の場合は妻がパートで働いているので、そこからも生活費を出してます。こういうことも説明できるようにしておくべきです。
毎月帳簿を確認する習慣をつけましょう。私は毎月末に必ずfreeeで貸借対照表をチェックしてます。事業所得に対して事業主貸が多すぎる月があれば、理由をメモに残しておきます。
- 子どもの入学金で一時的に引き出した
- 冠婚葬祭で出費がかさんだ
こういう記録があれば、税務調査時にも明確に説明できます。実際、私はExcelで簡単なメモを残してます。これだけで安心感が全然違います。
ルール2:現金売上は必ず口座に入金する
飲食店や小売店で現金商売してる人、本当に要注意です。
事業用の現金をそのまま生活費に使って、売上として記帳しない。これ、完全にアウトです。知人がこれでやられました。「売上除外」という脱税行為に該当します。税務調査で最も厳しく追及される項目です。
悪意がなくても、現金売上を記帳しないと帳簿上の売上は少ないのに事業主貸が多いという不自然な状態になります。
正しい処理方法は、現金売上を一度すべて事業用口座に入金すること。その後で必要な生活費を引き出して事業主貸として記帳します。1日の現金売上が3万円なら、事業用の現金から直接2万円を生活費に使うんじゃなく、3万円全額を口座に入金してから2万円を引き出す。
面倒に感じるかもしれません。しかしこの手間を惜しむと、後で取り返しのつかないトラブルに発展します。実体験から断言できます。
ルール3:領収書と帳簿をセットで保管
税務調査では、帳簿の内容が事実かどうか確認するため、領収書やレシートの提示を求められます。
事業主貸として処理した支出も「本当に事業と関係ない支出なのか」確認されることがあります。実は経費として計上できるものだったら、節税の機会を逃してます。もったいないですよね。
事業主貸として処理した支出も、可能な限り領収書を保管しておきましょう。私は事業主貸の領収書も別のクリアファイルに入れて保管してます。帳簿には、以下のように具体的な摘要を記入しておくと、後から見返した時に明確になります。
- 生活費
- 所得税支払い
- 住宅ローン返済
税務調査は過去3年分(場合によっては7年分)を遡って調べられます。気が遠くなる話ですが、日頃から丁寧な記帳と書類保管を習慣化することが最大の防御策です。
ルール4:少なすぎても要注意
これは意外かもしれませんが、事業主貸が極端に少ない場合も税務署から不審に思われます。
事業所得が400万円あるのに事業主貸が年間50万円しかない。税務署は「どうやって生活してるの?」と疑問を持ちます。以下のように、合理的な説明ができれば問題ありません。
- 配偶者の収入がある
- 預貯金を取り崩してる
- 実家暮らしで生活費が少ない
私の知り合いで、配偶者が会社員で収入が安定している人がいます。その人は事業主貸が少なめなんですが、説明できるので大丈夫です。
事業所得以外に給与所得や不動産所得がある場合は、確定申告で合わせて申告する必要があります。事業主貸は多すぎても少なすぎても注目されるため、適正なバランスが重要です。
家事按分で経費を最大化する
家事関連費とは、事業と私生活の両方にまたがる支出のこと。自宅家賃、電気代、通信費などが該当します。
これ、うまく使えば節税になります。
これらは全額を経費にできません。でも、事業で使用している割合を合理的に計算して按分すれば、その分を経費として計上できます。私も自宅の一室を事務所として使ってるので、家賃の一部を経費にしてます。
自宅兼事務所で仕事してる場合、家賃10万円の物件で全床面積60平方メートルのうち10平方メートルを事務所として使用しているなら、按分比率は10÷60≒16.7%です。家賃10万円×16.7%≒16,700円を地代家賃として計上できます。
きちんとメジャーで測って、間取り図にも印をつけて記録してます。税務調査で聞かれても大丈夫なように。
合理的な按分基準を用意する
家事按分には「必ずこの方法」という決まりはありません。合理的に説明できる基準なら認められます。
感覚的な按分じゃなく、客観的な根拠を示すことが必要です。自宅家賃なら床面積や部屋数、電気代なら使用時間やコンセントの数、携帯電話代なら通話記録から業務とプライベートの比率を算出します。
| 費目 | 按分基準の例 | 記録方法 |
| 自宅家賃 | 床面積・部屋数 | 間取り図に事務所スペースを記入 |
| 携帯電話代 | 使用時間・通話回数 | 通話記録から業務分を算出 |
| 電気代 | 床面積・使用時間 | 事務所部分の使用時間を記録 |
| ガソリン代 | 走行距離・使用日数 | カレンダーアプリに営業訪問先をメモ |
ガソリン代の按分では、走行距離を記録したノートやアプリの履歴を証拠として残しておくと説得力が増します。私はスマホのカレンダーアプリに「営業訪問:〇〇市、往復50km」みたいにメモしてます。「1か月で1,000キロ走行し、そのうち700キロが営業訪問や仕入れなどの事業目的」という記録があれば、按分比率70%を主張できます。
手間はかかりますが、税務調査時の安心材料として必ず役立ちます。
期末に家事按分の再仕訳を忘れずに
家事関連費を払った時点では、いったん全額を経費として計上しておき、期末(確定申告時)に家事分を事業主貸へ振り替える処理を行います。
日々の支払い時に按分計算するのは手間がかかるため、一旦全額を経費として記帳し、年度末にまとめて按分する方が効率的です。水道光熱費を年間5.5万円支払い、事業割合が30%なら、年間の家事分は3.85万円。この金額を経費から除外するため「借方:事業主貸 38,500円/貸方:水道光熱費 38,500円」という仕訳を切ります。
会計ソフトには按分設定機能が付いているものが多いので、年度初めに按分比率を登録しておけば、期末に自動で再仕訳を行ってくれます。この機能は作業効率を大幅に向上させます。freeeを使い始めてから、この作業がすごく楽になりました。
銀行融資で評価を下げない管理術
融資審査で銀行が見る3つのポイント
銀行が融資審査を行う際、決算書の中で特に注目するのが貸借対照表の事業主貸です。私も実際の融資申込で痛感したポイントです。
銀行が融資審査でチェックする3項目
・事業主貸が事業所得に対して多すぎないか
→ 目安:所得の8割以内
・ 事業主貸が年々増加していないか
→ 右肩上がりは「資金管理が悪化」のサイン
・ 元入金がマイナスになっていないか
→ マイナス=累積赤字状態で融資は厳しい
これらの指標が悪化していると「資金管理がずさん」「経営が不安定」と判断されます。融資条件が厳しくなったり、審査自体が通らなくなったりします。
知り合いの個人事業主が銀行借入の借り換えを申し込んだ際、銀行担当者から「事業主貸と事業主借が多いのはなぜですか」と質問され、明確に答えられなかったため融資が見送られました。誰にでも起こりうる事例です。
融資資金を事業主貸で処理してはいけない
融資を受けた資金は、事業運転資金や設備投資など、事業目的のために使うことが前提です。当たり前ですが。
銀行は融資契約時に資金使途を明確にしています。違反が発覚すれば契約違反と見なされ、一括返済を求められたり、今後の融資が一切受けられなくなったりするリスクがあります。事業継続に関わる重大な問題です。
運転資金として300万円の融資を受けた直後に、200万円の事業主貸が計上されていると「融資金を私的に流用した」と疑われます。タイミングが重なっただけでも不信感を持たれるため、融資後しばらくは事業主貸を控えめにすることが賢明です。
私は融資を受けた後の3ヶ月間、事業主貸を極力抑えるようにしました。その間は個人の貯金を取り崩して生活費に充てました。慎重すぎるかもしれませんが、安全第一です。
元入金をプラスに保つ
元入金とは、個人事業主における資本金のようなもの。
元入金の計算式
| 翌年の元入金 = 前年の元入金 + 事業所得 + 事業主借 − 事業主貸 |
例)前年の元入金100万円、今年の所得300万円、事業主借50万円、事業主貸200万円 → 100万 + 300万 + 50万 − 200万 = 250万円
この金額がマイナスになると「累積赤字を抱えている」「自己資本が枯渇している」状態を示します。銀行融資では元入金がマイナスの事業主は評価が大きく下がります。これは避けたいところです。
元入金をプラスに保つには、事業所得を増やすか、事業主貸を減らすか、事業主借を増やすかのいずれかです。最も健全なのは、売上を伸ばして利益を確保すること。これに尽きます王道ですが、これが最も確実な方法です。
次に、生活費を見直して事業主貸を必要最小限に抑えることです。私も家計簿をつけ始めて、無駄な出費を削減しました。小さな改善の積み重ねが、健全な経営の基盤になります。
開業1年目でも迷わない!口座とクレカの分け方
口座を分けるだけで記帳の手間が半分以下
開業したばかりの人が最初にやるべきは、事業用と個人用の銀行口座を完全に分けることです。最初からやっておくべきでした。
一つの口座で事業も生活も管理していると、会計ソフトに取り込んだ取引データの中に私的な支出が大量に混ざり込みます。一つ一つ仕分けする作業が膨大になります。私は開業1年目、これで確定申告前に地獄を見ました。
どの支出が経費でどれが私費なのか判断に迷い、ミスが増える原因にもなります。
事業用口座を新たに開設し、売上の入金や経費の支払いはすべてその口座から行うようにすれば、会計ソフトとの連携も容易になります。freeeや弥生会計などのクラウド会計ソフトは、銀行口座と自動連携して取引データを取り込む機能があります。
事業用口座だけを連携させておけば、取り込まれるデータはすべて事業関連となり、仕訳の精度が飛躍的に向上します。私は開業2年目から口座を分けて、作業効率が本当に上がりました。
クレジットカードも分ける
クレカも同様に、事業用と個人用を別々に持つことが推奨されます。私は楽天ビジネスカードを事業用にしてます。
事業用クレカで事務用品やガソリン代などを支払い、個人用カードで食料品や衣服を購入する。この使い分けをすれば、カード明細を見ただけで事業の支出と私的な支出が一目瞭然です。確定申告時の作業負担が大幅に軽減されます。
事業用クレカの中には、ポイント還元率が高いものや、会計ソフトと連携しやすいものもあります。法人カードとして発行される事業用カードは、経費管理機能が充実しており、カテゴリー別の支出レポートも自動生成されます。経理作業の効率化に大きく貢献します。
どうしても口座を分けられない場合
開業直後で資金的に余裕がなく、すぐに口座を分けるのが難しい場合もあります。気持ちは分かります。
その場合は、会計ソフトの「プライベート資金」や「事業主貸」の自動仕訳機能を活用しましょう。多くの会計ソフトでは、特定の取引を自動的に事業主貸として処理するルール設定ができます。コンビニやスーパーでの支出は自動的に事業主貸とする、といった設定です。
また、Excelなどで簡易的な管理表を作り、月ごとに「事業用の入出金」と「プライベートの入出金」を色分けして記録する方法もあります。これを基に、月末に事業主貸の合計金額を計算して会計ソフトに入力すれば、一定の精度を保てます。
ただし、この方法は手間がかかるため、事業が軌道に乗り次第、速やかに口座を分けることをおすすめします。将来の自分への投資だと思ってください。
よくある質問
Q1. 事業主貸の上限額は決まっていますか?
いいえ、法的な上限額はありません。ただし、事業所得に対して不釣り合いに多いと税務調査の対象になりやすいため、所得の範囲内に抑えることが推奨されます。私の税理士さんも「所得の8割以内が目安」と言ってました。
Q2. 毎月一定額を生活費として引き出す場合、どう処理すれば良いですか?
毎月25日に20万円など、定期的に引き出す場合でも、その都度「借方:事業主貸/貸方:普通預金」として仕訳を切ります。個人事業主が自分に支払うお金は給料ではないため、必ず事業主貸として処理してください。私も毎月15日に定額で引き出してます。
Q3. 事業主貸が少なすぎると問題になりますか?
はい。極端に少ない場合、「他に収入源があるのでは」「売上を除外しているのでは」と疑われる可能性があります。配偶者の収入で生活している、実家暮らしで生活費が少ないなど、合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。説明できればOKです。
Q4. 青色申告決算書の事業主貸・事業主借は翌年に繰り越されますか?
いいえ。事業主貸と事業主借の残高は、翌年の元入金の計算に使用された後、それぞれゼロにリセットされます。翌年は再びゼロから記録を始めることになります。私も最初これが分からなくて混乱しました。
Q5. 家事按分の比率は毎年変えても良いですか?
はい。ただし、変更する場合は合理的な理由が必要です。「事務所スペースを拡大した」「事業の稼働日数が増えた」など、実態の変化に基づいた変更なら問題ありません。恣意的な変更は税務調査で指摘される可能性があります。私は2年目に事務所スペースを広げたので、按分比率を変更しました。
事業主貸は「適正管理」が成功の鍵
事業主貸が多いこと自体に違法性はありません。でも、事業所得に対して不釣り合いな金額は税務調査や銀行融資で不利に働きます。私自身、これを経験して学びました。
開業1年目から実践すべき4つのポイント
- 口座・クレカの完全分離
事業用と個人用を明確に分ける - 現金売上の正しい処理
必ず事業用口座に入金→その後生活費を引き出す - 家事按分で経費を最大化
合理的な基準で按分し、証拠を残す - 毎月の帳簿チェック
事業所得と事業主貸のバランスを確認する
個人事業主として事業を継続していくには、複式簿記や事業主勘定の理解が不可欠です。正しい知識を身につけて適切に管理すれば、税務リスクを回避しながら健全な経営を実現できます。不安がある場合は、税理士に相談して専門的なサポートを受けることも検討しましょう。私も年に1回は税理士さんに相談してます。
あなたの事業を守るために、今日から事業主貸の適正管理を始めてください。最初は面倒でも、慣れれば当たり前になります。一緒に頑張りましょう!
出典・参照元
本記事は以下の情報源をもとに作成されています。
- 国税庁「青色申告制度」「青色申告特別控除の要件や複式簿記に関する公式情報」
- 国税庁「家内労働者等の必要経費の特例」「家事関連費の按分に関する基準」
- 中小企業庁「個人事業主の会計基準」「事業主勘定の取扱いに関する指針」
※記事内容は2025年10月15日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。