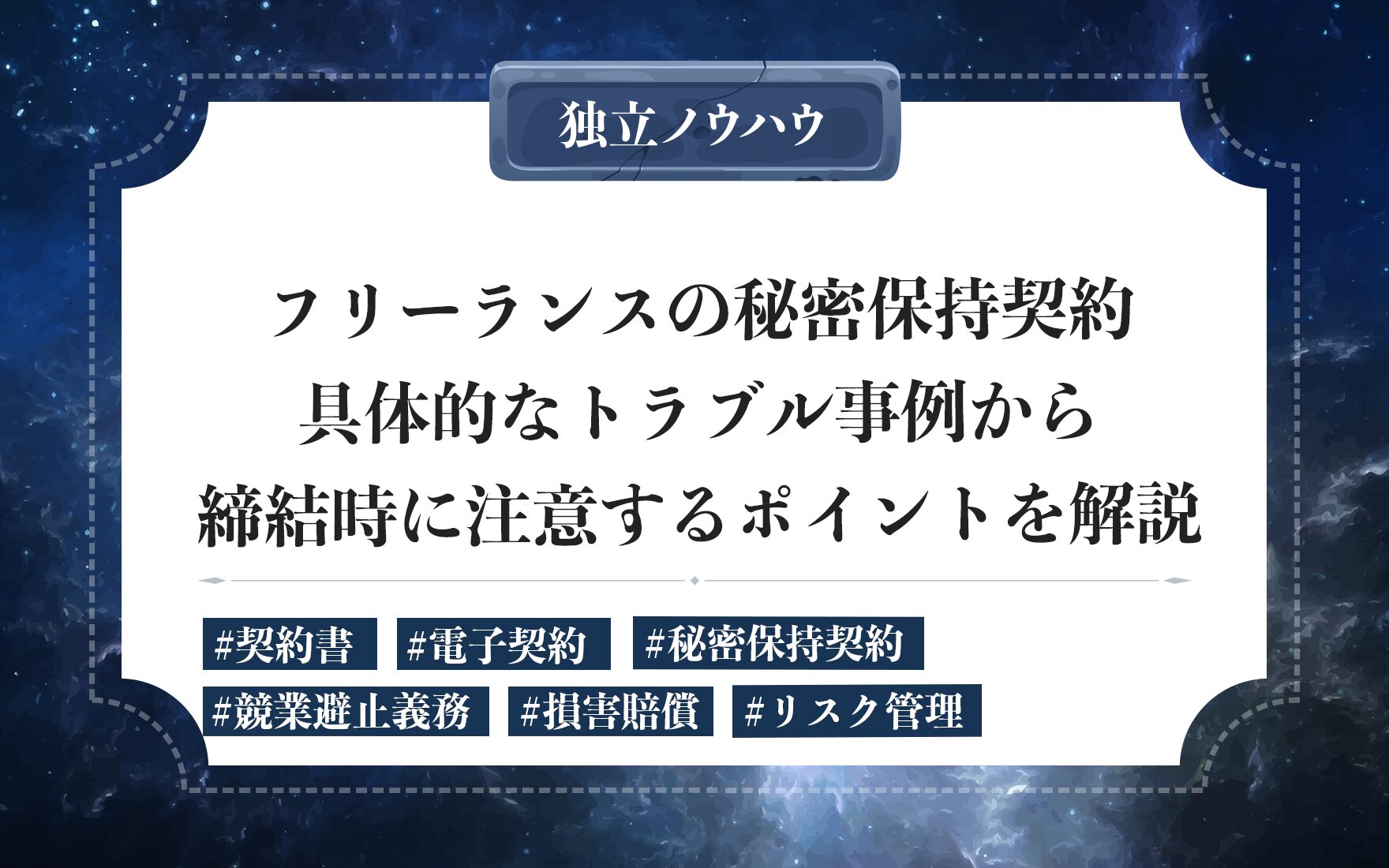契約書類の締結はフリーランスにとって大切な業務です。業務内容、成果物の定義、報酬額などは誰もが気にするチェックポイントですが、それ以外にも確認が必要なものがたくさんあります。確認するべきポイントを押さえながら署名前に内容をきちんと確認しましょう。
秘密保持契約書(NDA)の内容をきちんと確認せずに署名をしてしまうと、のちのち後悔する可能性が!フリーランスは自分の身を自分で守らなければなりません。契約書類の中でも重要なNDAについて学びます。
フリーランスにとって秘密保持契約書(NDA)は取引の自由度にも影響する重い契約
秘密保持契約書とは情報の開示者(相手先企業)と情報の受領者(フリーランス側)との間で締結され、秘密情報が適切に管理されることを保証するための契約書です。英語では「Non-disclosure agreement」と言われ、NDAと略して呼ばれることが多いです。
NDAに署名することで、フリーランスは法的に秘密情報を守る義務を負うことになります。契約の内容によっては、その後のフリーランス活動や取引先獲得の自由度が大きく左右されます。顧客との信頼関係にも関わる大切な契約です。
秘密保持契約書の契約内容
秘密保持契約書とは、取引先の秘密情報や顧客情報などの取り扱いや双方の秘密保持義務、開示された秘密情報の利用目的などについて定めた契約です。フリーランスの場合は、取引を通じて知り得た取引先企業の秘密情報を必要な業務以外の目的で使用したり第三者に開示・漏洩したりしないことを制約する内容になっています。
署名するにあたって、秘密情報の範囲や開示の可否、契約終了時や契約違反時の取扱いについてきちんと確認が必要です。知らなかった、読んでなかったでは済まされないので自己防衛のためにも秘密保持契約についてきちんと理解をしておきましょう。
秘密保持契約書とはビジネスの守秘義務を取りまとめた契約
企業とフリーランス間で取り交わされる秘密保持契約書は以下のような形になっています。
・秘密情報の定義
どこまでの情報を秘密情報とするかを明記しています。
・秘密保持義務の定義
秘密情報を管理する方法と、誰にまで開示してよいのかをまとめている箇所で、秘密保持契約の中核をなす規定です。
・目的外使用の禁止
秘密情報をどこまでの範囲で利用してよいのかを明記してあります。
・秘密情報の返還、破棄のルール
契約終了時や企業からの要請があった場合など、一定の事由が発生した場合においての秘密情報の返還義務や破棄義務が書かれています。
・損害賠償、差止めのルール
秘密保持契約に違反した場合に、どのようなペナルティがあるか、損害賠償義務だけでなく賠償の範囲まで書かれてあります。
・有効期限、存続条項
フリーランスの場合の秘密保持義務の存続期間は契約期間と同じであることが一般的です。
秘密保持契約は取引を検討する段階でクライアントと締結するもの
フリーランスの場合は、業務契約を結ぶ前に企業と打ち合わせする場面も出てきます。企業側の内部情報を提供される前には必ず秘密保持契約を締結しておき、秘密情報を開示される前に結ぶのが鉄則です。
CHECK
・秘密保持契約とは、取引先の機密情報の取り扱いに関して定めた契約
・内容によってはフリーランスとしての取引先の自由度が制限されることもある
・秘密保持契約は、取引の開始前でも情報を提供される前に締結が必要
秘密保持契約はクライアントの雛形を活用する場合もあるが自前を持っておくべき
秘密保持契約書は企業側から出されることが多いものですが、プロのフリーランスとしてひな形を用意しておくと良いでしょう。
秘密保持契約書 テンプレート:NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形【参考資料2】各種契約書等の参考例 (令和6年2月改訂版)
クライアントとの秘密保持契約の契約方法
秘密保持契約は企業側から提示されることがほとんどです。もし取引契約時に秘密保持契約が含まれていない場合は、相手企業に確認を入れることをおすすめします。
昨今、秘密保持契約は電子契約で締結することが多い
秘密保持契約に限らず、企業との契約は電子契約で行われるのが主流になっています。電子契約の流れは難しいものではないので契約前に理解しておきましょう。
秘密保持契約書に収入印紙を貼付する必要はない
契約書によっては印紙の貼付が求められるものもありますが、秘密保持契約書は印紙は不要です。また、電子契約を行う契約書類は印紙貼付の対象外となっています。
CHECK
・秘密保持契約は企業側から提示されることが多いが、提示されなかった場合は確認が必要
・収入印紙の貼付は不要
フリーランスの秘密保持契約に関する具体的なトラブル
秘密保持契約の内容をきちんと確認しなかったために発生しうるトラブルについてまとめました。何を確認しなければいけなかったのかがわかる内容になっているので、チェックしてご自身に当てはまるか確認してみてください。
「著作権の所在」を明確にせずポートフォリオに掲載できなかった
ケース事例
フリーランスのデザイナーとして企業から依頼を受けてロゴをデザインした。契約により著作権は依頼元の企業に帰属することが明記されていた。
トラブル内容
デザイナーはこのロゴをポートフォリオに掲載することができなくなります。
防止策
自身の作品実績をポートフォリオに載せることが出来ないのは売上にも関わる大きな問題です。ポートフォリオに掲載することを視野に入れ、NDA内の著作権欄の確認が必要です。
「競業避止義務」が広く設定されており仕事の範囲が狭くなってしまった
ケース事例
フリーランスのデザイナーとして、企業と契約を結び特定のプロジェクトのためにデザインを提供していた。契約にはプロジェクト終了後1年間は競合する同業企業にサービスを提供しない旨が含まれていた。
トラブル内容
プロジェクト終了後、新しい取引先を探す際に一定期間同じ業界からの案件が受けられなくなり、案件数が減ってしまった。
防止策
競業避止義務とは、情報・ノウハウの流出を防ぐために他の企業への就職を制限するものです。フリーランスの契約で必ず盛り込まなければいけない内容ではないですが、取引先の企業との契約に入っている場合は、適応範囲や期間を確認しましょう。
秘密保持契約に違反した場合は差止請求や損害賠償請求になる
ケース事例
フリーランスのコンサルタントとして、NDAを結んでA社のマーケティング戦略を請け負っていた。契約期間終了後、別の企業でのコンサルティングの際にA社の戦略を事例として紹介した。
トラブル内容
企業の秘密情報を外部に漏らしたとして損害賠償を請求された。
防止策
意図せずともNDAの契約内容に違反した場合は、損害賠償を請求される可能性があります。その場合フリーランスとして個人で払いきれない金額とならないよう、損害賠償限度額を定めておくのが良いでしょう。取引額を限度とすると定めるのが一般的です。
CHECK
・きちんと確認をしないとトラブルにつながるので要注意
・「著作権の所在」「競業避止義務」の項目はチェックするべし
・違反した場合の損害賠償の内容も確認しよう
フリーランスが秘密保持契約を締結する際のチェックポイント
仕事に大きく影響する契約書になるので、締結する前には内容をきちんとチェックしましょう。チェックするポイントは以下のとおりです。
秘密情報の定義(範囲)が広すぎないか
何が秘密情報とされているのか定義欄を確認し、企業側の考える定義と自分の考える定義の相違がないかを確認します。
存続条項の対象および期間が長すぎではないか
秘密保持の履行対象期間が契約終了後もずっと続くような内容になっている場合は、一度企業側へ確認をした方が良いでしょう。
損害賠償が民法の規定に比べて重すぎではでないか
秘密保持義務違反があった場合、企業側は損害賠償請求をすることが可能です。その際に請求できる損害は、原則として民法416条(損害賠償の範囲)に沿うものになるので、比較して妥当なものになっているか確認しましょう。
| 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 |
特約事項として受領側の義務が増えていないか
特約事項が加えられている場合はその内容の確認も行いましょう。企業への定期的な報告義務の追加など、フリーランス側の追加作業が発生する可能性もあるので、実現可能かどうかも検討します。
CHECK
・秘密情報の範囲、対象の期間は必ず確認する
・損害賠償の規定内容を民法と照らし合わせて妥当なものかも確認する
・特約事項で提示される義務も確認すること
秘密保持契約書に関して気を付けなければいけないことが多すぎて不安になる必要はありません!チェックするべき項目を押さえておけば大丈夫。トラブルを防止し、フリーランスとしての活動をスムーズに進めるためにしっかりと対応しましょう。