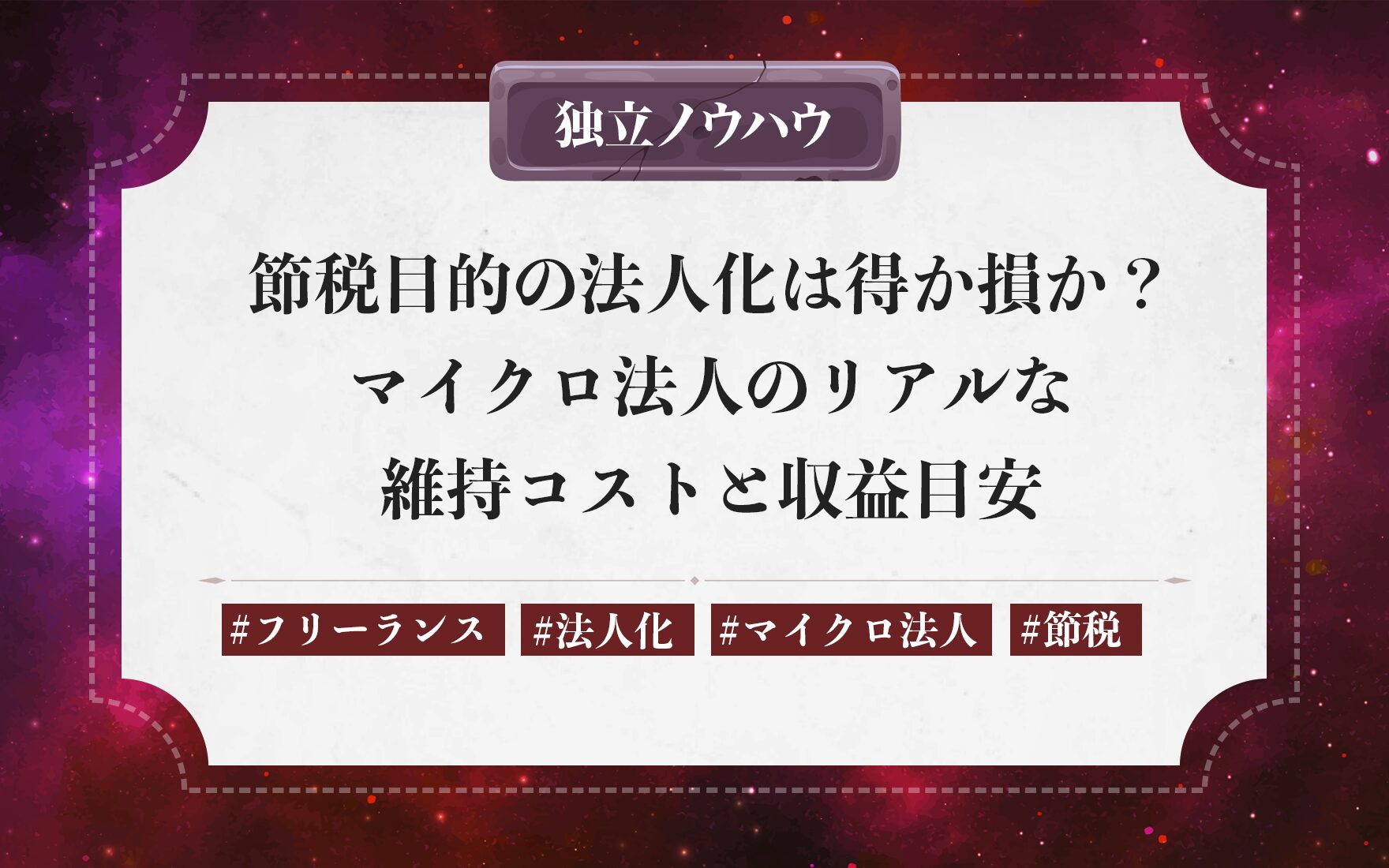フリーランスは税金の手続き等も全て自分でしなくてはなりません。経費を上手に活用することで、節税に繋がるので経費はきちんと管理しましょう。

頑張って稼いだ収入から、できる限り税金で引かれる金額を減らすようにするのが節税対策で、フリーランスとして上手く対処したいところです。正しい知識と適切な対処法を知り、確定申告を節税のチャンスとして活用できると良いですね。
フリーランス活動にかかる税金の仕組み
フリーランスは個人事業主として、所得税、消費税、住民税、個人事業税などの税金を自分で管理・納税します。なかでも所得税は確定申告によって毎年申告が必要なものです。
所得税は、「年間の総収入から必要経費を差し引いた所得」に対して課税されるため、経費の管理が非常に重要になってきます。
収入から必要経費や各種控除を引いた課税所得に税金がかかる
所得税は稼いだ売上額ではなく、利益の額に対して課税されます。「総収入(売上)」「経費」「控除」「事業所得(利益)」それぞれの違いを理解することで上手く節税対策しましょう。
- 総収入(売上)= 仕事の報酬で受け取る金額
- 経費= 事業に関連する支出
- 控除=基礎控除、扶養控除、医療費控除など
- 事業所得(利益)= 収入-経費
- 課税所得= 所得-所得控除
正しい経費計上で節税につながったり還付金が返ってくる
還付金とは、確定申告で必要よりも多くの税額を払っている場合に税務署から過剰分を払い戻しされることです。事業に関する経費を適切に計上することで課税所得が減り、過剰に支払った税金が還付されることがあります。
CHECK
・フリーランスは納税も自分で行わなければならない
・「総収入(売上)」「経費」「控除」「事業所得(利益)」の違いを理解しておこう
・正しい経費計上で節税につながったり還付金が返ってくる
フリーランスの経費の原則は業務上利用したものだけに適用される
なんでもかんでも経費に出来るわけではなく、業務に直接関連する支出のみ経費として扱えます。不適切な経費計上は税務署から指摘される可能性もあるため気を付けましょう。
売上や収入がなくても経費があるなら確定申告で計上可能
フリーランスの場合、売上や収入がなくても経費があれば確定申告で計上することができます。申告しておくことで、青色申告特別控除の適用など、将来的に利益が出たときにメリットを得られるためです。
フリーランスが計上できる勘定科目と経費になる例・ならない例一覧
| 用途 | 科目 | 計上できる例 | 計上できない例 |
|---|
| 事業関連 | 外注費 | 営業やマーケティング関連業務などの外注料金やライターやデザイナーへの報酬 | 家事代行など業務とは無関係な代行 |
| | 広告宣伝費 | インターネット広告、チラシ広告、SNSやインフルエンサーとのコラボ費用や名刺作成費用など | – |
| | 通信費 | 事業用の電話代、インターネット代、モバイル通信費用 | 家の固定回線など業務では使わないもの |
| | 事務用品費 | 事務所で使用する文房具や消耗品、コピー用紙など | プライベートで利用するもの |
| | 消耗品費 | 電池、事務用品など業務で使うもの | プライベートで利用するもの |
| | 接待交際費 | クライアントとの打ち合わせカフェ代や会食費、贈答品 | 業務に関係ない飲食代 |
| | 交通費 | 業務に関連する電車代やタクシー代、ガソリン代 | 個人的な移動の交通費 |
| | 旅費交通費 | 出張費用としての飛行機や新幹線、宿泊費用 | 個人的な観光などの費用 |
| オフィス関連 | 家賃 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | – |
| | 光熱費 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | – |
| | 保険料 | 事業用の損害保険や生命保険 | 事業主自身の保険料 |
| | 設備投資 | パソコンやオフィス家具、カメラ機材など、事業に必要なもの | プライベートで利用するもの |
| | ソフトウェア費用 | 業務で使用するソフトウェアの購入費用やサブスクリプション費用 | プライベートで利用するもの |
| 人件費 | 給与 | 社員やアルバイトへの給与 | – |
| | 社会保険料 | 雇用保険や健康保険、年金などの社会保険料 | – |
| 教育・研修関連 | 研修費 | 業務やスキルアップに関連する研修やセミナーの参加費用 | – |
| | 書籍費 | 業務に役立つ書籍や資料購入代金 | 個人の趣味で購入したもの |
場合により経費にできる業種や職業によっても変わる費用の例一覧
- ライター:取材での飲食代や、サービスの体験利用料など
- フォトグラファー:カメラやレンズなどの購入費、撮影スタジオの利用料
- デザイナー:デザインツールのソフトウェアライセンス料
- Webデザイナー:サーバーレンタル費やクラウドサービス利用料
経費として計上できるかどうか迷いやすい費用の例
| 項目 | 計上できる場合 | 計上できない場合 |
|---|
| バッグ | 仕事で使うバッグ | プライベートで使うバッグ |
| 手帳 | スケジュール管理など業務で使用しているもの | 日記など業務に関係なく使っているもの |
| スーツ | 取引先に訪問したり、業務内で着用する服 | 仕事の際には着用しないプライベートのもの |
| タクシー代 | 業務内での利用。行先やその目的など利用履歴を残しておくと良い | 休日の利用や旅行時などに利用したもの |
| 車のガソリン代 | 業務内での利用。行先やその目的など利用履歴を残しておくと良い | 休日の利用や旅行時などに利用したもの |
| カフェ | 取引先との打ち合わせや作業のための利用 | 個人的な利用 |
| 保険料 | 国民健康保険は計上できる | 自身の生命保険料は計上不可 |
| 病院の治療費 | なし | 治療費は一定額以上で「医療費控除」の対象 |
CHECK
・不適切な経費計上は税務署から指摘される可能性もある
・売上や収入がなくても経費があれば確定申告で計上できる
・業種や職種、状況によって経費として計上出来るものと出来ないものがある
個人事業主やフリーランスの経費は家事按分が可能
家事按分(かじあんぶん)とは、フリーランスが自宅で仕事をしている場合など、仕事とプライベートの両方で使っているものを仕事で使用している割合と家庭で使用している割合に分けて経費計上することです。
按分の計算方法としては、利用しているスペースの「面積」で計算する方法や、使っている「時間」の割合をもとに計算する方法があります。
自宅オフィスの場合は家賃や光熱費・通信費などの一部を経費に計上できる
フリーランスの家事按分経費の対象となるものの例は、家賃、水道光熱費、通信費、交際費、交通費などが挙げられます。それぞれ仕事で使用している割合と家庭で使用している割合に分けて経費として計上します。
家事按分の勘定科目と家事按分の仕訳の例
①家賃を家事按分する場合の仕訳例
家賃10万円、床面積が100㎡の家のうち、25㎡の部屋をオフィスとして事業用で利用している場合
按分計算(面積):按分の割合は25÷100=25%
仕訳の入力方法
事業として使った分を「地代家賃」、プライベートとして使った分を「事業主貸」で記入
| 日付 | 借方 | 貸方 |
| 地代家賃 25,000 | 普通預金 100,000 |
| | 事業主貸 75,000 | |
②インターネット代を家事按分する場合の仕訳例
1ヶ月のインターネット使用料が15,000円、毎月200時間仕事をしてネットを使っている場合
按分計算(時間):按分の割合は200÷720(1ケ月あたりの時間)=28%
仕訳の入力方法
勘定科目「通信費」と、プライベート分を「事業主貸」で記入
| 日付 | 借方 | 貸方 |
| 通信費 4,200 | 普通預金 15,000 |
| | 事業主貸 10,800 | |
生活費を何でも経費にしてしまうと怪しまれて税務調査の対象に
経費として計上できるのはフリーランスとして売上をあげるために支出した費用のみです。私的な生活費や個人的な支出などなんでも経費で落とそうとすると税務署からの指摘を受けたり、ペナルティを課せられる可能性もありますので、十分に注意しましょう。
CHECK
・個人事業主の経費は家事按分が可能
・家賃、水道光熱費、通信費、交際費、交通費などを按分できる
・生活費のすべてを按分できるわけではないので注意
経費にできるかどうか迷ったときの判断基準
経費になるかならないかには、はっきりとした線引きがなくあいまいです。フリーランスが経費として計上できるかどうか迷った場合、以下の判断基準を参考にすると良いでしょう。
事業との関連性があるか
業務上必要なパソコンソフトやツール、電話や、デザイナーの場合はデザインツールなど、それがないと仕事ができないものかどうか、で判断します。
個人的な支出ではないか
フリーランスの場合、どこまでが経費でどこまでがプライベートか迷うことが多くあります。自宅オフィスなどプライベートと共通して使っている場合は按分して経費計算をします。
家族の旅行代や個人の趣味の買い物などはくれぐれも計上してはいけません。
経費として常識の範囲内の金額であるであるか
事業規模に対して適切な割合かどうか、という視点も重要です。大量の備品購入や高級車の利用など、過剰な支出は避けましょう。
税務署から指摘を受けた際に説明できるか
経費として計上するためには領収書、請求書、振込明細書など証拠として示せる書類が必要です。税務署から指摘を受けた際に、それらの経費が事業に関連していることを説明できるようにしておきます。
経費の割合が50%を超えないか
フリーランスの売上に対する経費の割合は50%前後が目安です。上限が定められているわけではありませんが、経費の割合が高過ぎると税務からの調査が入る恐れがあります。
CHECK
・経費にできるかどうかの明確な基準は定められていない
・事業を行うに必要な支出かどうかで判断する
・フリーランスの売上に対する経費の割合は50%前後が目安
経費の領収書の取り扱い方法
領収書は経費として支出をした証明をするために欠かせない書類であり、税務署から決められたルールに基づいて管理をしなければなりません。
領収書は7年間保存が義務に
個人事業主の場合、領収書の保管期限は原則7年間と定められています。紙と電子のそれぞれ、なくさない保管方法で保存しておき、税務署から求められた際にいつでも開示できるようにしておきます。
領収書を紛失した際は出金伝票を用意しておく
領収書が見当たらなくなった場合は、代替証拠となるものをそろえる必要があります。その際に使えるのが出金伝票です。
出金伝票とは取引に関連する支払内容を記録する書類で、領収書が発行されない取引の際に使われるものですが、領収書の代わりとして使うこともできます。
あくまで領収書やレシートがない場合の代替方法なので、多用は避けましょう。
経費計算アプリでこまめに電子データで管理をしておく
会計ソフトのアプリや経費管理アプリを使うと、電子取引データの自動取り込みやレシートのスキャン機能を使い経費データの管理を手軽に行うことができます。ツールを活用して効率的に経費処理が出来て便利です。
CHECK
・領収書は経費として支出をした証明をする大切な書類
・経費の領収書は7年間保存する義務がある
・経費計算アプリを活用してうまくデータ管理を行おう
フリーランスが経費を計上する際の注意点
フリーランスが経費を計上する際に注意することとしては、まずプライベートとの線引きが大きなポイントになります。
自宅オフィスやインターネット料金は按分して業務利用分のみを経費として計上しましょう。
電子取引の領収書やレシートは電子データのまま保存
紙での領収書だけでなく、近年では電子領収書としてPDFファイルや画像データで領収書を受け取ることも多くなっています。
電子領収書が改ざんされていないことを証明するために、受け取った電子領収書はそのままのかたちで保存が必要です。
経費計上に誤りがあり脱税とみなされると重いペナルティに
申告漏れや不正確な申告をしたとみなされた場合はペナルティが課されます。
過少申告加算税
税額を納めるべき金額よりも過少に申告したと判断された場合にその差額に対して課される追加の税金。
重加算税
”故意に”税額を少なく申告した場合に課される税金。過少申告加算税よりも高い税率が課されます。
経費・確定申告など税務に関する相談は迷わず税理士へ
フリーランスだからと言って経費処理や確定申告をすべて自分でしなければならない訳ではありません。大きなトラブルを防止するために、不安なことや分からないことがあれば税理士に相談すると良いでしょう。
CHECK
・フリーランスが経費を計上する際にはプライベートとの線引きがポイント
・電子取引の領収書やレシートは電子データのまま保存する
・わからないことは気軽に税理士に相談しよう
フリーランスが事業をうまく回すためには経費のポイントをしっかり押さておくことが非常に大切です。どこまでが経費の対象になるのか、家事按分の割合など、あとから指摘を受けることがないようにうまく管理して計上しましょう。