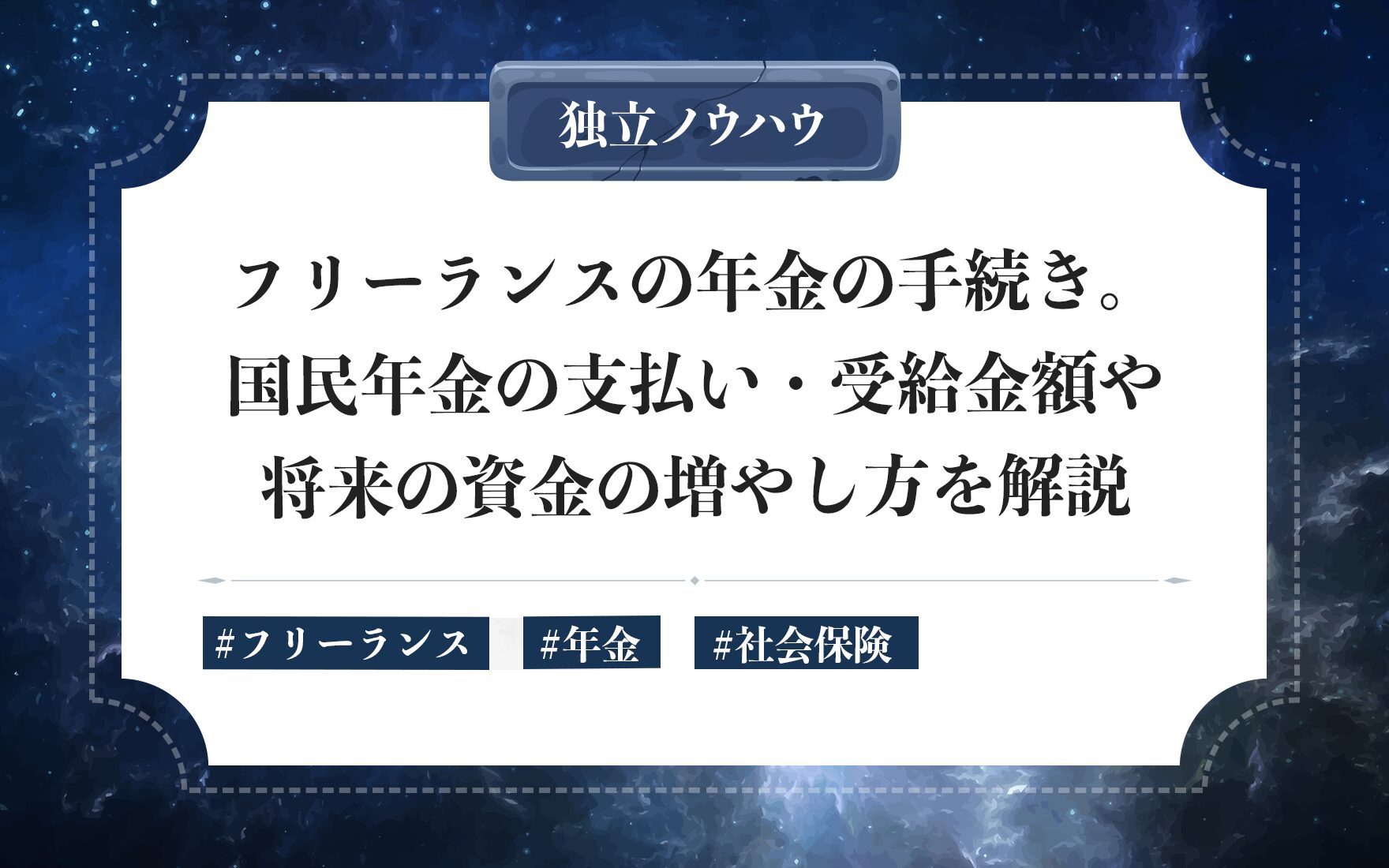フリーランスの年金受給額は、会社員に比べて少なくなります。会社員は「厚生年金」と「国民年金」の二階建て構造で年金を受け取れますが、フリーランスは基本的に「国民年金」の一階部分のみの受け取りになるためです。このため、老後の生活資金確保のため年金だけに頼らず様々な制度の活用を検討する必要があります。
フリーランスは受け取れる年金が少なくなるため、計画的な資産形成が老後の安心につながります。フリーランスになった際に必要な年金関連の手続き及び、年金額を増やすための手法をみていきましょう。
フリーランスになったら国民年金に切り替え
会社員からフリーランスになった際には、会社が手続きを行ってくれていた厚生年金から、自分で国民年金に切り替える必要があります。
国民年金は法律で義務づけられているもので、未加入や未納の場合将来の老齢基礎年金が受け取れないだけでなく、病気や事故で働けなくなった場合の障害基礎年金や、万が一亡くなったときの遺族基礎年金も受け取れなくなるので早めの手続きが必要です。
国民年金加入の手続き方法・納付方法
厚生年金から国民年金への切り替えは、最寄りの市区町村の年金窓口で国民年金の第1号資格取得手続きを行います。その際、以下のものが必要になります。
- 退職を証明する書類
- 身分証明書
- 年金手帳
- 印鑑
手続きは、原則として退職から14日以内に行う必要があります。また、配偶者も扶養に入れる場合は、配偶者の分も国民年金への加入手続きが必要になります。
手続き後、納付書が送付されるので、金融機関やコンビニ、口座振替、クレジットカード払いなどで支払います。毎月の保険料は定額で年度により金額が定められています。
手続きをしないと年金額が減少する可能性も
国民年金は、加入期間に応じて将来の受給額が決まります。そのため、未加入や未納の期間があると老後の年金額が減ってしまう可能性があります。
さらに、一定期間以上の加入がないと、年金をまったく受け取れない場合もあります。フリーランスになったら、できるだけ早く市区町村で加入手続きを行い、保険料を確実に納めることが大切です。納め忘れがあった場合でも、2年以内であればさかのぼって納付することができます。
日本の公的年金は二階建て構造
日本の公的年金制度は「二階建て構造」と呼ばれ、すべての人が対象の「国民年金(1階部分)」と、会社員や公務員などが上乗せで加入する「厚生年金(2階部分)」から成り立っています。
1階部分の国民年金は、20歳以上60歳未満の全国民が対象で、保険料は定額、支給額も一定です。40年間納めた場合の満額は、2025年現在で年約80万円です。2階部分の厚生年金は、主に会社員や公務員が対象で、保険料と支給額は収入に応じて変動します。
国民全員が対象の国民年金
国民年金は日本の公的年金制度で、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。自営業者やフリーランス、学生、無職の人も対象で、2025年度の保険料は月17,510円です。
主に会社員が対象の厚生年金
厚生年金は、日本の公的年金制度の一部で、主に会社員や公務員が加入する年金です。保険料は給与に応じて決まり、勤務先と加入者が半分ずつ負担します。厚生年金の受給額は、加入期間中の平均標準報酬額と加入期間によって計算されるため、収入が多いほど将来の年金額も増えます。
フリーランスにおける厚生年金と国民年金の違い
フリーランスが加入する国民年金は、会社員とは異なる点がいくつかあります。給与天引きされないので自分で支払わなければならないことや、国民年金保険料を控除できることが挙げられます。
フリーランスの場合配偶者も保険料を支払う
フリーランス世帯では、配偶者も国民年金の保険料を自分で納める必要があります。ただし、配偶者が会社員や公務員の被扶養者であれば、第3号被保険者として保険料の支払いが免除されるケースもあります。
フリーランスは年金を控除対象にできる
フリーランスが支払う国民年金の保険料は、「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の計算時に所得から控除できます。
社会保険料控除は、納税者本人だけでなく、生計を同じくする配偶者の保険料も対象です。控除を受けるには、支払った保険料の領収書や納付証明書を確定申告で提出する必要があります。
CHECK
・フリーランスが加入する年金は国民年金
・厚生年金は会社員や公務員が対象
・フリーランスの国民年金保険料は社会保険料控除の対象になる
フリーランスは会社員よりも年金受給額が少ない
フリーランスは原則として国民年金のみに加入するため、受け取れるのは「老齢基礎年金」のみです。一方、会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入しており、「老齢厚生年金」が上乗せされるため、年金受給額が多くなります。また、フリーランスの保険料は定額ですが、会社員は給与に応じた保険料を納め、その額が将来の年金にも反映されます。これらの制度の違いにより、フリーランスの年金額は会社員より少なくなる傾向があります。
国民年金の月額保険料の計算
国民年金の月額保険料は、全国一律の定額制で、年ごとに国が決定します。最新の保険料は日本年金機構のホームページで確認できます。
国民年金保険料は月々17,510円
国民年金の保険料は、収入や職業に関係なく定額になっています。ただし、前納割引や口座振替割引など支払い方法や制度によって割引が適用されることがあります。
前納制度による割引も受けられる
国民年金の前納制度は、保険料を一定期間分まとめて前払いすることで割引を受けられる仕組みです。6ケ月、1年、2年分をまとめて支払うことができます。
たとえば、2年分をまとめて支払う「2年前納」では、毎月納付する場合と比べて2年間で約17,000円の割引が受けられます。前納を希望する場合は、事前に申出書の提出が必要で、納付書に記載された期限までに支払う必要があり、早めの手続きが大切です。
フリーランスの実際の支給年金額はいくら
フリーランスが受け取る公的年金は、原則国民年金のみです。保険料を40年間納めた場合の満額は年額816,000円(月額68,000円)ですが、納付期間が短かったり、保険料の免除があった場合は受給額が減少します。厚生年金にも加入している会社員と比べると年金額は少ないと言えます。
受給開始年齢は原則65歳から
フリーランスが受け取る公的年金(国民年金)は、原則として65歳から受給が開始されますが、60~75歳の間で受給開始時期を選ぶことができます。これを繰上げ受給・繰下げ受給と呼びます。
受給額と計算方法
フリーランスが受け取る国民年金は満額で年額816,000円(月額68,000円)です。これは20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)全て納付した場合の額で、納付月数が少ないと減額されます。
計算式:国民年金受給額 = 基準額(816,000円) × 保険料納付月数 ÷ 480
納付期間・繰上げ/繰下げ受給・厚生年金加入歴で金額が上下
フリーランスが受け取る年金額は、保険料を納めた期間や受給を始める年齢によって変わります。通常は65歳から受給開始ですが、60~64歳で受け取る「繰上げ受給」を選ぶと、1ヶ月ごとに0.4%ずつ減額され、最大で30%減額されます。
一方、受給開始を遅らせて66~75歳で受け取る「繰下げ受給」を選ぶと、1ヶ月ごとに0.7%増額され、最大84%増額となります。
CHECK
・国民年金の保険料は収入など関係なく定額制
・年金の受給開始年齢は原則65歳から
・繰上げ受給・繰下げ受給で受取金額が変動する
フリーランスができる将来もらえる年金額を増やす方法
フリーランスは会社員と違って厚生年金に加入できず、将来受け取れる年金額が少なくなる傾向があります。そのため、老後の生活資金が不足するリスクが高くなります。
安心した老後を迎えるためには、早い段階から年金以外の資産形成も含めた準備を始めることが大切です。今のうちから少しずつ備えることで、将来の経済的負担を軽減することができます。
国民年金基金で2階建て年金に
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者が利用できる、公的な年金の上乗せ制度です。
老後の年金をより手厚くするための仕組みで、将来の備えとして有効です。加入は、全国国民年金基金の公式サイトから必要書類をダウンロードし、郵送で申し込みます。
付加年金で手軽に支給額を増やす
付加年金は、フリーランスや自営業者など国民年金第1号被保険者が利用できる、少額で効率的に年金を増やせる制度です。
月額400円を国民年金保険料に上乗せするだけで、「200円 × 納付月数」分の年金が一生涯にわたり加算されます。ただし、国民年金基金との併用はできないため注意が必要です。加入手続きは市区町村の窓口で行います。
iDeCo(個人型確定拠出年金)で所得税控除をしつつ資産形成
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」の略で、自分で年金資金を積立て・運用し、老後に年金や一時金として受け取れる制度です。
特にフリーランスにとっては、将来の年金対策と資産形成を両立できる有効な手段です。掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果も期待できます。金融機関によって手数料や運用商品が異なるため、事前に比較・検討が大切です。加入は、選んだ金融機関で申し込みを行います。
小規模企業共済で退職金を積み立てつつ節税
小規模企業共済は、フリーランスや個人事業主が自分で退職金を積み立てながら節税できる、国が運営する共済制度です。
廃業や引退時に退職金を受け取ることができ、税制上も優遇されています。加入手続きは委託団体や金融機関の窓口で行います。長く続けるほどメリットが大きいため、早めの加入で老後の安心と節税効果を高めることができます。
個人年金保険で将来のリスクに備える
個人年金保険は、公的年金の上乗せを目的に保険会社が提供する保険商品です。自分で保険料を積み立て、一定期間後や老後に年金として受け取る仕組みで、老後の収入を安定させる役割があります。選ぶ際は、運用利回りや保障内容をよく比較することが重要です。
年金だけでなく今からさまざまな資産形成をしておく
会社員のように厚生年金や企業の退職金制度がなく、公的年金だけでは老後の生活費が不足するリスクが高いフリーランスにとって、資産形成は非常に重要です。
早いうちから貯蓄や投資、iDeCoや小規模企業共済などの制度を活用し、リスクを分散しながら着実に資産を築いていきましょう。
CHECK
・年金額を増やす方法はいくつかある
・公的制度だけでなく民間制度も活用する
・早いうちから老後を見据えた資産形成をすること
フリーランスにとって、年金だけに頼る老後資金計画はリスクが高く、貯蓄や投資、公的制度などをうまく活用して計画的に資産形成をすることが大切です。基礎となる国民年金はきちんと納付しつつ、リスク分散を心掛けながら賢く老後資産を作っておきましょう。