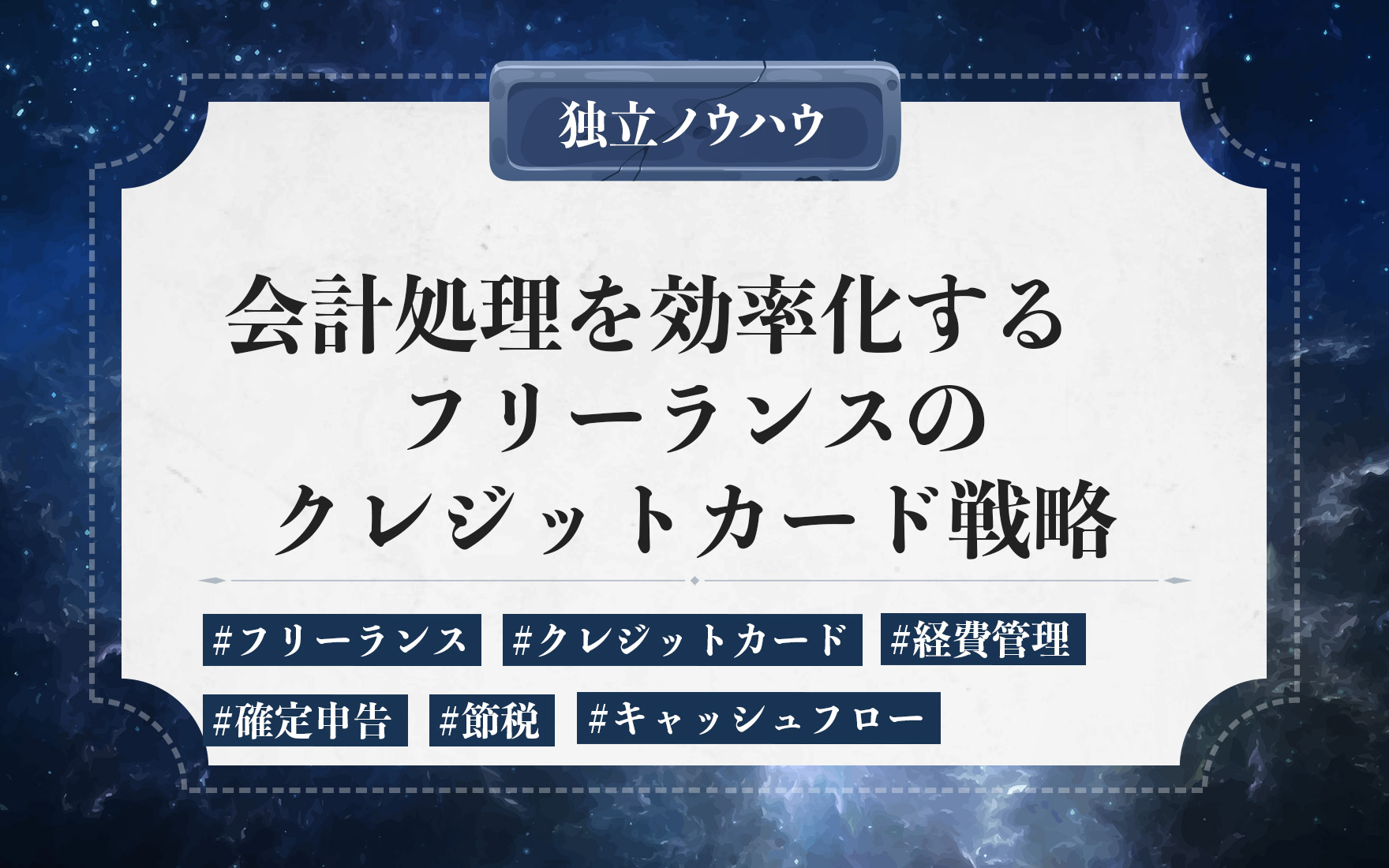フリーランスとして独立すると決めたらまず作っておきたいのがクレジットカード。独立後ではなく独立前の準備段階で作ってしまいましょう。
独立前にこそフリーランスはクレジットカードを作るべき
開業準備時にはさまざまなものが必要になります。オフィスを借りる、家具や備品を購入するなど、物を買う機会が出てくる独立前にこそ、クレジットカードを作っておくとポイント利用ができて経費削減につながります。確定申告をしようと思ったら開業時の領収書が見つからないといったことにならないように、独立前に1枚はクレジットカードを作っておいた方がよいでしょう。
プライベートで使うクレジットカードと事業用に使うクレジットカードは別々にするのがおすすめです。事業用のクレジットカードを独立して持つことで、ビジネスにまつわる会計処理がぐっと楽になりますよ!
フリーランスがクレジットカードを使う理由
フリーランスとして事業用クレジットカードを作るべき理由は多くあります。プライベート用と事業用でカードを分けることで、経費の管理や確定申告などの会計処理がスムーズになるのが大きなメリットです。
経費管理の効率化
収支を管理するために使われている会計ソフトには、クレジットカードとの連携機能があります。カード支払いを行った際に自動でデータが蓄積されるため、領収書をもらって会計ソフトに手入力する手間を省くことが出来ます。
確定申告の手続き簡素化
確定申告をスムーズに行うには、日々の収支の記録をいかにわかりやすくまとめているかが重要です。会計ソフトとクレジットカードを連携させて取引明細を自動処理することで、確定申告の書類作成が楽になります。
節税対策(年会費の経費計上、ポイント還元)
事業用クレジットカードの年会費は「支払手数料」として経費計上できます。また、事業に関連する支払いは大きな額のものも多くポイントがたまりやすくなります。貯めたポイントを交換したりキャッシュバックしながら経費節減につなげましょう。
ビジネスに役立つ特典の利用
法人用のクレジットカードにはビジネスシーンを応援するサービスが充実しています。チケット優待サービス、空港ラウンジ利用、会計ソフトの料金優遇、福利厚生サービスの優待利用など、カードごとにさまざまな特典があるので比較検討してみましょう。
キャッシュフローの改善
法人用のクレジットカードは個人向けのクレジットカードと比べて利用限度額が高く設定されており資金繰りに役立ちます。また、カード利用日から実際の支払いまで時間のゆとりがあるので、キャッシュフローをコントロールしやすいのもメリットです。クレジットカードでの支払い設定をすることで、家賃、光熱費、税金などバラバラな経費の支払日も固定化することが出来、支払いの見通しを立てやすくなります。
CHECK
独立準備段階でクレジットカードを作っておくのがおすすめ
ビジネス用のクレジットカードを作ることで経費管理や確定申告の手続きが楽になります
法人カードによってはビジネスシーンに役立つ特典があるので要チェック
フリーランスはビジネスカードを必ずしも選ばなくても良い
クレジットカードには「個人カード」と「法人カード(ビジネスカード)」の2種類が存在します。法人カードは経営者の信用情報に加え、法人としての信用力も審査対象となります。
個人事業主として持っておきたいクレジットカードとしては個人用でも法人用でもどちらでも問題ありません。クレジットカードを使う目的を整理して、ポイントを絞って自分に合ったカードを選びましょう。
フリーランスがクレジットカードを選ぶポイント
クレジットカードを作る際には、次の項目をチェックしながら自分に合ったカードを選ぶことが大切です。
- 年会費
- 利用限度額
- 付帯サービス
- ポイント還元率
- 飲食店などの割引サービス
独立したばかりの場合は、年会費無料のカードから始めるのが無難です。事業用の経費が高額になる場合は利用限度額が高いもの、経費削減を意識したい場合はポイント還元率の良いものを選びましょう。
年会費無料のおすすめカード
楽天カード
年会費が永年無料で、楽天市場などの楽天グループでのサービスで利用すると高い還元率でポイントが貯まります。
ポイント高還元のクレジットカード
PayPayカード
最大1.5%のポイント還元を狙える、特典でもらえるポイントが多い、公共料金の支払いでもポイントが貯まる、無期限でポイントを利用できるといったポイントの使いやすさが魅力のカード。
リクルートカード
常時還元率が1.2%と高還元率でポイントがすぐ貯まる、貯まったポイントがPonta・dポイントに即時交換できるところが人気のカード。
旅行保険が充実したカード
エポスカード
取材などで出張が多い人は是非考慮したい旅行保険付きのクレジットカード。海外旅行保険の利用付帯、手厚い補償内容、エポスカード海外サポートデスクが世界各国にありトラブル時も現地で日本語対応が可能です。
付帯サービスがあるカード
クレジットカードの付帯サービスには様々なものがあります。自分の利用シーンに合った特典がついているカードを選びましょう。
特典例
- ショッピング割引や特典
- 人気のホテルや旅館にお得に宿泊
- 空港ラウンジの無料利用
- 航空マイルやポイントプログラム
- 割引やキャッシュバック
- 各種保険
経費管理機能があるカード
日々の帳簿や確定申告の手続きを楽にしたい場合は、会計ソフト会社が出しているクレジットカードがおすすめ。会計ソフトとのスムーズな連携により、経理の処理にかかる時間を大幅に削減できるだけでなく、年会費・発行手数料無料、開業直後のカード発行可能など使いやすいポイントが詰まっています。
freeeカード Unlimited
マネーフォワード ビジネスカード
分割払いやリボ払いの選択があるカード
分割払い(利用金額の支払回数を指定して支払う方式)やリボ払い(設定した一定の金額を毎月支払う方式)をする可能性があるのであれば、条件や手数料をきちんと確認してカードを選びましょう。リボ払い専用カードというのもあります。
CHECK
クレジットカードには個人用カードと法人用カードがある
法人用カード(ビジネスカード)はビジネスに特化した特典がついている
年会費やポイント還元率などを比較し自身のビジネスサイズに合ったカードを選ぼう
フリーランス向けビジネスにも使えるクレジットカード
法人向けのビジネスカードの大きな魅力は利用限度額が大きいところ。事業用のクレジットカードを作った場合、フリーランス運営に関わるあらゆる経費を支払うことになるのでクレジットカードの利用限度額が大きいほうが安心です。
限度額だけでなく、ビジネスシーンに役立つ特典や優待サービスが多くあるのがビジネスカードの特徴なので、ご自身のビジネス規模や支払いサイクルに合わせて検討しましょう。
三井住友カード ビジネスオーナーズ
スタートアップ企業や副業・フリーランス向けの法人カード。申込時の登記簿謄本などの書類提出が不要で気軽に作りやすい法人カードです。東海道新幹線のネット予約&チケットレスサービスや福利厚生代行サービスなど付帯サービスも充実しています。スタートアップ企業や副業・フリーランス向けの法人カード。申込時の登記簿謄本などの書類提出が不要で気軽に作りやすい法人カードです。東海道新幹線のネット予約&チケットレスサービスや福利厚生代行サービスなど付帯サービスも充実しています。
JCB CARD Biz
個人事業主特化型JCBカード。インターネットで申し込み完結でき、法人カードにも関わらず個人与信なので本人確認書類のみで申請可能です。フリーランスがひとりで使う法人カードとして人気があります。
楽天カード
楽天プレミアムカードの特典に加え、接待・出張・オフィス環境の充実・ビジネスツールなどに使える多彩なサービスが利用可能。ETCカードを複数枚作れるところも魅力です。
セゾンコバルト・アメリカン・エキスプレスカード
個人事業主やスタートアップ企業のために特化した法人カードで、登記簿謄本などの提出不要で開業前でも気軽に申し込めます。レンタルサーバーやクラウドサービスの優待利用などビジネスに特化した特典があります。
オリコ EX Gold for Biz S
フリーランスなど個人事業主向けのオリコ法人カードです。オリコの証書貸付やローンカードの金利が優遇されるサービスがある他、freee会計の有料プランが3ヶ月分お得になります。
フリーランスのクレジットカードに関するFAQ
申し込むカードが決まった後、実際にカードの申し込みをした後によく出てくる疑問への答えをまとめました。
申込時の職業・勤務先はどのように書くべき?
職業欄には「屋号」、勤務先欄には「就業している場所の住所」を記入します。屋号がない場合は個人名や個人事業主と記載することも可能ですが、一般的に屋号がある方が信用度が上がると言われています。
審査に落ちた場合はどうするべき?
すぐにクレジットを使う必要がない場合は、数ヶ月期間を空けてから再度申し込んでみましょう。収入や実績が向上していれば再審査で通る可能性があります。
すぐにでも使いたい場合はクレジットカードではなくデビットカードの検討がおすすめです。デビットカードとは利用と同時に引き落とし口座から利用代金が引き落とされるもので、与信審査がなく作りやすいのがメリットです。
フリーランスは複数枚持つべき?
1人で事業を行っている限り、ビジネス用のクレジットカードは1枚で十分です。カードごとに異なるさまざまな特典や優待サービスを受けたい場合はプライベート用のカードとして契約しましょう。
法人化して社員を雇用する場合は、法人カードのサービス内の追加カードとして社員用に新たにカードを追加できます。
キャッシング機能はつけるべき?
フリーランスがクレジットカードを使う大きな目的は資金調達と会計処理の効率化です。
分割やリボ払いと同じようにキャッシング機能は手数料もかかるため積極的な活用はおすすめしません。
CHECK
登記簿謄本などの提出不要で本人確認のみでつくれるビジネスカードはフリーランスでも作りやすくておすすめ
分割払い、リボ払い、キャッシング機能など手数料がかさむサービスは極力使わない
クレジットカードの審査が通らなかった場合はデビットカードも選択肢に
個人事業主やフリーランスに特化したビジネスカードがあるほど、フリーランスにとって必要不可欠なクレジットカード。ビジネスを加速させ、効率化アップをさせてくれる頼もしい存在です。