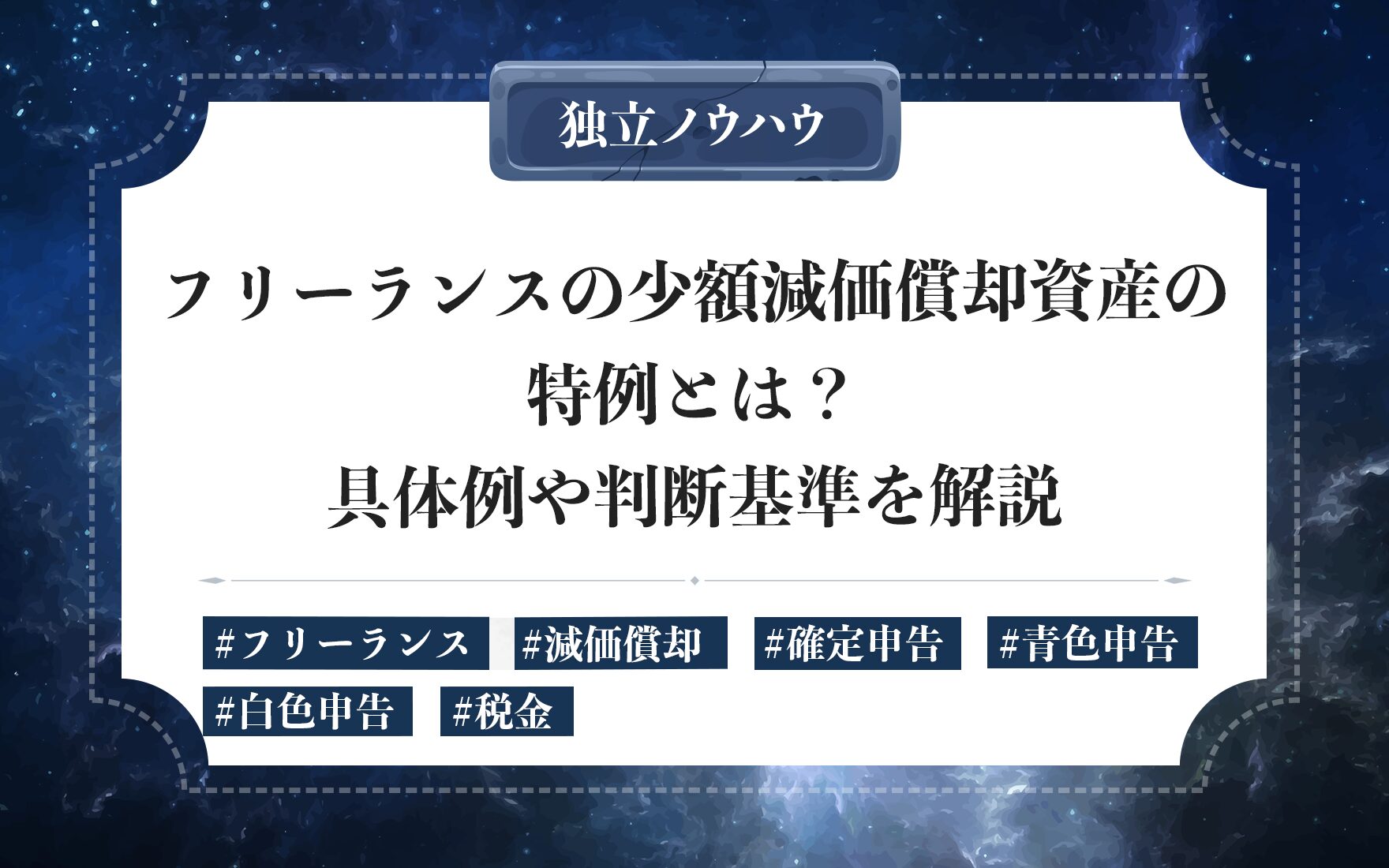固定資産を一定期間にして会計処理する減価償却は、節税効果やキャッシュフローの改善といったメリットのあるものです。適用方法にはいくつか選択肢があります。フリーランスと減価償却について詳しく知りましょう。
減価償却資産に該当する資産は原則として減価償却を行い、耐用年数に応じて割って費用に計上する必要があります。フリーランスの場合は特例適用することで減価償却せずに一括経費計上ができる場合もあります。
フリーランスは30万円未満の減価償却資産は一括経費計上できる
フリーランスは、30万円未満の減価償却資産に関しては少額減価償却資産の特例を利用して一括経費計上が可能です。パソコンを買い替えたり、新しいソフトを導入したり、オフィスの引っ越しをした際など、通常よりも必要経費が増えた年度に使える制度を知っておきましょう。
そもそもフリーランスの経費と減価償却とは
まず、「経費」とは事業活動を行うために必要な支出のことです。
一方「減価償却」とは固定資産を耐用年数に応じて分割計上することを指します。減価償却により発生した「減価償却費」は経費の一部となります。
減価償却の対象になる資産や金額は定められていますので、資産ごとの耐用年数や減価償却方法を確認しておくことが重要です。
経費計上の減価償却は分割して経費化すること
減価償却とは、長期間使用する資産の価値を複数年で分割して経費として計上する処理のことです。
事業の運営に使用する固定資産の中で時間の経過とともに価値が減っていくもので、取得価額が10万円以上、耐用年数が1年以上のものが対象となります。
減価償却の定額法と定率法の違い
減価償却には主に定額法と定率法の2つの方法がありますが、フリーランスの場合は「定額法」を使用することが一般的です。
定額法のメリットとして、毎年同額の減価償却費を計上できてわかりやすく計算が簡単ということが挙げられます。
定額法:毎年均等に減価償却を行う方法です。資産の取得金額をその耐用年数で割り、毎年同じ減価償却額を経費として計上します。
定率法:初年度に多く減価償却し、減少した金額で償却する方法です。最初のうちは高い額が経費として計上され、その後は徐々に減少します。
そもそも経費になる例・ならない例
事業活動を行うために必要な支出は経費として計上できますが、プライベートなど業務と関係ない支出は経費として認められません。経費になる例・ならない例を以下表でまとめています。
| 計上できる例 | 計上できない例 | ||
|---|---|---|---|
| 事業関連 | 外注費 | 営業やマーケティング関連業務などの外注料金やライターやデザイナーへの報酬 | 家事代行など業務とは無関係な代行 |
| 広告宣伝費 | インターネット広告、チラシ広告、SNSやインフルエンサーとのコラボ費用や名刺作成費用など | – | |
| 通信費 | 事業用の電話代、インターネット代、モバイル通信費用 | 家の固定回線など業務では使わないもの | |
| 事務用品費 | 事務所で使用する文房具や消耗品、コピー用紙など | プライベートで利用するもの | |
| 消耗品費 | 電池、事務用品など業務で使うもの | プライベートで利用するもの | |
| 接待交際費 | クライアントとの打ち合わせカフェ代や会食費、贈答品 | 業務に関係ない飲食代 | |
| 交通費 | 業務に関連する電車代やタクシー代、ガソリン代 | 個人的な移動の交通費 | |
| 旅費交通費 | 出張費用としての飛行機や新幹線、宿泊費用 | 個人的な観光などの費用 | |
| オフィス関連 | 家賃 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | – |
| 光熱費 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | – | |
| 保険料 | 事業用の損害保険や生命保険 | 事業主自身の保険料 | |
| 設備投資 | パソコンやオフィス家具、カメラ機材など、事業に必要なもの | プライベートで利用するもの | |
| ソフトウェア費用 | 業務で使用するソフトウェアの購入費用やサブスクリプション費用 | プライベートで利用するもの | |
| 人件費 | 給与 | 社員やアルバイトへの給与 | – |
| 社会保険料 | 雇用保険や健康保険、年金などの社会保険料 | – | |
| 教育・研修関連 | 研修費 | 業務やスキルアップに関連する研修やセミナーの参加費用 | – |
| 書籍費 | 業務に役立つ書籍や資料購入代金 | 個人の趣味で購入したもの |
経費化できる減価償却の対象となる資産
フリーランスの減価償却の対象となる主な資産は以下の通りです。経費と同じく、事業に関連するもののみが対象になります。
- パソコン・タブレット・スマートフォン:仕事で使用するパソコン、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど。
- オフィス機器:プリンター、スキャナー、コピー機、FAXなど、業務で使用する電子機器。
- ソフトウェア:会計ソフトやデザインソフトなど業務で使用するソフトウェア。
- 車両:事業用に使用する自動車やバイク、トラックなど。
- 家具・備品:事務所で使用する机、椅子、棚、書類整理用のキャビネットなど。
- 建物:事業用に借りている事務所や店舗。
※プライベートで使用しているものは減価償却対象になりません。
業務に使用しない固定資産や、時間が経っても価値が減少しない固定資産に関しては、減価償却の対象にはならず、大きな例で言うと土地は減価償却の対象ではありません。
減価償却の分割は耐用年数により決定されている
減価償却を行う場合、税務署が定めた耐用年数に基づいて償却します。主な資産の耐用年数は以下の通りです。
| 資産の種類 | 耐用年数 |
| パソコン・タブレット | 4年 |
| 携帯電話・スマートフォン | 10年 |
| プリンター・コピー機・スキャナーなどの事務機器 | 5年 |
| ソフトウェア(業務用) | 5年 |
| 事務机、いす及びキャビネット(金属製のもの) | 15年 |
| 事務机、いす及びキャビネット(金属製以外のもの) | 8年 |
| カメラ | 5年 |
| 自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| バイク | 3年 |
| 自転車 | 2年 |
さらに詳しい耐用年数は国税省の減価償却ページもご確認ください。
CHECK
・価値が時間とともに減少する固定資産は減価償却する
・フリーランスは30万円未満の減価償却資産は一括経費計上できる
・対象資産や分割年数は法で決められている
少額減価償却資産の特例で一括で損金算入する
少額の減価償却資産とは取得価格10万円未満の資産のことを指し、この資産に関しては減価償却せずに費用を全て経費計上することができます。
これに加えて、青色申告法人である中小企業者の場合は「少額減価償却資産の特例」が適用となり、購入金額が10万円以上30万円未満の資産についてその年に一括で経費計上できます。これは青色申告を行っているフリーランスも対象となっており、一括で減価償却することで税負担軽減につなげられます。
少額減価償却資産の特例の概要
少額減価償却資産の特例とは、10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合に合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)が認められる制度です。青色申告をしている中小企業および個人事業主が対象となっています。
減価償却の手続きを避けたい場合や、経費を増やして利益額を減らすことで減税対策をしたい場合に有用です。
少額減価償却資産の特例の対象となる資産は取得価格が30万円未満
1つあたりの取得価格が30万円未満かどうかで対象になるか判断されます。
また、自社の経理処理が消費税込みで処理をしているか、税抜きで処理をしているかによって、判断する価格が変わってくることにも注意しましょう。
少額減価償却資産の特例の上限は事業年度で300万円までが対象
1年間に特例として計上できる資産の上限額は300万円となっています。300万円を超えるものに関しては適用外となります。
ひとつの資産を特例の対象と対象外に分けることはできないため、上限金額ぎりぎりまで使いたいので資産を分けて計上する、ということはできません。
少額減価償却資産と一括償却の償却方法の違い
「少額減価償却資産の特例」とは別に、「一括償却資産制度」による減価償却手法もあります。
一括償却資産とは、すべての事業者を対象に10万円以上20万円未満の減価償却資産を3年間で均等償却できる制度です。
例えば15万円(10万円以上20万円未満の)のパソコンを購入した場合にできる処理方法は以下の3パターンになります。
①耐用年数に応じて減価償却
②一括償却資産として処理
③少額減価償却資産の特例で処理(青色申告をしている場合)
| ①耐用年数に応じて減価償却 | ②一括償却資産として処理 | ③少額減価償却資産の特例で処理 | |
| 償却年数 | 4年(パソコンの耐用年数が4年) | 3年(3年の均等償却が適用される) | 1年(即時償却が可能) |
| 会計処理 | 初年度:減価償却費 3万7,500円2年目:減価償却費 3万7,500円3年目:減価償却費 3万7,500円4年目:減価償却費 3万7,500円 | 初年度:減価償却費 5万円2年目:減価償却費 5万円3年目:減価償却費 5万円 | 初年度:減価償却費 15万円 |
少額減価償却資産の特例の適用には青色申告が必要
少額減価償却資産の特例を適用できるのは、青色申告書を提出している事業者のうち、常時使用する従業員数が500人以下である事業者に限定されています。
特例を適用したい場合は、青色申告で確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
少額減価償却資産の特例は節税にメリットがある
少額減価償却資産の特例を使う大きなメリットは節税効果です。実際に支払った金額を同じ年度のうちに経費として計上することで利益額を抑え、課税対象額を低くすることで節税効果を得られます。
CHECK
・フリーランスは少額減価償却資産の特例が適用される
・少額減価償却資産の特例により年300万円まで全額損金算入可能
・少額減価償却資産の特例は節税にメリットがある
少額減価償却資産の特例を適用する注意点
少額減価償却資産の特例は、10万円未満の減価償却資産や一括償却資産との違いを理解しどれが最適なのかを判断して選択する必要があります。
また、資産の購入金額が基準を超えている場合や事業用途でない資産には適用されないので注意しましょう。
節税対策になる一方で利益が減るケースも
少額減価償却資産の特例を利用すると、その年度に全額を経費として計上するので帳簿上の利益額が減少します。
利益が減少することは、税負担軽減や資金繰り改善に有利である反面、銀行からの融資を受けにくくなるなどのメリットもあります。
消費税の処理の方法で会計の扱いが変わる
インボイス制度により免税事業者と課税事業者のどちらかを選択するフリーランスが出てきました。免税事業者は消費税の納付義務が免除されており税抜きで会計を行います。
課税事業者は消費税の納税義務があり、税込みで会計を行います。少額減価償却資産の特例が適用される30万円までに費用が収まるかどうか、税抜きか税込みのどちらで判断するべきなのか自社の会計方法をきちんと把握しておく必要があります。
CHECK
・少額減価償却資産の特例を適用するには注意が必要
・短期的な利益の減少によるデメリットもある
・消費税の処理の方法で会計の扱いが変わる
減価償却は、フリーランスにとって節税やキャッシュフローの改善に有効な手段です。特に、30万円未満の資産には一括経費計上ができる特例があり、これを活用することで税負担を軽減し、経営の安定性を高めることができます。