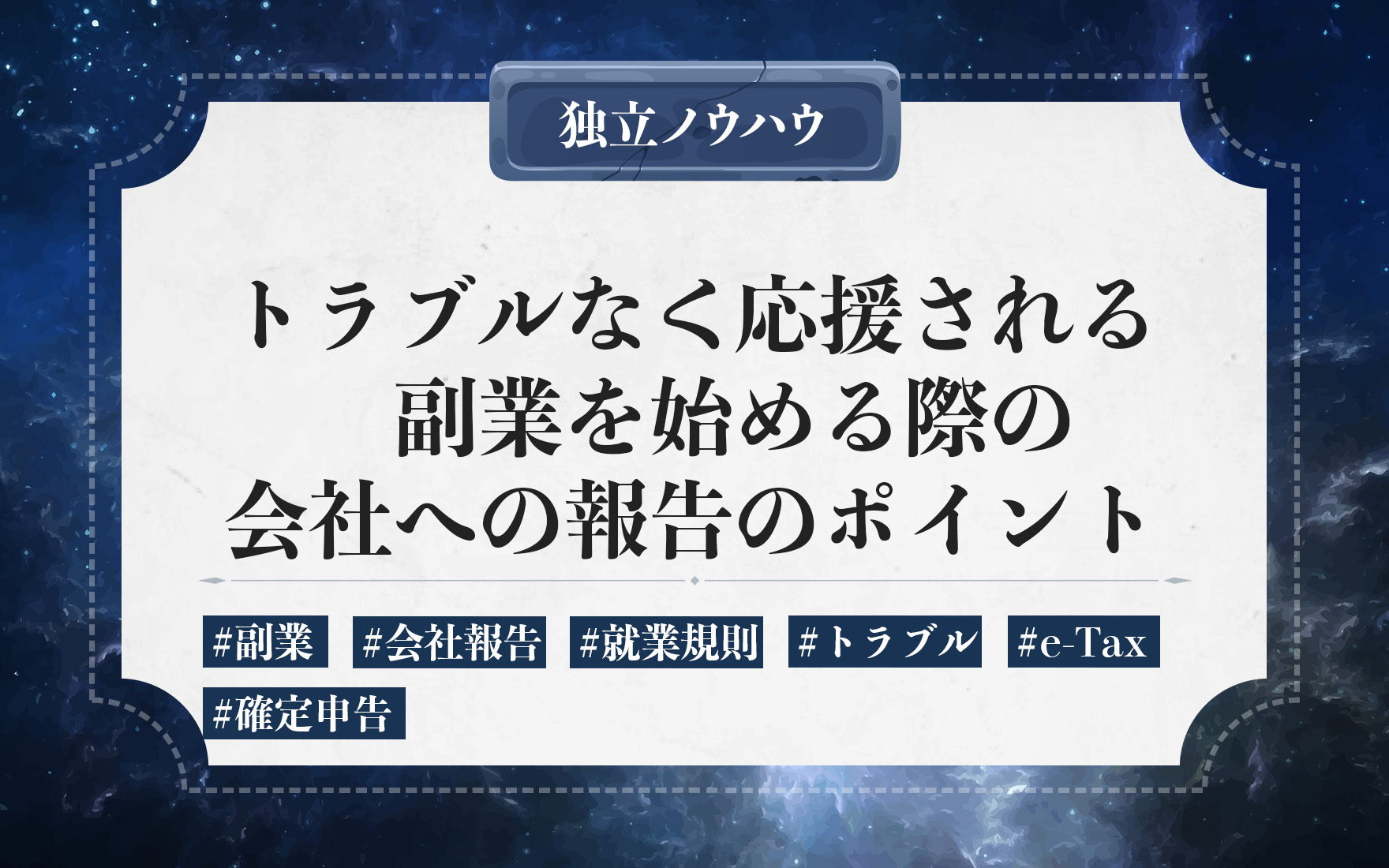多様な働き方が尊重される中で、副業が推奨される社会になってきました。副業を始める際は就業先へ報告や税務署への開業届などすることがいくつかあります。就業先の会社には副業をする旨を伝えたほうがいいのか?伝えなくてもいいのか?と気になっている方のために副業・兼業を始める時に気を付けるべきこと、ルールやフローについて詳しくご紹介します。
副業を就業先の会社に隠す必要はありません!副業をする前に必ず会社に報告してから始めましょう。会社に伝える際は、就業規則を確認し、自分のキャリアプランや会社へメリットがあることも合わせて伝えることでスムーズに始めやすくなりますよ。
副業をする際は必ず会社に報告をする
副業を始める際は、まず就業先の会社にきちんと報告が必要です。会社に報告をしなくても副業をすることはできます。
また、何かトラブルになることもありません。しかし、はじめに報告しておいたほうがリスク回避になり周りの協力を得られるので、結果的にメリットとなります。
副業を始めるということは、自分のキャリアの可能性を広げる一歩を踏み出すこと。
堂々と自分のキャリアづくりを進めましょう。そのためにも、まず会社からの理解を得たほうが心強いですよね。
一方で、会社によっては副業の申請が必要だったり副業が禁止されていたりする場合もあります。副業禁止の規則を守らず副業を行うと懲戒処分の対象となる可能性があるので、注意が必要です。
会社員の副業は法律で禁止されてはいない
少子高齢化が進み労働力不足が課題となっている中、働き方改革の一環として副業が解禁されました。人々の働き方の選択肢が拡大し、興味のある分野を経験しながら、スキルアップにチャレンジする人が増えています。
ATTENTION
政府主体で副業・兼業を推奨している
働き方改革に伴い、政府は副業・兼業の促進や柔軟な働き方を推奨しています。副業を許可することで従業員のスキルアップやモチベーションの向上から離職率の低下につながるなど、企業側にとっても良い効果があり、推奨する会社が増えています。
就業規則によって副業を禁止している会社もある
副業を禁止する法律はありませんが、会社によっては副業を禁止している場合もあります。そのため、勤務先の就業規則の確認が必要です。ちなみに国家公務員・地方公務員は副業が禁止されています。
副業を認めている会社でも事前に許可が必要な場合もある
副業禁止となっていなくても、制約がある場合もあります。
例えば「競合する業種・企業での副業は禁止する」「副業は会社の許可が必要」など条件が定められていることがありますので方針をきちんと確認し、会社の定める承認フローに沿って上司や人事へ適切に報告しましょう。
CHECK
会社員の副業は法律で禁止されていません
会社の規則で副業が禁止されている場合があります
会社によっては事前に許可を取る必要があります
副業に関する就業規則別の会社に報告する具体的な流れ
まずは、就業規則を確認し、決められた方法に沿って会社に副業を開始する旨を報告します。その後、役所に開業届を出せば副業の申告は完了です。
会社の就業規則で副業禁止の規定がないか確認する
副業を始めようと思ったら一番初めにすることは就業規則の確認です。
会社によっては就業規則で副業禁止としている場合もあり、どの会社に所属をしていたとしてもまずは就業規則を確認し、自分の勤める会社の規則に応じて手続きをしましょう。
具体的には、就業規則の中にある「副業・兼業」もしくは「禁止事項」の章に書かれている規則を確認します。
副業許可申請書を記入して本業の会社へ提出する
就業規則で「他の会社等の業務に従事することができる」といった内容が書かれていれば副業OKです。「事前に会社に所定の届け出を行うものとする」「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」などがある場合は、会社へ申請書を提出します。
副業が完全許可制の場合
- 届け出の必要はないが、上司には一言入れておく
- 届け出をしなければならないと規則に書かれていなければ申請書の提出は必要ないですが、上司には報告しておくと良いでしょう。
副業が原則許可制の場合
- 既定の手順で会社の許可を取りに行く
- 申請を出せば基本的に副業OKの場合は、既定の手順で会社に報告し副業の許可をもらいます。
- 申請却下される心配はないので、きちんと申請を出しましょう。
条件付きで副業が許可制の場合
- 審査を経て副業許可が出る場合や、副業をする理由などを会社に詳しく伝えるよう求められている場合は、伝え方に注意が必要です。
- 副業をする理由は、「収入を増やしたいため」と簡単に書くよりも「子どもの学費や親の介護費用を稼ぐため」「スキル取得のため」などと具体的に書き、嘘は書かないようにしましょう。
- 副業をすることでスキルを得て本業に還元できるなど会社にとってメリットがある旨もアピールすると良いでしょう。
副業が就業規則で完全に禁止されている場合
- もし会社にばれた場合は懲戒処分の対象となる可能性もあります。禁止されている場合は、副業をひかえましょう。
副業の業務内容を決めて開業届を出す
就業先から副業の許可をとれたら、役所に開業届を出します。
開業届とは、新たに所得を得る事業を始める人が出す届け出のことで、本業・副業問わず届け出が必要です。個人事業主やフリーランスとして活動している人だけでなく、副業の場合も必ず届け出が必要になります。
開業届の内容を確認する
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)や開業届支援ツールを使ってオンライン申請ができますのでシステムにログインして、どんな項目があるのかまず確認します。税務署や国税庁のホームページで開業届用紙をPDFでダウンロードすることもできます。
ATTENTION
開業届に書く内容を決める
- 開業届の項目の中には「事業の概要」として業務内容を書く欄があります。どんな仕事をする予定なのかある程度決めておく必要があるので、自分がやりたい事、挑戦したい事を整理しておきましょう。
必要書類と共に提出
- オンライン申請もしくは直接or郵送で税務署窓口へ提出します。提出時期は特に決まっていないので、思い立ったら早めに届けを出してしまえば大丈夫です。
副業からの所得額が20万円を超えると確定申告も必要
1月1日から12月31日までの副業所得が20万円を超える場合は確定申告も必要になります。副業所得とは、副業で得た売上金額ではなく経費を差し引いた額のことです。
副業を始める際に購入した機器・ツールの領収書や、月々のネット使用料などはまとめておくと便利です。売上から必要経費を引いた金額が20万円を超えそうな場合は確定申告の準備をしておきます。
CHECK
まず会社の就業規則を確認しましょう
上司へ報告し、必要な場合は副業許可申告書を提出します
税務署へ開業届を提出して副業の届け出は完了です
副業をして懲戒処分を受けてしまうケース
就業規則で副業禁止とされている場合、規則を破って副業をしているのがばれた場合、懲戒処分を受ける可能性があります。副業が認められている場合も、明らかに会社にとって不利益が生じた場合は罰則が課されることがあります。
会社の定めるルールや規定に違反し、会社の信用や利益に深刻な損害を与える行為に対して行われるのが懲戒処分です。
「警告」、「減給やボーナスはく奪」、「降格」や、さらには「解雇」といった措置が取られます。さらに、副業をする際には、体調管理とともに情報漏洩などに十分注意しながら業務にあたる必要があります。
ケース例1:他社への情報漏洩で会社に不利益を被らせた場合
特に気を付けたいのが情報漏洩です。意図的に情報漏洩するのはもちろんNGですし、自分でも気づかぬうちに情報漏洩のリスクを犯している場合もあります。以下のようなケースに当てはまらないか確認が必要です。
- 会社支給のパソコンを使って副業をしている
間違って機密情報が外部に漏れる可能性があります
- 副業で使用するパソコンのセキュリティ対策をしていない
不正アクセスやハッキングによって機密情報が漏れる可能性があります
- 就業先の顧客情報や商品情報を副業先に伝える
企業の財産である情報を安易に外部に伝えることは機密情報漏洩にあたります
ケース例2:副業が原因で会社の信用に悪影響をもたらせた場合
副業として関わった業務が不正に関連しており、倫理的に問題があるなどの場合、社員が関わったとして会社の信用が損なわれる可能性があります。
例えば、副業の案件が詐欺行為に関っていた場合、就業先の会社の信用も傷ついてしまいます。案件は慎重に選びましょう。
また副業の営業活動のために自分のSNSを活用することもあるかもしれませんが、SNSで炎上するなどした場合も会社に影響する可能性があります。こちらにも十分に注意が必要です。
CHECK
就業規則で副業禁止とされている場合、副業はひかえること
副業が認められていても、会社の不利益につながることは懲戒処分対象になります
情報漏洩や会社の信頼低下を起こさないように注意しましょう
副業をすることの会社への切り出し方・報告のポイント
副業を報告する際は具体的な業務内容や副業をしたい背景と目指しているキャリアプランを明確に伝え、周りを味方に引き込むことがポイントです。
副業を会社に報告することでトラブルを防げるだけではなく、自分がどういうことに興味があり、どんなことをやりたいと思っているのかを上司や同僚に伝えることによって、社内でもやりたい仕事が回ってくるチャンスが増えることもあります。
まずは本業を通じて職場での信頼を得よう
「仕事できちんと成果を出していないのに副業をするなんて」「副業を始めさせたら、本業がおろそかになるのではないか」と、不当な評価を受けてしまうのは一番避けたいことです。
副業をスムーズに始めるためには、まず現在自分が受け持っている業務をきちんとこなし、仕事における信頼関係をつくっておくことが大切です。
副業に集中しすぎて本業がぼろぼろになることがないように、まずは本業でやるべきことをきっちりこなしましょう。
上司や周囲の同僚に応援をしてもらえるようにしよう
社内での信頼関係が構築できたら、タイミングを見計らって副業を始める旨を周りに伝えます。
目指すキャリアプランや、どんな想い・計画でどんな内容・頻度の業務を副業として行う予定なのか、上司に報告すると良いでしょう。
スケジュール感や、予想される影響範囲などもあらかじめ共有しておくと良いです。副業が現在の職務や会社の利益に影響を与えないことと納得できる理由も説明し、誠実に報告することで会社との関係を損なうことなく副業を始めます。
人事や管理部に報告をして会社から副業許可をもらう
周囲の理解が得られたら、上司の後押しとともに会社へ申請・報告を行い、副業許可をもらいます。その際以下の内容を伝えましょう。
- 副業の目的:新しいスキルの取得のため、子供の学費のためなど、具体的に伝えます。その際、就業先にもメリットになることがある旨も伝えると良いでしょう。
- 業務内容:具体的な業務内容のほかに、競合する企業でのプロジェクトではないか、顧客との関係性や機密情報の取り扱いなど利益相反の観点も問題がないことを伝えます。
- 作業時間:副業と本業のバランスをもって両立できる時間配分がスケジュールできており、本業に支障が出ない働き方であることを伝えます。
CHECK
まず同僚や上司の信頼を得ることから始めます
会社のフローに沿って副業報告を行います
副業の目的、業務内容、背景、想定されるリスクと対処法まで包み隠さず伝えます
副業をする旨を会社に伝えたほうが、周りからの理解も得られて良いですね!会社によって報告のしかたが決められているので就業規則を確認し、フローに沿って報告します。まずは報告するところからが副業のスタートです。
副業を行う際は目的を持って臨み必ず会社に報告
副業を始める際はゴール設定が大切です。ゆくゆくはフリーランスとして独立したいのか、キャリアアップのためなのか、目指すゴールによって副業の働き方も変わってきます。自分がなりたい状態を具体化し、副業をする目的を明確化したうえで副業をスタートできると良いでしょう。