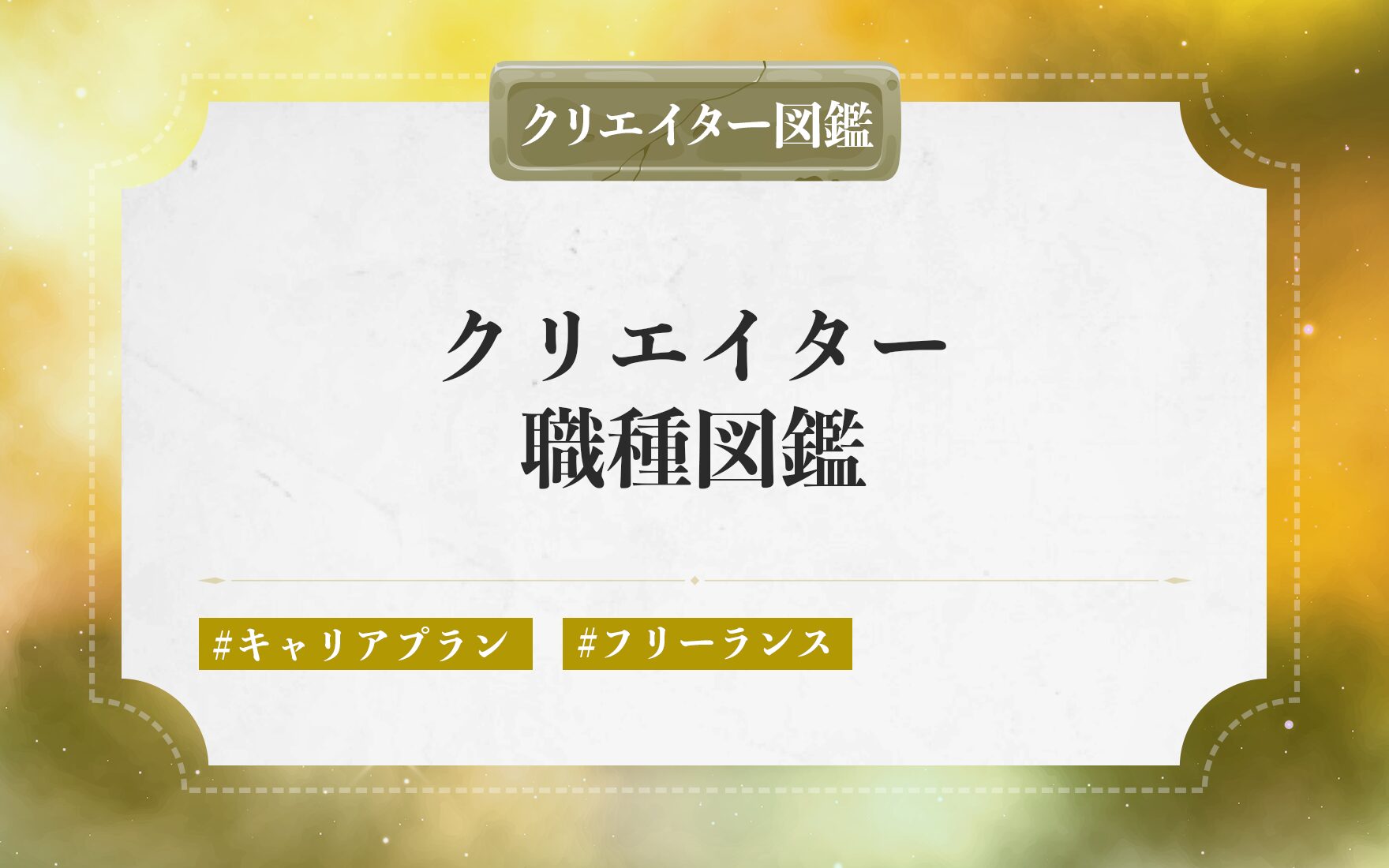クリエイター(Creator)を一言で紹介するなら、技術やスキルを使って新しい作品やコンテンツを生み出す人々のことです。クリエイターが生み出すものには、アニメやマンガ、ゲーム、映像、Web、XRなどがあります。最近ではVTuberも活躍していますね。
多種多様な媒体で活躍しているクリエイターたちは何か特殊なスキルをもっているのだろう、と思うかもしれませんが、そうではありません。持ち前のアイデアやセンスはすぐに使い果たしてしまいます。ではクリエイターたちは何が特別なのでしょう?
実は、憧れのクリエイターも弛まないスキルの習得と良質な経験を積み続けています。毎日の隙間をつかってインプットを増やし、スキルをひとつひとつ身につけて、アウトプット。チームのメンバーとフィードバックを繰り返すことで成果を高められます。
クリエイターは作り手だけではない
クリエイティブな仕事とはアイデアを形にする仕事
アニメやマンガなど日本を代表するコンテンツは世界でも高く評価されています。制作に携わったクリエイターたちのなかには、海外のプロダクションに移籍して働く人も多くあります。スキルさえあれば、国境を飛び越えて、産業の垣根も越えて活躍できるのがクリエイターです。
クリエイターと大きな括りにしていますが、わかりやすいアウトプットを出す職種ばかりではありません。クリエイターたちをまとめる監督、Webディレクター、アートディレクターなどもクリエイターです。企業であれば企画を考える「企画職」もクリエイターといえますね。
営業や人事の仕事の中にも、発想やアイデアを活かせるクリエイティブな仕事があるのではないでしょうか。
意外かもしれませんが、企画中の製品やコンテンツが陳腐化しないように市場をチェックしつづけるアナリストもクリエイティブな仕事のひとつです。
では「クリエイティブな仕事」とは何をさすのでしょう? 言葉の定義に忠実に「新しい価値や意味を生み出す仕事」とまとめると、逆に分からなくなってしまいます。
もう少しわかりやすく、「あっこれ面白い!」「少しだけ要素を足したら分かりやすくなる」、こんなアイデアを出し合ってまとめていく行為。と言い換えれば腑に落ちるでしょうか。
デザイナーはアイデアを視覚的なデザインに落とし込みます。エンジニアはデザイナーが仕事をしやすいように新しい補助プログラムを開発するかもしれません。ラインプロデューサーはクリエイターたちの負荷を減らすべく環境を整えて完成まで導きます。
プロジェクトに関わる全員がアイデアを出し合ってアウトプットを重ねることで、より良い成果を出せます。
クリエイティブな仕事は一人ではできない
映画やビデオゲームのエンドロールに、キャスト・スタッフの名前が並んでいるのを見たことがあるでしょうか。小さなタイトルであっても役割ごとにスタッフ名が記載されています。映像はたくさんの人によって作られる一大プロジェクトです。
そんな映画を夢に描いて、一人で「あっ、これ面白い」を形にしようとすると、途中やめになってしまいませんか?仕事では途中やめはありませんが、個人制作となると完成への道のりは平坦ではありません。モチベーション的にもクオリティ的にも、チームを組むほうが良い成果を出しやすいのは誰しも同じでしょう。
メンバー同士でアイデアを出し合い、アウトプットに対してフィードバックを出し合い、ブラッシュアップしたものは、満足のいく作品として生み出されるはずです。
チームメンバーそれぞれが異なった強みを持っていれば、苦手な工程はメンバー同士で補い合うことができる、というのもチームを組むメリットのひとつです。
プロジェクトで必要となる新しいスキルや知識をあらかじめ習得しておけば、チームメンバーに情報をシェアすることも可能になります。チームで実績を積み続ければ、憧れは現実になるかもしれません。
CHECK
・制作に関わる全員が「クリエイター」
・クリエイティブな仕事とは発想やアイデアを活かすこと
・チームを組むと良い成果を出しやすくなります
クリエイティブな仕事に必要なマインドやスキル
知識や専門性を高めるための知的好奇心
無限にあったと思っていた頭の中のアイデアも、アウトプットを続けるとすぐに枯渇してしまいます。一度は評価されたものでも、繰り返しアウトプットしていてはやがて飽きられてしまいます。クリエイターは常に新しいアイデアを探し求め、貪欲に自分のものにしていく知的好奇心が重要になります。
そして、アイデアを形にするためのテクノロジーやツールを使いこなすスキルも必要とされます。テクノロジーやツールは常に進化していますから、クリエイターは好奇心のままに新しいスキルを習得する向上心も必要になります。スキルが高まれば専門性が生まれますから、チーム内で重宝されます。
好奇心と向上心はすべてのクリエイターに共通する基本的なスキルです。
常に新しい物事に興味を持つためには、心・時間・資産に余裕があることが大切です。せわしない毎日のなかで余裕を持つことは簡単ではありませんが、落ち着ける場所、落ち着ける時間を工夫してつくり、好奇心を育ててあげましょう。
1冊の本、オンラインのレッスン、SNS。知識を得る便利な方法はたくさんあります。自分に合った媒体を選び、向上心を持って、世の中のニーズやトレンドを押さえましょう。現在の自分のスキルに満足せず、常に新しい情報を取り入れて自己を高めていけるクリエイターは、長期的に活躍できます。
チームで円滑に仕事をするためのコミュニケーション
クリエイティブな活動をしていくなら、コミュニケーションはとても大切なスキルのひとつです。クリエイターが仕事をする上でコミュニケーションをとる相手は、大きく三つあります。
- 見る人
- クライアント
- チームメンバー
クリエイターという仕事そのものが、見る人に言葉やデザインを届ける、というコミュニケーションです。
そして、どれほど高いスキルを持っていてもクライアント仕事である以上はクライアントの望むものを提供できなければ、次の仕事につながりません。チームで働いている場合は、チームメンバーと円滑なコミュニケーションを構築することが重要になります。
自分の発想の意図や要求を言語化して明確に伝える必要がありますし、クライアントやメンバーからフィードバックを受けることも成果物のクオリティを上げるときに役立ちます。どちらもコミュニケーションの形態の一つです。
「コミュニケーション」に対して苦手意識を持っている人もいるかもしれませんが、「仕事上でのコミュニケーション」は慣れと訓練で克服できるものです。
クライアントやチームメンバーと会話する際には、相手の要望を正確に汲み取ること、共感すること、自分のクリエイティブを丁寧に言語化して伝えることを意識しましょう。
コミュニケーションが活発化してくるとアイデアが湧き上がり、プロジェクトの成果が高まりやすくなります。やがては自身のキャリアにもつながるでしょう。
本質的な問題をとらえる観察力と解決のための論理思考
クリエイターはクライアントの課題を明確に把握した上で、クリエイティビティをもって解決策となる企画を提案し、成果物として提供することが求められます。
成否の決め手は、クライアントもユーザーも満足いくように本質的な問題を解決すること。
「クライアントの相手は大変そうだから、企画はプロデューサーやディレクター任せ、自分は自分のクリエイティブを爆発させて制作に取り組む」という姿勢のクリエイターがいるなら、クリエイターとして一人前とはいえません。
新しい仕事を前にしてテンションが上がる、そんな自分にブレーキをかけましょう。そしてクライアントが求めているもの、ディレクターが示した方向性、チーム内で自分に求められているものを正確に把握しなおしましょう。アイデア出しでは、自分がクールだと思うアイデアに対して根拠をとことん考え抜いてみる。求められているものとアイデアの間に違和感があれば言語化してみる。
メンバーに相談してフィードバックをもらう。こうした言語化や振り返りの一つ一つが自らの観察力を高め、論理的な思考に導いてくれます。
論理思考とクリエイティブの関係は車の両輪と同じです。どちらが欠けても走りませんが、うまくハマれば憧れの目的地まで運んでくれるでしょう。
CHECK
・知的好奇心はクリエイターの必須スキル
・チームメンバーとは円滑なコミュニケーションを構築しましょう
・本質的な問題を論理的に考えることが、成長につながります
クリエイティブな仕事に必要な専門的経験を積むには
センスよりも経験の量と質
たとえばロゴを30種考えて欲しいと依頼を受けたとします。AIを使えば一瞬ですが、自分のスキルは養われませんし、もっと上手にプロンプトを書けるクリエイターがいれば仕事を一瞬で持っていかれます。
スキルを養うために頭の中のアイデアを元にして考えていくと、アイデアはすぐに枯渇する、というのが現実です。
インプットを増やしましょう。好きなゲームやアニメや映画を見ることから始めましょう。「いいな」と思ったシーンがあれば、そこで止めて「なぜいいと思ったのか」を深掘りします。商業作品はよくできていて、随所に工夫が凝らされています。その工夫を自分の中に知識として蓄え、いざという時に出し入れできるようになっておきましょう。好きなタイトルの知識であれば、いくらでも蓄えられるのではないでしょうか。
見知らぬ土地で新しい遊びを体験するのもよいでしょう。美術館に行って古今東西の傑作に触れることももちろんおすすめです。インプットした情報は言語化して誰かとの会話のネタに出してみましょう。
スケッチのような形でアウトプットしておくことでも、記憶に定着します。遠回りに見えるかもしれませんが、クリエイティブな仕事は膨大で良質なインプットから生まれます。
経験を積むための会社員という選択
クリエイティブな活動を続けるなら働き方も重要です。キャリアの方向性が変わる可能性があるためです。
まずクリエイターとしてのキャリアをスタートさせたいなら、広告会社や制作プロダクションに就職するとよいでしょう。
学生や未経験者、クリエイターとしての実績が少ない人でも、企業に就職してプロジェクトに参加できればスキルアップできますし、最新のテクノロジーやスキルの知識を身に付けられます。数年も働けばクリエイターとしての実績も十分残せるでしょう。
会社員の魅力はほかにもあります。プロジェクトを通して仲間との高揚感や一体感を味わったなら、「仲間」が働く意味になるかもしれません。それに先進的なプロジェクトに関われることも、会社員のメリットでしょう。
フリーランスの世界は意外と狭い範囲に限られており、よほどの実績がある人を除けば、大きなプロジェクトに中心的なクリエイターとして関わることは非常に難しいです。
会社であれば制作を全て引き受けますから、例えば、万博やオリンピックなど記憶に残る仕事に携われるかもしれません。大きな案件を通じた経験を重視するのであれば、会社員という選択はとても現実的です。
スキルを高めるための独立という選択
会社員として同じ会社、同じチームに居続けると、必要以上にはスキルを身につけなくなる、ということがありえます。
その点、会社から独立し、さまざまなクライアントの難しいプロジェクトにコミットするフリーランスは、新しい知識やスキルを求められますから、知らず知らずのうちに成長していくことになります。スキルを高めるために会社を独立する、というキャリアは十分にアリでしょう。
ただし、フリーランスのクリエイターにはいくつかのメリットとデメリットがあります。
メリットは、時間や場所を選ばず、自宅やコワーキングスペースなどで自分のペースで働けることでしょう。各地を旅しながら仕事をするワーケーションという働き方も選べます。仕事を選べるというメリットもあります。
ストレスを感じる仕事は避けられますし、出産や育児の間は仕事をセーブすることができます。会社員が育休を取る際に感じるやましさなどを、フリーランスは感じる必要がありません。また、スキル・実績次第では、会社員より高収入を得られる可能性もあります。
デメリットのほうは、仕事量を減らすと収入が減るということです。進化していくテクノロジーと価値観に合わせて、新しいスキルを身につけ、考え方を刷新していくことが常に必要になります。孤独に耐えられない、営業が向いていないと、会社員に戻っていく人もいます。
自分の適正がどちらにあるのか、ゆっくりと考えてみるとよいでしょう。
CHECK
・クリエイティブな仕事はインプットの量と質から生まれます
・会社員は挑戦的なプロジェクトに携われます
・常に最前線で戦うフリーランスという働き方
企画・マネジメントの代表的な職種と年収相場
クリエイティブ系プロジェクトの上流に位置する企画・マネジメント職の仕事内容と年収相場をまとめました。なかには新卒・未経験から応募・転職可能な職種もあります。
Webプロデューサー
WebプロデューサーはWebサイト制作全般を統括するのが仕事です。IT系のクリエイターの中では最も稼げる職業といわれており、平均年収は約557万円ですが、経験と能力次第では1000万円を超えることもあります。
Webプランナー
WebプランナーはWebサイト制作において、クライアントの希望を具体的な企画に落とし込みます。時には、取材やライティング、原稿チェックを担当することも。平均年収は450万円で、経験と実績に応じて収入が上がる傾向にあります。
Webディレクター
Webサイトに掲載する記事やページの企画・編集や制作のディレクションを行い、クライアントの期待に応えるのがWebディレクターです。平均年収は443万円。年収の差はスキルレベルに大きく依存しています。
デザインの代表的な職種と年収相場
デザイン系の代表的な職種の仕事内容と年収相場をまとめています。デザイナー職は一度手に職をつければ、テレワークやフリーランスなど働き方を選びやすい仕事といえます。
クリエイティブディレクター
クリエイティブディレクターは、広告制作やブランド制作などプロジェクト全体の進行と管理の責任を担っており、多彩なクリエイターをまとめることが主な仕事です。平均年収は500万円ほど。実績に応じて1,000万円を超えることもあります。
アートディレクター
アートディレクターは、広告やグラフィックデザイン、映像、空間デザインなどにおいて、美術分野の総合演出を指揮する役割にあります。年収の平均は約524万円で、認知度や評価が高まると収入も増える傾向にあります。
UIデザイナー
UI(User Interface)とはユーザーと製品やサービスをつなぐ接点のことで、UIデザイナーは見た目のデザインの魅力だけでなく、使いやすいデザインを実現することが仕事です。UIデザイナーの平均年収は約598万円と高い傾向にあります。
UXデザイナー
UX(User Experience)とはユーザーが製品やサービスに触れたときに得られる体験を指します。UXデザイナーはユーザーに「楽しい、心地良い」と感じさせる体験をデザインすることです。 年収は611万円ほどとなっています。
動画クリエイター
動画クリエイターは、テレビ、映画、Webなどのメディアに向けて動画コンテンツを制作しており、制作のプロセスごとにさまざまな役割があります。初心者でも年収300万円から400万円、スキルによって500万円以上の高収入を目指せます。
エフェクトデザイナー
エフェクトデザイナーは、主にゲーム開発において、光、炎、雷、煙、魔法陣、回復シーンなど、さまざまな視覚効果を制作します。年収は企業によって異なりますが約472万円程度で、スキルや経験によって大きく変動します。
モーションデザイナー
モーションデザイナーは、CG作品においてキャラクターに生き生きとした動きをつけていく専門職で、手付けで動きをつける場合と、モーションキャプチャーデータを使用する場合があります。年収は平均で約473万円と言われています。
3Dモデラー
3Dモデラーは、キャラクター、景色、乗り物など、あらゆるオブジェクトを3DCGで表現します。ゲームやアニメだけでなく建設業や製造業など多岐にわたる産業で活躍しています。年収は300万〜500万円ほど。個人制作でも活躍の場所を増やすことができます。
CGデザイナー
CGデザイナーには、モデラー、アニメーター、エフェクトアーティスト、コンポジターなどの仕事があります。CGデザイナーの平均年収は300万〜500万円ほどで、そのスキルは国際的にも通用するため、海外での就業機会も多く存在します。
Webデザイナー
Webデザイナーは、クライアントの要望に基づいてWebサイトをデザインするのが仕事です。レイアウトを組むだけでなく、HTML、CSS、JavaScriptなどを使用してコーディングも行います。平均年収はおよそ386万円で、実績や経験に応じて収入が増える傾向にあります。
アニメーター
アニメーターはアニメーション制作においてキャラクターに動きを与える専門職です。アニメーターの創造性はダイレクトに作品のクオリティに影響します。動画、原画、作画監督とスキルを高めることで収入を増やすことが可能で、作画監督の平均年収は538万円となっています。
イラストレーター
イラストレーターは雑誌や書籍、パンフレットやポスター、商品パッケージなどさまざまな媒体でイラストを制作しています。平均年収は約362万円。フリーランスの場合は仕事量によって収入が大きく変動し、スキルや実績が上がると高収入が期待できます。
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナーはクライアントのニーズを踏まえて、広告やブランディング、プロダクトのデザインを手がけています。広範囲にわたるデザインスキルが求められるだけに、平均年収は約478万円と、高い水準にあります。
エディトリアルデザイナー
エディトリアルデザイナーは、雑誌やカタログなど印刷物やデジタルメディアの編集とデザインを担当するデザイナーです。アシスタントからスタートすることが多いエディトリアルデザイナー、平均年収は300万〜400万円がボリュームゾーンになります。
フォトグラファー
フォトグラファーは写真撮影を専門としており、広告やメディア業界のほか、個人向けサービスやアート系など、多岐にわたるジャンルで活動しています。平均年収は一般的に300万〜400万円の範囲にあり、高い技術を持つフォトグラファーは高額な収入を得ることも可能です。
文章・コンテンツ制作の代表的な職種と年収相場
文章・コンテンツ制作系の代表的な職種の仕事内容と年収相場をまとめています。すぐれた言語感覚や、読者の心に届く言葉を選ぶ能力が必要とされますが、未経験者でも参入の可能性が高いのが執筆業です。キャリアプランを計画する際の情報収集にお役立てください。
コピーライター
コピーライターは、ブランドのイメージにフィットした広告文を創造しています。広告コピーは企業の広告戦略の核にもなることから、広告制作の重要な役割を担っているといえます。年収は350万円からスタートし、シニアレベルでは1000万円を超えることもあります。
シナリオライター
シナリオライターは映画やドラマ、アニメ、ゲーム、YouTubeなどさまざまなプラットフォームに向けてストーリーを構築しています。新人シナリオライターの平均年収は約300万円、キャリアを積めば年収800万円以上、という人も珍しくありません。
エディター
エディター(編集者)は、書籍や記事の制作に携わる仕事で、企画の立案だけでなく、取材や校正を行うこともあります。そして編集者やクライアントが執筆を依頼する相手がライターになります。ライター・エディターの平均年収は約382万円で、経験や能力によって変化します。
エンジニアリングの代表的な職種と年収相場
ITエンジニア系の代表的な職種の仕事内容と年収相場をまとめています。エンジニアの活躍の場は幅広く、それぞれ担う役割が異なります。
システムエンジニア
システムエンジニア(SE)の仕事は、クライアントのニーズに応じてITシステムやソフトウェアの設計や開発、運用、保守を行うことです。アプリケーション開発系のSEで平均年収は550万円ほど、要件定義や基本設計といった上流工程の経験を積むと年収が上がる傾向にあります。
プログラマー
プログラマーはプログラム言語をつかい、SEが作成した詳細設計に合わせてプログラミングを行うのが仕事です。プログラマーの年収は433万円ですが、使えるプログラミング言語や取得している資格によって年収は大きく変わっていきます。
フロントエンドエンジニア
フロントエンドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーション開発において、ユーザーが直接見る部分や操作できる部分の設計・開発を担うITエンジニアです。平均年収は550万。経験年数が長くなるほど平均年収が高くなっていきます。
HTMLコーダー
HTMLコーダーの仕事は、指定されたデザインの通りになるよう、HTMLやCSSなどを使ってWebページをコーディングすることです。HTMLやCSSは比較的簡単に学べるので、未経験からHTMLコーダーになる人も。平均年収は約410万円といわれています
マーケティングの代表的な職種と年収相場
マーケティング系の代表的な職種の仕事内容と年収相場をまとめています。それぞれの役割ごとに求められるスキルが異なるため、マーケターを目指す方は、それぞれの特徴を正しく理解しておくことが大切です。
上流・戦略設計マーケター
上流・戦略設計マーケターの仕事は、市場やクライアントの分析を行い、商品(サービス)を提供するために適切なマーケティング戦略を練ることといえます。平均年収は約484万円ですが、経験や求められるスキルによって大きく異なります。
広告マーケター
広告マーケターは、ターゲットユーザーのニーズをリサーチし、その結果をもとに自社商品(サービス)を売り出すのに適したメディアを選び、商品(サービス)の広告を出すことを仕事にしています。平均年収は400万円~500万円となっています。
PR・広報マーケター
PR・広報マーケターは、自社サービスの売上を上げることを目的に、自社サービスの情報発信やメディア対応などを行っています。広報戦略とデジタルマーケティングの融合が求められて生まれた新しい職種であり、平均年収は484.5万円ほどといわれています。
コンテンツマーケター
コンテンツマーケターはユーザーが必要としているコンテンツについてリサーチを行い、それに基づいてブログやオウンドメディアなどのコンテンツを企画します。企画によっては制作や運用を担当することもあり、平均年収は400~500万円ほどになります。
SNSマーケター
SNSマーケターはInstagramやTikTok、YouTube 、X(Twitter)といったSNSを活用したマーケティングを担当しています。注目を浴びているSNSマーケターですが、そもそもの顧客単価が低いため、年収相場は300~400万円が中心となっています。
SEOマーケター
SEOマーケターは、検索エンジンにおける検索者のニーズを理解したうえで、彼らが求める価値ある情報を提供し、検索者のアクセス数を増やすことを目的とする仕事です。平均年収は約438万円〜625万円で、フリーランスであれば1,000万円も目指せます。
ATTENTION
どの仕事も経験やスキル、資格の取得によって年収相場は高まっていきます。フリーランスであれば年収1000万円も夢ではありません。自身の適正にあった職種を見定め、経験を詰み、スキルを高め、キャリアを拓いていきましょう。