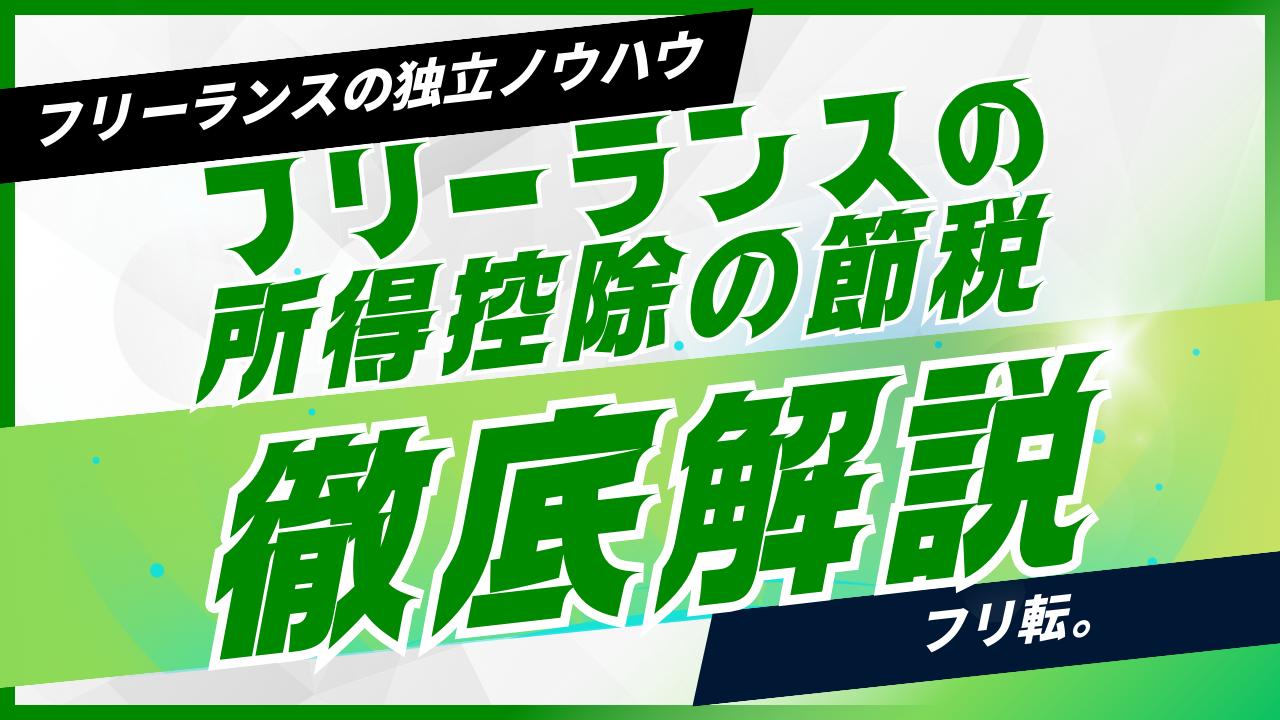フリーランスは支払うべき税金が多く、自身で計算をしなければならないため大変です。税金を低く抑えるためには、それぞれの税金の算出方法と節税方法を知っておきましょう。

フリーランスにとって、納税と節税は非常に重要です。資金繰りを適切に管理し、納税額を減らすための対策がフリーランスの成功を大きく左右します。
フリーランスが支払う税金は5種類
フリーランスが支払う主な税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」「固定資産税」の5つで、税額は収入によって異なります。税金を払うためには所得額を計算し確定申告を行うことが必要です。
所得税・復興特別所得税の計算・節税方法
所得税とは1年間の所得に対して支払う税金で、復興特別所得税とは所得税額に対する付加税で所得税に対して2.1%上乗せで計算されます。
計算方法:所得税 = 課税所得×税率−控除額
※課税所得 = 総収入−必要経費−基礎控除−その他の控除
復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
累進課税の所得税・復興特別所得税の算出方法と計算例
所得税の累進課税とは、所得が多くなるほど税率も高くなる仕組みのことです。所得税・復興特別所得税ともに累進課税で計算されます。
| 課税所得 | 所得税率 |
| 0~195万円 | 5% |
| 196~330万円 | 10% |
| 331~695万円 | 20% |
| 696~900万円 | 23% |
| 901~1800万円 | 33% |
例えば課税所得が500万円の場合、以下の計算となります。
500万円 × 20%(所得税率) – 427,500円(控除額) = 572,500円
所得税・復興特別所得税の支払いのタイミングは天引き&確定申告
フリーランスは前年の1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をしますが、所得税・復興特別所得税も原則として同じタイミングの3月15日が納付期限となっています。
所得税・復興特別所得税は控除活用と経費計上で節税
所得税・復興特別所得税は、控除の活用と経費の計上によって節税することができます。
所得税率が課される「課税所得額」を低くする方法と、所得税額から直接減らせる「税額控除」を利用する方法があるので上手く活用しましょう。
住民税の計算・節税方法
住民税は、所得税の確定申告書をもとに計算され、「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。
住民税の所得割・均等割の算出方法と計算例
計算方法:住民税 = 所得割 (一律10%)+ 均等割(世帯割)
例えば所得が500万円の場合、所得割は500万円 × 10% =50万円、均等割は5,000円となり、住民税は合計の505,000円です。
住民税の支払いのタイミングは6月末・8月末・10月末・翌1月末の年4回
フリーランスや自営業者の場合、住民税は普通徴収となり、年4回払いで市区町村から納税通知書が送られてきます。
住民税はiDeCo・医療費控除の活用や親の扶養化で節税
住民税の節税には、iDeCo(個人型確定拠出年金)や医療費控除、家族の扶養を活用する方法があります。
個人事業税の計算・節税方法
個人事業税とは、特定の事業を営む個人事業主やフリーランスが事務所のある自治体に納付する地方税のことを指します。個人事業税は経費への計上が可能です。
業種によって税率が変わる個人事業税の算出方法と計算例
個人事業税は業種によって納めるべき税率が異なります。また、1年間を通して事業をおこなっている場合290万円の控除が適用されます。
| 第一種事業 | 第二種事業 | 第三種事業 |
| 税率5% | 税率4% | 税率5% |
| 飲食店、旅館、運送業など | 畜産業、水産業など | デザイン業、コンサルタント、士業など |
計算方法:納税額 = (前年の事業所得金額 – 各種控除額)× 業種に応じた税率
例えば所得が500万円・必要経費が100万円の場合、所得から経費・控除額を差し引いた課税所得は500万円-100万円-290万円=110万円となり、その5%=5.5万円が個人事業税になります。
個人事業税の支払いのタイミングは8月と11月の年2回
都道府県により詳しい日程は異なりますが、8月と11月の2回に分けて、前年分の確定申告をもとに計算された納税通知書が届きます。
個人事業税は減価償却費の特例や損失の控除の活用で節税
所得が290万円以下なら個人事業税は非課税になるので、所得額を下げることで節税につながります。減価償却費の特例や損失の控除が適用できるか確認してみましょう。
消費税の計算・節税方法
年間の所得が1,000万円を超えるフリーランスは、課税事業者となって消費税を納める必要があります。
課税事業者になるには、管轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。
課税事業者に一律掛かる消費税の算出方法と計算例
計算方法:納税額 = 課税売上高の消費税 – 課税仕入高の消費税
例えば、税込の売上が1,000万円、経費が330万円の場合、売上高の消費税は1,000万円×0.1=100万円、経費(売上高)の消費税は300万円x×0.1=30万円となり、納付消費税は100万円-30万円=70万円となります。
消費税は消費毎&決算の2ヶ月以内に支払い
消費税は取引ごとに清算し、決算後2ヶ月以内にまとめて納めます。
消費税の免税事業者は2年間は原則納付義務がない
フリーランスの場合、年間の課税売上高が1,000万円未満、もしくは開業してから2年以内であれば、消費税の免税事業者となり消費税を納付する必要はありません。
固定資産税の計算・節税方法
フリーランスが事業に使っている資産には、固定資産税がかかる場合があります。この場合の固定資産は土地や建物だけでなく、事業用の設備や備品(償却資産)も対象となります。
償却資産を持っている場合に掛かる固定資産税の算出方法と計算例
償却資産とは事業に使用する資産のことで、パソコンや業務関連の機器・ソフトウェアで取得価額が10万円以上のものを指します。
償却資産を購入した際は固定資産税を納税する義務が発生します。固定資産税の標準税率は1.4%です。
計算方法:納税額 = 固定資産税評価額×標準税率1.4%
固定資産税の納期は年4回で自治体毎に異なる
原則年4回に分けて納付書が届くので、届いたタイミングで支払いを行います。第1期分の納付書は毎年4月〜6月頃に届きますが、スケジュールは自治体により異なります。
償却資産の合計額が150万円未満であれば償却資産税はかからない
償却資産の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、資産の多少に関わらず申告が必要となります。
CHECK
・支払う税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」「固定資産税」の5つ
・税額は確定申告の内容に基づいて計算される
・支払いのタイミングはそれぞれ異なるのでスケジュールを押さえておく
社会保険も実質的な税金の一部
フリーランスが支払う社会保険料(国民健康保険や国民年金)は、実質的に税金の一部といえます。
フリーランスの場合、社会保険料も自分で納付しなければならないため、税金と同じように計画的な支払いが求められます。
社会保険料の計算方法
フリーランスが支払う社会保険は「国民健康保険」と「国民年金」の2つです。どちらも全額所得控除の対象で、年収が少ない場合は軽減措置もあります。
国民健康保険の計算方法:所得割+均等割+平等割
※所得割 = (前年所得 – 43万円) × 所得割率
※均等割 = 均等割額 × 加入者数
※平等割 = 定額/自治体により異なる
国民年金:全国一律で2025年度は月額16,980円(年額203,760円)
社会保険と所得税を加味したフリーランスの年収別手取り一覧
フリーランスの手取り額は、年収に応じて所得税や社会保険料(国民健康保険、国民年金)などが差し引かれます。
以下に、年収別の手取り一覧をまとめていますが、税金や保険料の額は地域や個人の状況により異なるため目安としてご確認ください。
| 年収(税引前) | 所得税 | 社会保険料 | 手取り額 |
| 300万円 | 約15万円 | 約40万円 | 約245万円 |
| 400万円 | 約30万円 | 約50万円 | 約320万円 |
| 500万円 | 約45万円 | 約60万円 | 約395万円 |
| 600万円 | 約60万円 | 約70万円 | 約470万円 |
| 800万円 | 約100万円 | 約90万円 | 約610万円 |
CHECK
・社会保険も実質的な税金の一部
・フリーランスの社会保険料は全額所得控除の対象
・フリーランスの手取り額は、年収に応じて異なる
フリーランスにできる手残りを増やすための節税対策
フリーランスにとって節税対策は、手残りを増やすために非常に重要です。
青色申告特別控除や必要経費の計上、各種所得控除を活用することで適切な節税になり、実際に手にする金額を大幅に増やすことができます。
青色申告特別控除を必ず受ける
青色申告を選択することで、一定の条件を満たせば最大65万円の控除を受けることができ、税負担を大きく軽減できます。
青色申告特別控除を受けるには、確定申告時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
この申請書は、初めて青色申告を行う年の3月15日までに提出しなければならないのでタイミングを逃さないようにしましょう。
各種所得控除を漏れなく申告する
所得控除を適用することで、課税対象となる所得が減少し、結果的に支払う税金を軽減することができます。
主な所得控除には基礎控除、社会保険控除、医療費控除、住宅ローン控除などがあります。
確定申告で必要経費を確実に計上する
確定申告で必要経費を確実に計上することは、フリーランスにとって非常に重要な節税対策です。
経費を適切に計上することで、課税所得が減少し支払う税金を軽減できるので、領収書と証拠書類を必ず保管し、事業に関連する経費は漏れなく計上しましょう。
売上高・利益によってはマイクロ法人化を検討する
個人事業主から法人に切り替えることで得られる税制面でのメリットを受けるため、法人化の検討も手段のひとつです。
マイクロ法人とは経営者1人がすべての事業を行っており、従業員を雇っていない法人のことを指します。
扶養・専業従事者に事業支援してもらい給与を払う
個人事業主が家族に給与を支払う場合、青色事業専従者給与を活用することができます。
個人事業主が家族に対して行う給与支払いが適切であれば、経費として計上できる制度で、節税につながります。
小規模企業共済の加入を検討する
小規模企業共済は、個人事業主が将来の退職金や年金資金を積み立てるための制度であり、節税対策にも有効な手段です。
収入の一部を共済に積み立てると積立額を全額経費として計上できるため、税金の負担を軽減することができます。
フリーランスが高すぎる税金を払えないときの対策
フリーランスが税金を払えない場合は、まず税務署や税理士に相談しましょう。
納税納期の変更や分割措置の検討が可能です。放置すると延滞税が増え、差し押さえの可能性もありますので早めに相談しましょう。
督促が始まる前に税務署や自治体に分割払いが可能かを相談する
税金を支払わずに放置すると税務署や自治体から「督促状」が届き、これを無視すると延滞税が加算され、最終的には財産の差し押さえなどをされる可能性があります。
督促される前に分割払いや猶予を相談することが重要です。
所轄の税務署に猶予を設けてもらえるかを相談する
督促前に税務署に相談をすることで、納税の猶予を申請できる制度があります。
必要に応じて、申請書類や収支状況の資料を提出し、支払い計画を立てることで猶予が認められる可能性があります。相談は早いほど有利なので早めの行動が大切です。
ファクタリングやローンの利用を検討する
フリーランスが税金を払えない場合、ファクタリングや事業者向けローンの利用も検討できます。
ファクタリングは売掛金を早期に現金化できる方法で、即日の現金化もできますが、手数料がかかりますので慎重に検討しましょう。
どうにもならない場合は自己破産を検討する
フリーランスが税金を払えない場合、最終手段として自己破産を考えることもあります。
ただし、フリーランスが自己破産した場合、借金は免除されますが税金は免除されません。自己破産を考える前に他に出来ることがないか専門家に相談することをおすすめします。
税金は自己破産でも免除されないためCF表で計画的な資金繰り
税金は原則として自己破産しても免除されない非免責債務のため、自己破産しても税金の支払い義務は残ります。
自己破産になるまで行く前に、キャッシュフロー表(CF表)を使った計画的な資金繰りや支払い計画を立てておくことが重要です。
CHECK
・手取り額を増やす節税手法はさまざま
・税金が払えない時は早めに税務署や税理士に相談する
・キャッシュフロー表で資金繰りの計画をきちんとたてておくこと
フリーランスにとって、税金の管理は大切な課題です。確定申告や節税対策をうまく活用することで、納税額を抑えることができます。また、万が一支払いが難しい場合でも、早めに相談し適切な対応を取ることが重要です。計画的に税金と向き合うことで、安定した事業成長をすることができます。