“壁”を超えるな、くぐり抜けろ!フリーランスの扶養テクニック
- Home
- フリーランスの資金術
- “壁”を超えるな、くぐり抜けろ!フリーランスの扶養テクニック
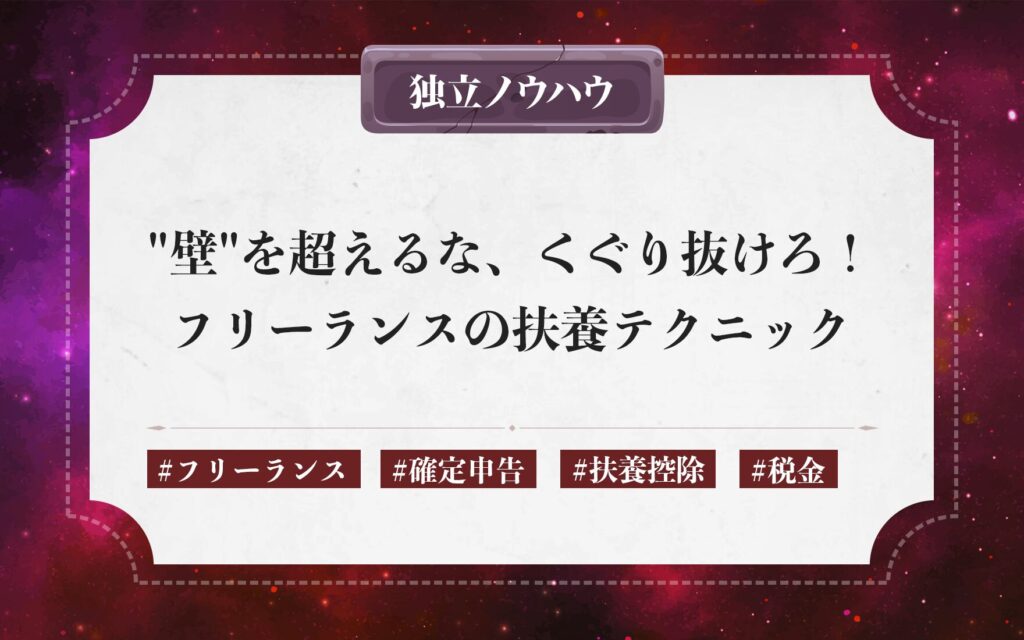
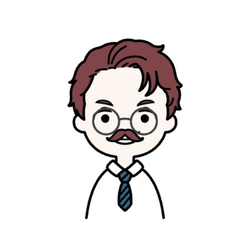
フリ転編集部 山脇
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
あなたはフリーランスとして活動しながら、配偶者の扶養に入りたいと考えていませんか?「いくらまで稼げるの?」「扶養に入るメリットは?」「確定申告はどうすればいい?」など、疑問は尽きないでしょう。この記事では、フリーランスが扶養内で働くための条件や注意点を徹底解説します。
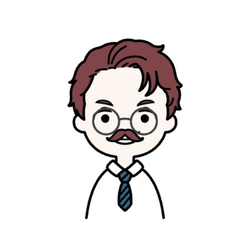
フリーランスの扶養内就業は所得管理がカギです。税法上は103万円、社会保険上は130万円が重要な壁となります。経費計上を工夫し、クライアントと仕事量を調整しましょう。ただし扶養はキャリアの一時期と捉え、将来的な経済的自立も視野に入れた働き方設計が重要です。
目次
フリーランスと扶養の基本的な関係
フリーランスも扶養に入れる?基本の「き」
結論から言うと、フリーランスでも一定の条件を満たせば扶養に入ることが可能です。ただし、会社員とは異なり、収入の管理や手続きに注意が必要です。フリーランスの場合、「収入」ではなく「所得」(収入から経費を引いた額)が扶養の判断基準となります。
税法上と社会保険上の「扶養」の違い
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。それぞれ条件が異なるため、混同しないように注意が必要です。
| 区分 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
| 判断基準 | 年間所得 | 年間収入 |
| 金額の壁 | 103万円(所得税)、100万円(住民税) | 130万円(厚生年金・健康保険) |
| メリット | 配偶者控除による税金軽減 | 健康保険・年金保険料の負担なし |
扶養内で働くとはどういうこと?
扶養内で働くとは、配偶者(多くの場合、会社員である夫や妻)の扶養家族として認められる範囲内で収入を得ることです。フリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた所得が一定額以下であれば、配偶者の扶養に入ることができます。
CHECK
・フリーランスでも条件を満たせば扶養に入れる
・税法と社会保険で扶養の条件が異なる
・所得が一定以下なら扶養内で働ける
フリーランスが扶養に入るメリットとデメリット
扶養に入るメリット:経済的負担の軽減
扶養に入ることで得られる主なメリットは以下の通りです。
- 社会保険料の負担なし:配偶者の健康保険や年金に加入できるため、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要がありません。
- 配偶者の税金軽減:配偶者控除により、扶養している配偶者の所得税・住民税が軽減されます。
- 確定申告の簡素化:所得が一定額以下であれば、確定申告が不要になるケースもあります。
扶養に入るデメリット:将来的なリスク
一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
- 年金受給額の減少:国民年金に自分で加入していないため、将来の年金受給額が少なくなる可能性があります。
- 収入制限による機会損失:扶養に入るために収入を抑えることで、本来得られたはずの収入機会を逃してしまうことがあります。
- キャリア形成の遅れ:収入を抑えるために仕事量を制限することで、スキルアップやキャリア形成が遅れる可能性があります。
扶養に入ることで得をするケース
以下のようなケースでは、扶養に入ることでメリットが大きくなります。
| ケース | 扶養のメリットが大きい理由 |
| 副業的にフリーランス活動をしている場合 | 本業の収入がある配偶者の扶養に入りつつ、負担の少ない範囲で活動できる |
| 子育てや介護で働ける時間が限られている場合 | 短時間労働でも社会保険料の支払いを回避でき、家計にゆとりが生まれる |
| 起業初期でスキルアップ中の段階 | 収入が少ない時期に扶養に入ることで、負担を抑えながら成長に集中できる |
| 配偶者の収入が安定している場合 | 家計全体としての手取りを最適化でき、将来的な資産形成にもつながる |
CHECK
・扶養に入れば保険料や税金の負担が減る
・収入制限が将来の年金や成長に影響する
・副業や子育て中などは扶養の利点が大きい
フリーランスの扶養内働き方と収入管理
各種「壁」を理解して収入を管理しよう
フリーランスが扶養に入るためには、いくつかの「壁」を意識する必要があります。それぞれの壁を超えると、どのような影響があるのかを理解しましょう。
| 区分 | 金額 | 超えた場合の影響 |
| 住民税の壁 | 100万円(所得) | 住民税の均等割が課税される |
| 所得税の壁 | 103万円(所得) | 配偶者控除が受けられなくなる |
| 社会保険の壁 | 106万円(収入)※1 | 配偶者の会社によっては社会保険から外れる可能性がある |
| 社会保険の壁 | 130万円(収入)※2 | 社会保険から確実に外れる |
| 配偶者特別控除の壁 | 150万円(所得) | 配偶者特別控除が段階的に減少・消失 |
※1 配偶者の勤務先が大企業(従業員101人以上)の場合
※2 配偶者の勤務先が中小企業(従業員100人以下)の場合
クライアントとの関係調整のポイント
扶養内で働くためには、クライアントとの関係調整も重要です。
- 扶養内で働きたい意向を伝える:新規案件の相談時に、扶養内で働きたい意向を率直に伝えましょう。
- 報酬の月額固定化を相談する:収入を安定させ、計画的に管理するために、月額固定の契約形態を提案してみましょう。
- 仕事量の調節を依頼する:年間の所得を見越して、繁忙期と閑散期のバランスを取れるよう相談してみましょう。
確定申告の必要性とその手続き
フリーランスであっても、年間の所得が一定額以下であれば確定申告が不要になるケースがあります。ただし、以下の場合は確定申告が必要です。
- 年間の所得が48万円を超える場合
- 複数の収入源がある場合
- 経費を計上して所得を計算する必要がある場合
- 青色申告をする場合
特に青色申告は最大65万円の控除が受けられるため、所得を抑えるのに効果的ですが、事前の届出や複式簿記による記帳などの条件があります。
| 申告方法 | 控除額 | 主な条件 |
| 青色申告(特別控除) | 65万円 | 複式簿記で記帳、e-Taxまたは電子帳簿保存 |
| 青色申告(基礎控除) | 55万円 | 複式簿記で記帳 |
| 白色申告 | 控除なし | 簡易な記帳でOK |
扶養から外れて独立すべき判断基準
「いつまで扶養内で働くべきか」という判断は、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
- 収入の安定性:安定した案件や顧客基盤ができてきたか
- スキルの成長:専門性が高まり、より高単価の仕事を受けられるようになったか
- ライフステージの変化:子育てや介護などの状況に変化があったか
- 将来設計:年金など将来の経済的安定を考慮した場合、独立したほうが良いか
所得が150万円を超えるようになると、扶養のメリットはほぼなくなります。このあたりが「卒業」の目安になるでしょう。
CHECK
・各種の「壁」を意識して収入を調整する
・扶養内で働くにはクライアントと相談が必要
・所得や状況に応じて扶養卒業の判断を行う
フリーランスが配偶者の扶養に入るには、税法上の103万円の壁と社会保険上の130万円の壁を意識した所得管理が必要です。経費の計上方法や仕事量の調整によって壁を上手に活用しつつ、短期的な節税・節約だけでなく、将来のキャリア形成や年金受給額なども考慮した総合的な判断が大切です。扶養内で働くことはキャリアの一時期と捉え、ライフステージやスキルの成長に合わせて、いずれは収入を増やして経済的自立を目指すことも視野に入れておきましょう。