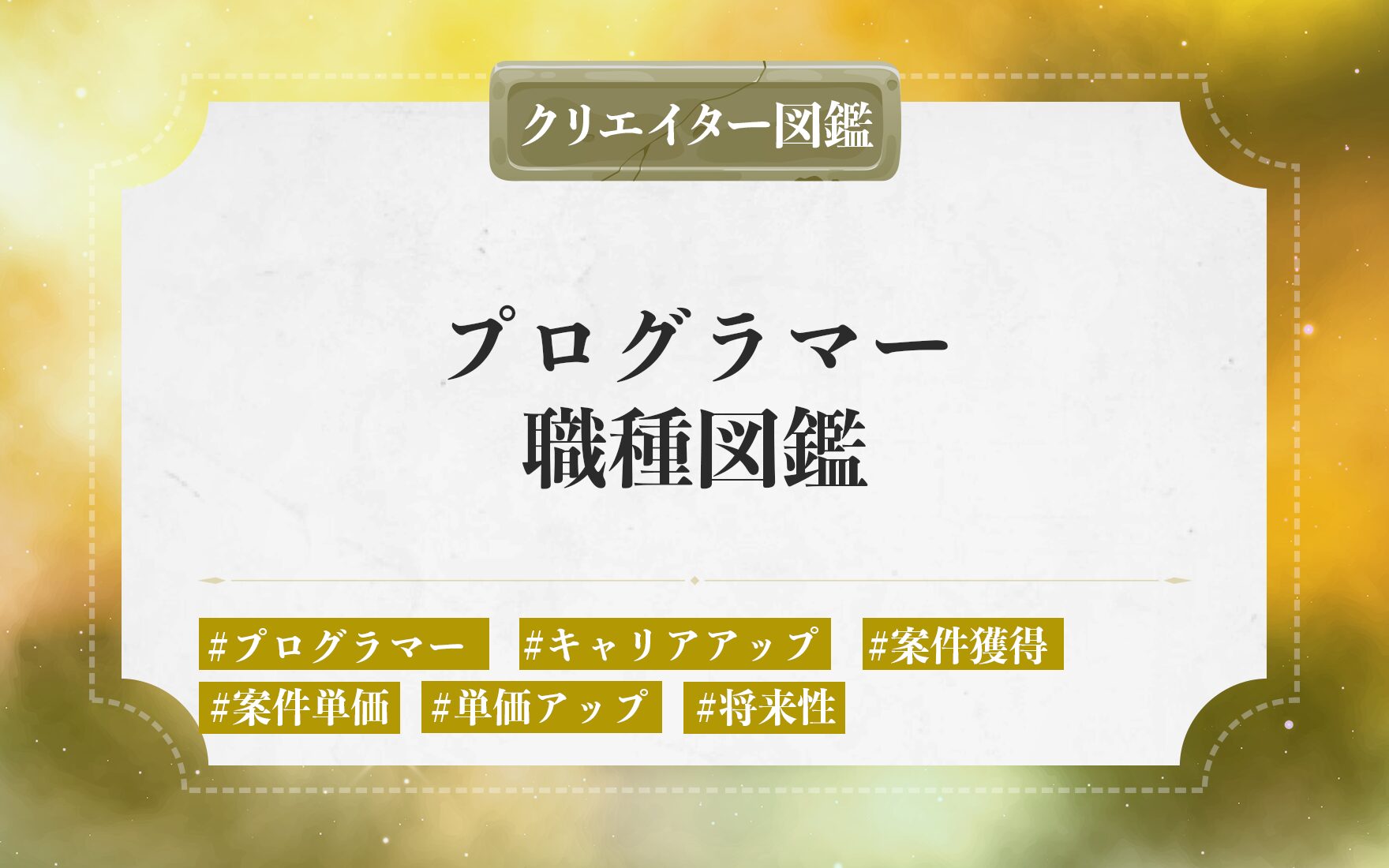※この記事はプロモーションを含みます。
これからフリーランスを目指す方の中には、「フリーランスに憧れるけど、どんな風に仕事を獲得できるのだろう」「周りに仲間がいないなかで、本当にやっていけるのかな?」と不安を抱えることもあるかと思います。会社員と違い、フリーランスは基本的には一人で活動することが多く、孤独を感じる方も一定数います。
だからこそ、コミュニティへの所属がおすすめです。たくさんの仲間に囲まれ、モチベーションアップやスキルアップの機会を持ちやすくなります。とはいえ、どんなコミュニティに入ればいいのかよくわからないという方も多いでしょう。そこで今回は、コミュニティの選び方や駆け出しの方にもおすすめのコミュニティをご紹介します。
駆け出しフリーランスにもオススメなコミュニティの選び方 フリーランスはどんなコミュニティに所属するとよいのでしょうか?フリーランスとして独立する方が増える今、コミュニティの数も増えています。そんな中、いくつものコミュニティを様々な観点からチェックしました。その結果わかった、駆け出しの方にもぴったりのコミュニティを詳しく解説します。
コミュニティ選びに悩んだら、まずはイベントに参加してみることがおすすめです。どんな人がいるのか、どんな雰囲気なのか、ネットで調べるだけよりもたくさんのことがわかります。職種や年齢だけでなく、どんなスキルセットを持った方がいるのか、将来についてどんなふうに考えている方が多いのかなどもつかめると、ミスマッチを防げます。イベントは、1つだけに参加するのではなく、複数に顔を出してみましょう。いくつかを比較することで、「自分にはここがあっていそう」とわかります。
どのような形態で運営されているかも重要なポイントです。オンラインだけで開催しているのか、オフラインでも交流があるのか、しっかり事前に確認してください。もちろん、活動内容のチェックも欠かせません。食事会などの交流会をしているのか、セミナーや勉強会なども開いているのかなど、コミュニティによって異なるので自分が求めているタイプのものを探しましょう。
最近では、自由な働き方を求めて独立を目指す方が増えています。フリーランスになると仕事をする時間や場所にとらわれず、たしかに自由度が上がります。その一方で、「具体的にどうやってフリーランスになったらいいの?」「案件はどうしたら獲得できる?」と不安に思う方も多いです。また、独立したものの「年収が半分になった」「孤独で寂しい」とフリーランスになったことを後悔する方も珍しくありません。
そんな失敗を避けるためには、コミュニティへの所属がおすすめです。同じくフリーランスを目指す仲間ができたり、フリーランスの先輩からアドバイスをもらったり、運営の方に独立をサポートしてもらえたりと、たくさんのメリットがあります。
とはいえ、「コミュニティの数が多すぎて、どこに所属したらいいかわからない」と悩んでしまいますよね。そこでフリ転編集部が、国内のあらゆるコミュニティを調査。その結果、「ここは駆け出しの方にもおすすめできる」と自信を持って紹介できるコミュニティを9つ厳選しました。これから独立を目指す方や、フリーランスになったばかりの方はぜひ参考にしてみてください。
フリ転は、2024年に運営が開始されたばかりのフリーランスコミュニティです。デザイナーやライター、エンジニア、マーケターなどを中心に、様々なクリエイターが集まっています。コンセプトは「クリエイターRPGギルド」。
他のコミュニティに比べて、ゆるいつながりを持てることが特徴です。入会の厳しい条件や、メンバーとして課されたタスクはなく、一人で仕事をする傍ら気軽にフリーランス同士のネットワークを持つことができます。
オンラインマガジンには、フリーランスとして働くうえで役立つ情報が盛りだくさん。オンライン、オフラインどちらもイベントを開催しているので、新しい人脈を作りたい方にもぴったりです。セミナーや勉強会では、仕事の進め方やクライアントとのコミュニケーションの取り方、確定申告についてなど、様々なジャンルの勉強ができます。入会方法も簡単で、LINEの友達登録をするだけです。
年会費 無料 コミュニティの機能 <実施中>オンラインマガジンポートフォリオ掲載交流イベント(オフライン・オンライン)セミナー・勉強会開催<準備中>分科会・イベント企画メンター紹介オンライン学習キャリア支援 運営会社 株式会社日本デザイン
今回ピックアップしたコミュニティの中でも、特におすすめできるのは以下の3つです。
フリーランス協会
フリーランス協会は、会員数10万人という国内最大レベルのコミュニティです。サポートの幅も広く、弁護士費用の保険など、これからフリーランスになる方も安心できる充実となっています。キャリアについて個別に相談できる仕組みもあるため、「これからどう案件を獲得していくか」「どのようにスキルアップしていくか」といったことも、プロに直接話せます。
Workship
Workshipは、フリーランスが案件を獲得するためのプラットフォームです。様々な案件が紹介されており、自分の気になるものがあればすぐに応募できます。そこから発展して、Workship LABというコミュニティが生まれました。交流会を通じてメンバーがつながりを持てたり、ウェブマガジンでフリーランスにとって有益な情報を得られたりと、多数のメリットがあります。
新しい働き方LAB
新しい働き方LABは、イベントやセミナーの機会が豊富なコミュニティです。コワーキングスペースの利用もできるので、「フリーランスになったけど、どこで仕事をしよう」「家ではなかなか集中できない」という方にもおすすめできます。また、自分のチャレンジしたいことに取り組める「実験プロジェクト」という仕組みもあるため、能動的に動きたい方にとってはぴったりのコミュニティでしょう。
フリーランスの独立にコミュニティは必要? フリーランスを目指している方は、「わざわざ独立するのに、コミュニティが必要?」「また会社にいるような気持になるのでは?」と懸念しているかもしれません。しかし、実際にフリーランスになった先輩の話を聞いてみると、様々な観点からコミュニティの必要性を感じられます。
横のつながりがフリーランスとしての成功の明暗を決める フリーランスの方には様々な悩みがありますが、中でも多いのが「案件が獲得できない」というものです。会社員であれば営業部の方が仕事を取ってきてくれるので制作に集中できたり、自分にスキルや実績がなくとも会社の名前で仕事を得られたりするものです。
しかし、フリーランスになると自分の実力だけで仕事を見つけなくてはなりません。また、案件がなければそのまま収入減になる点も会社員との大きな違いです。多少の蓄えを準備してから独立したとしても、日に日にお金が減っていく恐怖は耐え難いものです。
だからこそ、フリーランスの方には多くの人とのつながりが必要です。昔からの知り合いが仕事を紹介してくれたり、一度仕事をしたクライアントが「あなたの仕事のクオリティが高かったから、知り合いにも紹介したい」と提案してくれたり、つながりをベースに仕事が舞い込むことは珍しくありません。
仕事を得てフリーランスとして活躍し続けるか、案件がなくまた会社員に戻るか。その明暗は、いかにつながりを作れるかにかかっています。
コミュニティが必要な理由 フリーランスにとってなぜコミュニティが重要なのか、その理由はいくつもあります。今回は、特に3つに絞ってご紹介します。
情報や案件の共有による仕事の獲得 最も重要なポイントは、情報共有や案件の共有ができることです。コミュニティには複数のフリーランスがおり、それぞれ人脈を持っています。例えば同じ職種であれば、「今、あの業界で人手が足りてないから案件を獲得しやすい」「このスキルがこれから重要になりそう」「トレンドとしてこれは押さえておきたい」といった話ができます。
フリーランスは、自ら学びの機会を作らなければ、業界の最新情報からすぐに置いて行かれてしまいがちです。だからこそ、常にアンテナを張ってコミュニティ仲間から情報を得ることが重要になります。
また、締め切りが重なり手が回らないタイミングで「この仕事、手伝ってくれない?」という話が回ってくることも珍しくありません。特に、一度仕事をして「この人は信用できる」と思ってもらえれば、それ以降に何度も「また一緒にやらない?」と声をかけてもらえるようになります。
悩み事やトラブルの解決策の共有による心配事の解決 フリーランスのデメリットは、「困った時に気軽に相談できる人がいない」ことです。会社員であれば上司や先輩に相談できますし、同期に愚痴をこぼすこともできるでしょう。しかし、フリーランスは個人で活動しているため、基本的には人に相談することへのハードルが高いです。
しかしコミュニティに入っていれば、同職種のメンバーに「実は最近、こんなことがあって……」と話すことができます。また、フリーランスとして似たような悩みを抱えている人も多いので、一緒に解決に向けた取り組みを実施することができるかもしれません。
大きなトラブルに見舞われても、横のつながりをきっかけに弁護士などを紹介してもらえるケースもあります。何事も一人で抱え込みがちなフリーランスにとって、こういった仲間がいるのは非常に心強いでしょう。
孤独の解消やモチベーションの維持 多くのフリーランスが、「会社にいたころより孤独を感じる」と話します。オフィスに行けば見知った人がいる環境から、完全に一人で仕事をしなくてはならなくなると、孤独感を持つのも無理はありません。客先に出社する働き方もありますが、そこにいるのはあくまでクライアントです。仕事の愚痴を話したり、気軽に仕事後の食事に誘ったりといったことは、なかなかできません。
しかしコミュニティに参加することで、フラットな人間関係を簡単に作ることができます。フリーランスという同じ立場で話も合いますし、「自分は一人ではない」と感じることで孤独感が解消されるでしょう。
また、自分より多くの仕事をこなしていたり、より高単価な案件を獲得している人を見ると、モチベーションにつながります。「あの人も頑張っているから自分も頑張ろう」「いつかあの人のようになりたい」と思える仲間ができるのは、長いキャリアの中でも大きなメリットです。
実際にフリーランスのコミュニティが必要だと思う人は多い 様々な調査の結果、フリーランスにはコミュニティが必要であると考える人が多いことがわかりました。「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2021」によると、全体の半数を超える52%が、「フリーランス同士が交流できるコミュニティが必要だと思う」と回答しています。その理由として、「仕事の情報交換をしたい」「仕事上の人脈を広げたい」「仕事を増やしたい」といったものが挙げられています。
しかし、実際に「情報交換や問題点の共有のために集まり・ネットワークに参加している」と回答した方は、19.3%にとどまります。ここから、「コミュニティに参加はしたいと思っているが、実際に行動には踏み出せていない人が多い」という状況がうかがえます。
また、「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2024」では「フリーランスとして仕事上でトラブルの経験がある」と答えた人が46.6%を占めました。およそ半数の方が、何らかの問題を抱えた経験があるのは、意外かもしれません。
トラブルの内容としては、「不当に低い報酬額の決定」という回答が最も多く、そのほか「報酬の支払いの遅延」「一方的な仕事の取消し」「報酬の不払い・過少払い」なども挙げられています。
こうしたトラブルに、個人で立ち向かうことは非常に大変です。コミュニティにいる先輩フリーランスに相談することで、より効率的に解決することができるようになります。
現役フリーランスが解説するコミュニティの選び方 ここからは、実際にどうやってコミュニティを選べばいいのか、選別のポイントを解説します。現役のフリーランスである編集部の厳しい目で7つの項目をピックアップしたので、ぜひ参考にしてください。
十分な会員数がいるかどうか コミュニティに入るメリットは、様々な方と出会えることです。そのため、会員数は重要な指標になります。10人しかいないコミュニティより100人いるコミュニティの方が、自分と同じ職種や年代の方がいる可能性は高いです。
また、人数が多いほど様々な性格や仕事の方と交流できるチャンスがあり、出会いの幅も広がります。「いつもデザイナーとばかり話していたけど、エンジニアの仲間ができて、仕事をする時に新しい視点を持てた」「ディレクターの人に話を聞いて、イラストレーターして何を期待されているかが分かった」といったように、自分と違う職種だからこそ気づけることもあります。コミュニティ探しの際には、まず会員数を確認しましょう。
参加している人の属性が合うかどうか コミュニティにも性格があり、参加している方の属性は様々です。例えば、若手が多いコミュニティでは20代前半から30代前半までの方が多くを占め、活気に溢れていることが多いです。駆け出しの方も多く、熱気を感じることで自分も「これからフリーランスとして頑張ろう!」と前向きな気持ちになれます。
一方でミドル層が多いコミュニティでは、ある程度の経験があり、「クライアントからのリピートを得るにはどうすればいいか」「次のキャリアステップをどうすべきか」といった具体的な悩みを共有し、お互いに自分の経験を相手に伝えることができます。フリーランス歴が長い人も多く、広い人脈を持つ方とつながれるチャンスもあるでしょう。
属性は、年齢だけでははかれません。例えば、エンジニアの集うコミュニティやマーケターが大半を占めるコミュニティなど、職種が集中しているところもあります。そういった場では、自分と似ているキャリアの方や、同じ悩みを持った方と出会える確率が高いです。話も通じやすく、より多くの情報や仕事を共有し合えるでしょう。
まずは複数のコミュニティのイベントに参加してみて、自分にあっている属性はどんなものかを見極めましょう。
コミュニティが目的に合うかどうか コミュニティを選ぶときには、目的をはっきりさせることが大切です。何のためにコミュニティに所属するのか、改めて考えてみましょう。
案件獲得 コミュニティに所属することで、案件獲得につなげたいと考える方は多いです。実際にフリーランス同士で仕事を紹介しあうケースは多く、人脈が広がれば広がるほど新しい案件を獲得するチャンスは大きくなります。
コミュニティのイベントなどに参加した際は、メンバー同士で案件についてのやり取りがあるかを確認してみてください。「同じ職種の方で一緒に仕事をすることはありますか?」「仕事を紹介した・された経験はありますか?」など聞いてみると、案件獲得につながるコミュニティかどうかがわかります。
スキルアップ コミュニティを通じて、自身のスキルアップにつながるケースもあります。業界でどんなスキルが求められているか情報を得られ、資格を取ったり新しいツールを使えるようにしたりといった機会につながります。
また、フリーランスは周りに似たような立場の人がいないことも多く、目標となる人を見つけにくいです。しかし、コミュニティに所属することで同じ境遇の方と出会え、「こんな風になりたい」と思える方と近づき、人を通じたスキルアップもできるでしょう。
福利厚生 コミュニティには、独自の福利厚生を用意しているケースがあります。例えば、所属費用を払うことで、弁護士への相談ができたり、賠償責任保証をつけられたりといったものがあります。フリーランスは自分の仕事や案件獲得に時間を使うことが多く、こういった周辺的な作業をおろそかにしたり、もしもの場合に備えることを忘れたりしてしまいがちです。
そのため、コミュニティに入るだけでこういった問題が解決することは、非常に効率的だと言えるでしょう。コミュニティによって内容は様々なので、事前にHPなどから確認してください。
交流イベント コミュニティには、ほぼ必ず交流イベントがあります。メンバー同士が集まって、新しい人脈を広げるチャンスです。また、外部から講師などを呼んでイベントを行うこともあります。
クライアントにどのような提案をすればいいのかを学んだり、広告やSEOといった専門的な知識について知見を広げたりと、自分の成長の機会となることが多いので、こういったイベントが頻繁に開催されているコミュニティはおすすめです。
オンライン・オフラインの活動どちらが多いか コロナ禍以降は、コミュニティにおけるオンラインでの活動が活性化しました。ずっとオフラインで行ってきた交流イベントをオンラインに広げたり、Zoomなどをつないで食事会が開かれたりしています。
人によって、「人間関係を深めるためにオフラインで出会いたい」「気軽に参加できるオンラインでの交流がしたい」など考え方は様々です。自分にあったスタイルの活動を行っているかを見極め、どのコミュニティに所属するかを決めましょう。
月会費や年会費などコストパフォマンスが見合うか コミュニティに所属するには、月会費や年会費がかかります。いずれもさほど高額ではありませんが、定期的に発生するコストとなるので「今の自分にこれだけのお金を払う価値が、このコミュニティにあるのか」と検討しましょう。
あまり背伸びして高額なコミュニティに入っても、期待値が高くなり思ったより成果が得られないことは多いです。無理なく支払える金額のところに長期的に所属する方が、メンバーとの仲も深まり案件紹介などのチャンスに広がりやすいでしょう。
【厳選】現役フリーランスが選ぶフリーランスコミュニティ8選 フリーランスのためのコミュニティは数多くありますが、今回は現役のフリーランスであるフリ転編集部が選ぶおすすめを、8つ紹介します。それぞれ特徴が異なるので、「自分はコミュニティに何を求めているのか」を考えながら、どのコミュニティに入るか検討してみてください。
フリーランス協会 「フリーランス協会」の特徴や内容 フリーランス協会は、会員数10万人を誇る国内最大級のフリーランスコミュニティです。年会費は1万円で、賠償責任補償がつき、弁護士費用保険が利用できます。オンライン・オフラインのどちらでも運営している点も魅力的です。また、収入やケガ、介護に関する保険もあるので、もしもの時にも安心。ベネフィットプランでは、お得なクーポンなどが利用できます。
他のコミュニティとの違いは、政策提言を行っていることです。フリーランスはまだまだ法的な整備が整っていない部分もありますが、どのような課題やニーズがあるのかを分析し、関係省庁と連携しています。これにより、契約ルールの整備など、フリーランスにとって必要な環境が少しずつ整ってきています。いわば、フリーランス業界をけん引する存在だと言えるでしょう。
フリーランス協会に所属する一番のメリットは、キャリア支援を受けられることです。セミナーやワークショップ開催の他、個別にキャリアについて相談でき、駆け出しの方にもおすすめです。また、企業向け副業・兼業人材活用相談窓口である求人ステーションを運営していたり、地方創生の事業を通じてワーケーションや他拠点居住などのイベントを行っていたりします。
入会までの手間も、ほとんどかかりません。無料会員になるには、メールアドレスや氏名など基本情報を入力するだけ。無料会員でも、オンライン学習やコワーキングスペースの優待といったメリットを得られます。
年会費 無料/1万円 コミュニティの機能 キャリア支援オンライン学習交流イベントセミナー・勉強会開催ベネフィットプラン利用調査・白書 運営会社 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
「フリーランス協会」に関する口コミ フリーランス協会に関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「フリーランス協会」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・仕事で使うツールを安く利用できてお得
・ベネフィットがありリーズナブルな価格で商品やサービスを購入できる
・セミナーが充実していて学びがある
今やオンライン会議が当たり前の世の中なので、フリーランスとして仕事をする際にZoomなどの利用は必須です。フリーランス協会に入るだけでこれらをお得に使えるとなると、経費削減につながります。また、セミナーも積極的に開かれています。フリーランスになると納税も自分で行わなくてはなりませんが、確定申告やインボイスについて学べるのは駆け出しの方にとってありがたいでしょう。
デメリット
・政策提言などをしているが的外れだという意見も出ている
・国や政府への行動に対し疑問がある
近年、インボイス制度を巡りSNS上でも様々な議論が行われています。人によっては、フリーランス協会の動きや発言に納得できないということもあるようです。とはいえ、メンバーに対する不満や開催しているイベントの質などについての悪評は見られませんでした。
会員数10万人超という、国内でも最大級の規模を誇るフリーランス協会。大きい組織だけに、安心感があります。セミナーや勉強会など、オンライン・オフライン問わず開催されていますし、キャリア相談もできるので駆け出しの方からフリーランス中級者、ベテランまでおすすめの協会です。
Workship 「Workship」の特徴や内容 Workshipは、登録者が5万人を超えるフリーランスのためのプラットフォームです。3500件もの案件があるため、まだなかなか案件が獲れないという方も新しい仕事のチャンスを得られるでしょう。時給3000円〜5000円と高単価案件も多く、キャリアを積んだ中級~ベテランのフリーランスの方もおすすめです。
そんなWorkshipでは、 2021年5月からWorkship LABというクローズドのコミュニティが生まれました。年会費は無料で、基本的にはXを通じて交流しています。コミュニティ内では、フリーランス同士がお互いの悩みを共有したり、ノウハウを教えあったりと相互的な活動が見られます。また、会員に向けたメルマガも発行されています。
Workshipに参加する一番のメリットは、案件を探せることです。エンジニアからディレクター、デザイナー、マーケター、人事、広報など、幅広い職種の仕事を見つけることが可能です。また、Workship MAGAZINEというオンラインメディアも運営しており、フリーランスのよくある悩みを解決するような記事を読んだり、オンライン・オフラインのイベントに参加できます。
入会するには、まずWorkshipの会員になります。この時、自分の職種や年収などを入力してください。登録が完了するとメルマガが送られてくるようになるので、メール本文中にあるリンクからコミュニティに入会しましょう。
年会費 無料 コミュニティの機能 案件紹介オンラインマガジン交流イベントセミナー・勉強会開催 運営会社 株式会社GIG
「Workship」に関する口コミ Workshipに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「Workship」の口コミ分析によるメリット・デメリット Workshipに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「Workship」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・掲載される案件が増えてきている
・新しい仕事を獲得できる
Workshipは案件探しに特化しているため、これから仕事を獲得していきたいフリーランスにおすすめです。実際にWorkshipから新しい仕事を得て稼働を始めた方のコメントも、SNSで見られました。
デメリット
・自分の求める条件の案件が見つかるかわからない
・週2稼働など、ライトな案件が少ない
Workshipにはたくさんの案件がありますが、それでも自分が求めるものがあるとは限りません。「フルリモート希望」「経験が浅くても挑戦したい」など、こだわりが増えるとなかなか案件が見つからないでしょう。特に、稼働時間の少ない案件はさほど多くはないようです。
これからどんどん案件を探したい方にとって、Workshipは頼もしい存在です。特に仕事を探している駆け出しの方は、クラウドソーシングなどに比べると好待遇の案件を見つけられるでしょう。コミュニティであるWorkship LABに入るにはまずWorkshipへの会員登録が必要なので、アカウントを作り仕事を探してみてください。
新しい働き方LAB 「新しい働き方LAB」の特徴や内容 新しい働き方LABは、クラウドソーシングのランサーズが運営するコミュニティです。様々なフリーランス向けイベントがオンライン・オフラインで開催されており、交流会などを通して新しい出会いが見つかります。
セミナーでは、自分と同じ立場であるフリーランスが講師となり、実際に現場で必要となる知見を共有します。フリーランス向けのコワーキングスペースも利用でき、同業者を見つけやすい環境です。
最大の特徴は、研究員制度を取り入れていることです。これは、今の働き方から新しい働き方にチャレンジしたい方を対象とした制度となります。また、自分がやってみたいことを試せる実験プロジェクトというものがあり、個人で考えた企画を実践したり、企業が指定した企画に挑戦したりできます。
入会は、Googleフォームから氏名や職種などを送信し、Facebookグループに参加をリクエストを送るだけです。申請が承認され次第、すぐに入会できます。
年会費 無料 コミュニティの機能 キャリア支援交流イベントセミナー・勉強会開催 運営会社 ランサーズ株式会社
「新しい働き方LAB」に関する口コミ 新しい働き方LABに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「新しい働き方LAB」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・様々なセミナーに参加できる
・研究員制度で成長できる
・イベントを通じて新しい出会いがある
新しい働き方LABでは、様々なテーマのセミナーが開かれています。SEOやクライアントとのコミュニケーションのほか、どうやってキャリアを築いていくかなど、フリーランスとして知っておくべき内容のセミナーが豊富です。また、研究員制度を使って新しいチャレンジに取り組んでいる方も多く見られました。交流会などイベントを通じて人脈が広がる点も、大きなメリットです。
デメリット
調査の結果、デメリットに関してはSNS上で見つかりませんでした。
研究員制度という、他にはない取り組みを実施している新しい働き方LAB。いきなり研究員として申し込むのはハードルが高いかもしれませんが、過去の研究員の方のレポートなども閲覧できるので、まずはそういったコンテンツからチェックしてみましょう。
FleelanceNow 「FleelanceNow」の特徴や内容 FleelanceNowは、5000人以上のフリーランスが登録しているコミュニティです。職種の幅が広く、エンジニアが20%、デザイナーが20%、コンサルタントが20%、ライターが10%、マーケターが10%、ディレクターが10%、その他が10%という構成になっています。
特徴は、年間100回というイベントの多さです。フリーランス同士が集まって飲食をするものもあれば、地方から起業家を呼びチームを作って課題を解決するための方法を考えプレゼンをするといった実践的なものもあります。基本的にはクローズドのFacebookページで交流しており、ページ内では企業からの依頼も投稿されるため、案件獲得も可能です。
入会は、Facebookの「フリーランスに仕事・案件が集まるグループ(FreelanceNow/フリーランスナウ)」に入会し、承認を待つだけ。アカウントさえ持っていれば、すぐに参加できます。
年会費 無料 コミュニティの機能 案件紹介交流イベントセミナー・勉強会開催 運営会社 フリーランス株式会社
「FleelanceNow」に関する口コミ FleelanceNowに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「FleelanceNow」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・フリーランスにとって有益なセミナーが開催されている
・コミュニティメンバーと交流できる機会が多い
・フリーランスとして活動している人の話を直接聞くことができる
デメリット
調査の結果、デメリットに関してはSNS上で見つかりませんでした。
FleelanceNowの口コミをリサーチすると、フリーランスにとって学ぶべき情報がたくさん入ってくるコミュニティだと感じられました。年会費も無料で気軽に参加できるので、「色々と見てみたが、結局どのコミュニティに入るか決められない」という方は、まずはここでフリーランスコミュニティデビューをしてみるのはいかがでしょうか。
Home Worker’s Community 「Home Worker’s Community」の特徴や内容 Home Worker’s Communityは、「クリエイティブ/IT業界に関わるヒト・コト・モノをつなぐ。」をコンセプトに、フリーランスに対してWeb制作を中心とした案件を紹介しています。会員数は非公開ですが、エンジニアやデザイナー、ライターなどが登録しており、企業HPの制作やLPの運用などを手掛けています。メンバーの実績作りにするため、セミナー講師やイベント登壇などをバックアップしてくれる点は、フリーランスにとって魅力的です。
Home Worker’s Communityの特徴は、営業代行を依頼できることです。スタッフが企業にヒアリングし、登録しているフリーランスのニーズに合わせて提案してもらえます。営業に苦手意識を持つ方は少なくありませんが、ただ待っているだけで仕事が舞い込んでくる状況を作れるので安心です。
登録には、「フリーランスまたは現場にて実務のご経験3年以上」という資格が設定されています。こちらに該当する方は、まず会員登録ページから基本情報を入力し、実績などを登録します。スタッフが一人ひとりにあった案件を紹介してくれます。
年会費 無料 コミュニティの機能 案件紹介セミナー・勉強会開催 運営会社 ホームワーカーズコミュニティ株式会社
「Home Worker’s Community」に関する口コミ 調査の結果、Home Worker’s Communityに関する投稿はSNS上で見つかりませんでした。
3年以上の経験が求められるだけに、登録しているメンバーは中堅〜ベテランがメインとなりそうです。実力がついてきて制作に集中したい方にとっては、営業代行機能があるHome Worker’s Communityは、とても相性のいいコミュニティでしょう。
Wor-Q 「Wor-Q」の特徴や内容 Wor-Qは、「納品したのに報酬が払われない」「立場が弱く取引先からハラスメントを受ける」といった、フリーランスを取り巻く様々な問題を解決するために生まれたコミュニティです。フリーランスを対象としたリサーチを行いレポートを出したり、トラブルの際に弁護士サポートを提供していたりします。
最大の特徴は、Wor-Q共済という独自の共済を提供していることです。入会することで、基本共済と「団体生命共済」「総合医療共済」「賠償保障制度」「所得補償制度」といったオプションを選ぶことができます。
メルマガを受け取るだけの連合ネットワーク会員は、HPからメールアドレスなどを入力するだけで登録できます。こちらは、年会費がかかりません。3000円の年会費を支払いWor-Qライフサポートクラブに加入すると、様々な福利厚生サービスを利用できるようになります。
年会費 無料/3000円 コミュニティの機能 交流イベントセミナー・勉強会開催福利厚生サービス 運営会社 日本労働組合総連合会
「Wor-Q」に関する口コミ Wor-Qに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「Wor-Q」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・フリーランスへのサポートが期待できる
・運営団体に対する安心感
発足のきっかけがフリーランスを守るためという背景もあり、取引で弱い立場に立たされがちなフリーランスからの期待感が感じられました。また、主催している団体が日本労働組合総連合会であることから、安心感を持っているフリーランスも多いようです。
デメリット
調査の結果、デメリットに関してはSNS上で見つかりませんでした。
Wor-Qのサイトには様々なレポートや記事が掲載されています。どれも非常に有益で、これからフリーランスとして活躍したい方に読んでいただきたい内容ばかりです。また、取引先とのトラブルの際に弁護士に相談できるなど、フリーランスへのサポートが手厚い印象でした。
@World 「@World」の特徴や内容 @Worldは、200名の登録者を持つコミュニティです。旅好きのフリーランスが集まり、オンラインやオフラインで交流しています。基本的にはSlackでのやり取りをメインに、日々の情報交換やコミュニケーションを行っています。フリーランスだけでなく、フルリモートで働く会社員の方も登録可能です。
@Worldでは、様々な交流会が行われています。月に一度メンバーが近況を報告する全体交流会や、「お酒好き」「朝活希望」などの有志が集まるサークル活動のイベント、ちょっとした雑談のためのオンライン集会など、自分の興味のあるものに参加可能です。また、定期的にワーケーションイベントも開催しているので、普段は訪れない町でフリーランス仲間と一緒に仕事ができる点も魅力です。
入会するには、HPからチケットを購入します。年間チケットの他、月額チケットもあるので「まずは試しに雰囲気を味わいたい」という方は、月額がおすすめです。
年会費 19,800円 コミュニティの機能 交流イベントセミナー・勉強会開催 運営会社 合同会社アットワールド
「@World」に関する口コミ @Worldに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「@World」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・セミナーに参加すると新しい学びがある
・イベントでメンバーとオフラインの交流ができる
・新しいチャレンジのきっかけがある
@Worldでは、フリーランス向けの様々なセミナーが開催されています。少しとっつきにくい内容でも講師から直接教わることで理解度が上がり、一人で勉強するよりも効率的に学べそうです。また、オフラインのイベントも多々行われており、メンバー同士の交流機会も多いです。
デメリット
調査の結果、デメリットに関してはSNS上で見つかりませんでした。
口コミを調べると、明るく積極的なメンバーが多い印象でした。「旅好き」がコンセプトになっているため、行動力のある方が多いからだと思われます。フリーランスとしてたくさんの経験を積みたい方、積極的な仲間を作りたい方、旅が好きな方におすすめのコミュニティです。
DMMオンラインサロン 「DMMオンラインサロン」の特徴や内容 DMMオンラインサロンは、会員数18万人、コミュニティ数1600以上という大規模なコミュニティです。主な事業として、オンラインサロンの運営を行っている方のサポートを提供しています。英会話やヨガ、占いなどの活動をフリーランスで行っている方には、うってつけのコミュニティだと言えます。
最大の特徴は、バリエーション豊かなオンラインサロンが存在していることです。上記に挙げたもの以外にも、医薬品について知識を得られるサロンや、競馬の情報が提供されるサロン、FXに特化したサロンなどがあります。サロンを開くことで、自分が中心となってコミュニティを形成でき、サロンの活動を通して売上を得られるのは、他のサービスにはないメリットです。
入会するには、まずDMMアカウントを取得します。次に活動名やサロンの概要を入力し、送信します。メールで審査結果が送られてくるまで待ちましょう。
年会費 無料 コミュニティの機能 オンライン学習交流イベントセミナー・勉強会開催 運営会社 合同会社DMM.com
「DMMオンラインサロン」に関する口コミ DMMオンラインサロンに関する口コミを集めてみました。良い点・悪い点のどちらも確認してみましょう。
「DMMオンラインサロン」の口コミ分析によるメリット・デメリット メリット
・サロンの内容が勉強になる
・オフラインのイベントにも発展する
・サポートが充実している
DMMオンラインサロンには様々なサロンがありますが、それぞれへの満足度は高いようです。ジャンルに関係なく、「勉強になった」という口コミが複数見られました。また、オンラインサロンから発展して、オフラインのイベントが開かれているケースもあるようです。さらに、オーナー専用サポート窓口があるほか、オーナー向け勉強会やサロン解説支援、オフィスレンタルの利用など、サポート体制も充実しています。
デメリット
・怪しいと思っている人がいる
・お金儲けに関するものが多い
口コミを見ていると、オンラインサロンに対して漠然と「怪しい」「詐欺のよう」といったイメージを持っている方が一定数見られました。しかし根拠はなく、「なんとなく怪しそう」というものばかりでした。また、FXや投資関連のサロンも多いことから、お金儲けについてばかりという口コミも見られました。
SNSで様々な情報をリサーチした結果、DMMはサロン参加者にとっては勉強になり、オーナーにとってはコミュニティを形成できるという、どちらにとってもメリットのあるサービスだということがわかりました。オンラインサロンに対して漠然としたネガティブイメージを持っている方もいますが、根拠のある批判はほとんどなかったため、安心してスタートできるでしょう。
フリーランスコミュニティを上手く活用する方法 フリーランスコミュニティは、入っただけでは意味がありません。上手く活用してこそ、入会した効果を実感できます。
コミュニティに入会して終わりではない コミュニティに入ること自体が目的になってしまうと、自己成長や人脈の広がりなどにつながりません。入った後に、自分がどう動くかが大切です。どのコミュニティでも交流会が行われているので、まずはそれらにどんどん参加してみましょう。
そこで知り合いを作り、おすすめのセミナーに参加したり、キャリア支援のプログラムを受けたりと、どのように活用の幅を広げればよいか相談するとよいでしょう。
セミナーなどのイベントを体験してから入会する コミュニティに入ったものの「なんだか合わない」「思っていた雰囲気と違う」と後悔してしまうケースはよくあります。そういった失敗を避けるためには、まず体験をしてみることが重要です。セミナーを受講したり、イベントに参加したりと、実際にどのような活動をしているのか自分の目で確かめてみましょう。
オフラインイベントに参加して横のつながりを作る ほとんどのコミュニティではオンラインイベントを開催していますが、やはり人との関係をゼロから作るにはオフラインがおすすめです。最初にオフラインで関係を作れれば、そこから先はオンラインでも人脈を保ちやすくなります。参加ハードルの低いメンバー交流会などがあれば、積極的に顔を出しましょう。
コミュニティ内で学びを積極的に交流・発信する コミュニティに入ったら、自分が学んだことや気づいたことなどを、積極的に発信していきましょう。「恥ずかしい」「間違ったことを言っていたらどうしよう」という不安があるかもしれませんが、何も発信しなければコミュニティ内で自分の存在感を出すことはできません。
「新しい案件を獲得したい」「フリーランス仲間を増やしたい」という目的を達成するために、まずはチャットやコミュニティでのSNSで投稿することから始めてみてください。
【調査結果】フリーランスコミュニティに参加した人の声 フリーランスコミュニティに参加した人は、どのような感想を持っているのでしょうか。様々な切り口から、リアルな声を探してみました。
独立前のフリーランスの不安について調査した結果・・・ フリーランスとして独立する前は、とにかく不安を持っている方が多いです。「本当に自分にできる?」「食べていけなかったらどうしよう」など、生活や将来のキャリアへの不安が多々あります。
また、具体的にどのようにフリーランスになったらいいかわからないという不安を抱える方もいました。営業活動にも苦手意識があり、「仕事が獲得できないかも」という声も見られます。
独立後のフリーランスの後悔について調査した結果・・・ 会社員であれば、オフィスに行けば同僚や先輩・後輩、上司・部下などとコミュニケーションを取ることができます。しかし、フリーランスにはそういった関係性の人がいないため、孤独を感じやすいです。自由な時間に働けるものの、寂しさを感じる方は少なくありません。
また、一人で仕事をしているとスキルアップのチャンスを逃してしまうこともあります。モチベーションを保つのも難しく、ついついさぼってしまい後悔している方も多いようです。
フリーランスコミュニティに入った人の声を調査した結果・・・ フリーランスコミュニティに入った方は、実際にどんなふうに感じているのでしょうか。リアルな声を、SNSでリサーチしました。
フリーランスコミュニティのポジティブな意見 コミュニティに参加することで、スキルアップのチャンスを得られることは多いです。どのコミュニティでもセミナーを開催していることが多いため、それをきっかけに新しいスキルを手に入れられます。また、すでにプロとして活躍している方と出会えるため、「今はライターだけど、これからディレクターを目指したい」といった相談ができる点もメリットです。
他にも、身近に同じ立場のフリーランスがいることでモチベーションが上がります。出会いの幅も広がり、そこから案件獲得につながることも多いです。
フリーランスコミュニティのネガティブな意見 フリーランスコミュニティには、マイナス面もあります。特に人づきあいが苦手な方は、人とコミュニケーションをとらなくてはならないため、ストレスを感じてしまうかもしれません。また、フリーランスコミュニティとみせかけたマルチ商法や詐欺に遭ってしまった方もいるようです。
フリーランスコミュニティに入会すべき人とそうでない人
フリーランスコミュニティは、入るべき人とそうでない人にわかれます。以下の条件をもとに、入るべきかどうか改めて検討してみてください。
人付き合いを増やしたくない人は無理に入らなくてもよい コミュニティに入ると、たくさんの人との出会いがあります。それによって、新しいスキルが身についたり案件獲得につながったりとたくさんのメリットがあります。しかし、そもそも人付き合いをしたくないという方にとっては、コミュニティに入るメリットはほとんどありません。そういった方は、個人で淡々と仕事を進めるスタイルがあっているでしょう。
フリーランスとして長期で活躍したい人には必須 これからフリーランスとして活躍していきたい、不安はあるものの頑張りたいと思っている方には、フリーランスコミュニティへの入会が非常におすすめです。先輩フリーランスから話が聞けたり、同じ立場の仲間ができたりと、仕事を頑張るモチベーションに繋がります。
また、コミュニティからキャリア支援を受けたり、案件を紹介してもらえたりといった、実利面でのメリットも見逃せません。
新感覚RPGコミュニティのフリ転が始動 2024年、新たなフリーランスコミュニティが生まれました。それがフリ転です。まだ運営を開始したばかりなので、メンバーが凝り固まっていたり、運営内容が固定化されていたりといったことがありません。毎月入会するフリーランスがたくさんおり、メンバーの声も運営に反映される、柔軟なコミュニティです。
「とりあえず、勢いのあるコミュニティに入ってみたい!」という方はもちろん、「初期メンバーとしてコミュニティのベースを一緒に作り上げたい」「こんなコミュニティだったらフリーランスのためになるというアイディアを出したい」という方も大歓迎。セミナーや勉強会の内容、オンライン・オフラインイベントのコンテンツなど、メンバーの意見を積極的に採用します。
「クリエイターRPGギルド」をコンセプトとしたフリ転は、エンジニアやデザイナーなど、様々なスキルを持ったフリーランスが集まっています。ぜひ、あなたのクリエイティブなスキルを活かして、フリ転を一緒に盛り上げていきましょう!
年会費 無料 コミュニティの機能 <実施中>オンラインマガジンポートフォリオ掲載交流イベント(オフライン・オンライン)セミナー・勉強会開催<準備中>分科会・イベント企画メンター紹介オンライン学習キャリア支援 運営会社 株式会社日本デザイン