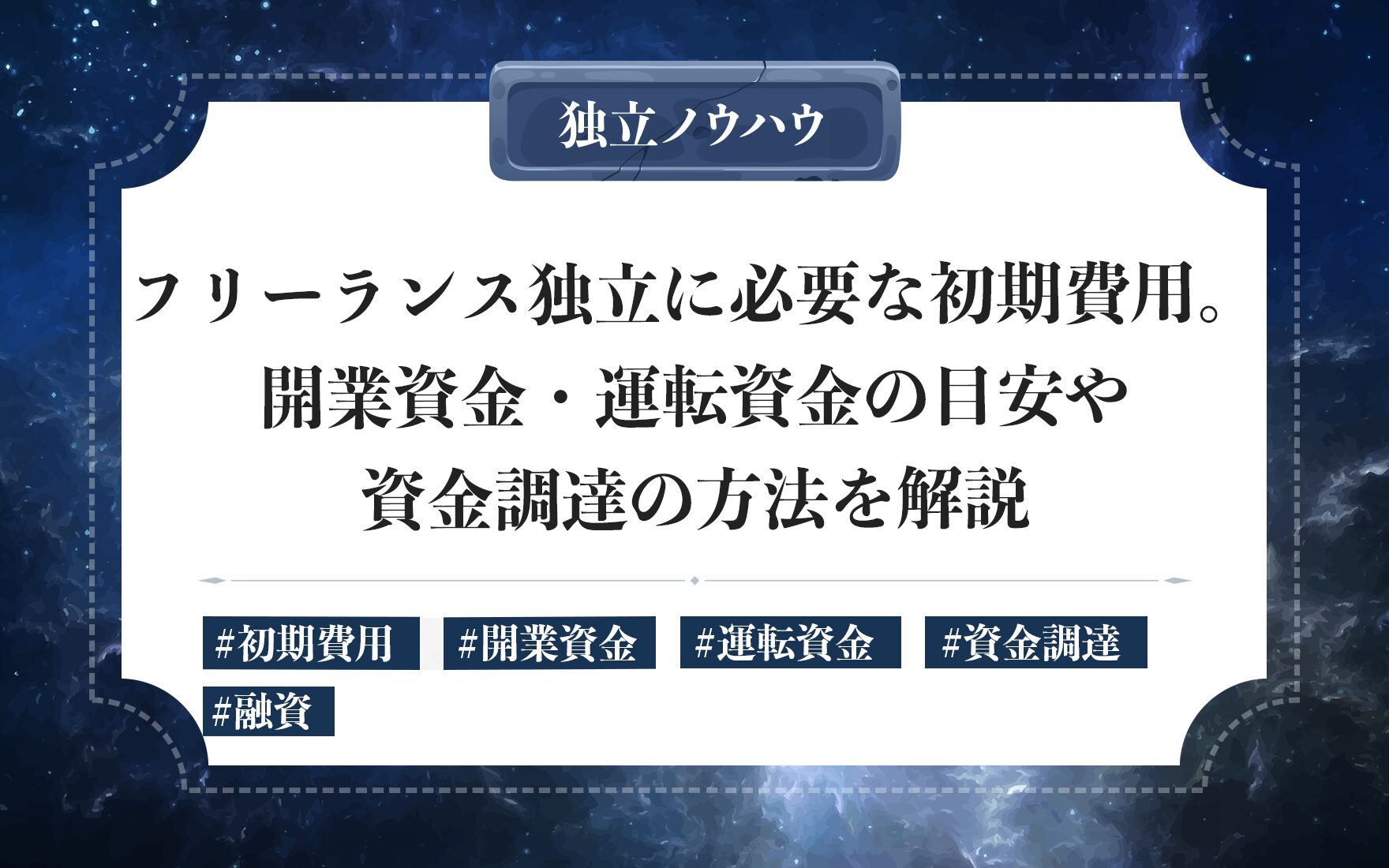今回は、フリーランスとして独立したい、またフリーランスの駆け出しという方向けに、独立・開業する際に考えなければならない開業資金としてどんなものがあるか、その調達方法、さらにその先の資金計画の立て方などについてお伝えします。
フリーランスの開業資金は業種によって異なり、設備投資などを抑えて数万円で始められるケースもあります。資金調達の方法もいくつかありますが、無理のない資金繰りをしていくためにも開業資金はできるだけ抑えるのがおすすめです。安定的な事業運営を目指して開業資金を検討しましょう。
フリーランスの独立・開業時にかかる開業資金
フリーランスとして独立・開業する際には、業種や働き方によって必要な資金が大きく異なります。開業資金の目安や運転資金の確保についてお伝えします。
開業費用は平均で約1,027万円
フリーランスの開業費用は業種によって異なりますが、日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、平均で約1,027万円とされています。特に、オフィスを構える必要がある業種や設備投資が必要な場合は、初期費用が高額になる傾向があります。
<開業費用の分布>
- 250万円未満:20.2%
- 250万~500万円未満:23.6%
- 500万~1,000万円未満:28.4%
- 1,000万~2,000万円未満:18.8%
- 2,000万円以上:9.0%
パソコンさえあればできる業種であれば数万円
一方で、ライターやデザイナー、エンジニアなど、パソコンとインターネット環境があれば始められる業種であれば、数万円程度の初期投資で済むケースもあります。
たとえば、
- パソコン購入費(新品で10万円~20万円、または中古で数万円)
- 必要なソフトウェアやツールの購入費
- ドメイン・サーバー費用(年間1万円程度)
などが主な費用となります。
運転資金は3カ月~6カ月分を確保
開業後すぐに安定した収益を得るのは難しいため、運転資金として最低でも3カ月~6カ月分の生活費や事業資金を確保しておくのがおすすめです。
特に、フリーランスは収入が不安定になりがちなので、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
開業前の費用も開業費として計上できる可能性も
開業準備にかかった費用(例:備品購入費、資格取得費、広告宣伝費など)は、「開業費」として経費計上できる可能性があります。税務上の扱いについては、税理士や専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
CHECK
・フリーランスの開業費用の平均は約1,027万円だが、数万円で可能な業種もある
・開業後すぐの安定収益は難しいため、運転資金として3カ月~6カ月分の費用を確保
・開業費として経費計上できる可能性もあるので専門家に相談を
開業資金の内訳・具体例
開業する際は、初期費用と業務のための運転資金、さらに日常の生活費が必要です。それぞれ具体的にお伝えしていきます。
開業に必要な初期費用
開業には、事業登録・届出費用、開業届(税務署への届出)、青色申告承認申請(節税対策)、各種許認可(業種による)などさまざまな届出や申請が必要ですが、基本的にはこれらは費用はかかりません。届出や申請以外で開業の準備として費用がかかるものを挙げていきます。
設備・備品購入
- PC・タブレット・スマートフォンなど、業務に必要なデバイス
- プリンター、スキャナーなど、作業効率を上げるための周辺機器
- 机・椅子・照明など、快適な作業環境を整えるための自宅作業スペースの設備
- 外で作業する場合の選択肢としてのコワーキングスペースの契約
- 業種や事業規模などの必要に応じたオフィス賃貸
マーケティング・宣伝
- ビジネス用名刺の作成
- 集客やブランディングのための自社Webサイトの構築
- Webサイトを運営するためのドメイン・サーバー代
- 集客のためのオンライン広告(SNS広告、Google広告など)
- 営業資料の作成
研修・スキルアップ
- 業務スキルの向上のためのセミナーやオンライン講座への参加費
- 資格取得のための費用
- 専門知識を深めるための投資としての書籍や資料の購入費
業務のための運転資金
フリーランスとして業務を継続的に進めていくために必要な資金を挙げていきます。
サブスクリプション
- インターネット・携帯電話などの通信費
- クリエイティブな業務をする場合のデザイン・編集ツール(Adobe、Canvaなど)
- 会計管理に必要な会計・経理ソフト(freee、弥生会計など)
- データ管理や共有のためのクラウドサービス(Google Workspace、Dropboxなど)
外注・アシスタント
- デザイン、ライティング、マーケティングなどを外部委託する場合の業務委託費
- 税務処理などをサポートしてもらうための税理士・会計士費用
税金関連積立
- 所得税・住民税
- 課税事業者の場合の消費税
保険関連費用
- 国民年金・国民健康保険
- 賠償責任保険などの事業用保険
- 保険・福利厚生として活用できるフリーランス協会などの加入費
交際費
- 飲食や接待などクライアントとの打ち合わせ費
- 人脈づくりや交流のためのネットワーキングイベント参加費
交通費
- 出張・打ち合わせのための移動費
- 交通ICカード・車両の維持費
急な怪我や病気にも対応できる生活費
最後に日常生活を送るために必要な生活費を挙げていきます。いざという時に困らないように、開業の際は生活費のことも念頭に入れて準備しましょう。
- プライベートの支出となる基本的な生活費
- 家賃・住宅ローンなどの住居費
- 在宅ワークの場合の電気代・水道代・ガス代
- 食費・生活雑費
- 急な収入減に備えた蓄え
- 医療費
CHECK
・開業時に必要な費用は、初期費用、運転資金、生活費に分けられる
・初期費用は設備費やマーケティング費など、運転資金には通信や税金関連費などが含まれる
・このほか日常生活を送るための生活費も備えが必要
まずは開業資金を極力減らして独立すべき
開業してすぐに収入を安定させるのは難しいことなので、リスクヘッジとしてまずは開業資金は極力減らして独立することをおすすめします。そのための方法をご紹介します。
自宅をオフィスとして活用する
初期投資を最小限に抑えるために効果的な方法が、自宅をオフィスとして活用することです。賃貸料やオフィスに必要な光熱費、通勤費などの経費を削減できるため、コストパフォーマンスが非常に高いです。
開業時は特に、大きなオフィスを構える必要はありません。自宅であれば毎月の固定費を大幅にカットできるので、事業が軌道に乗るまでの負担を軽減できます。
本当に必要な設備だけを購入する
初期投資を抑えるために、初めは最小限の設備でスタートしましょう。パソコンやスマートフォン、インターネット環境といった基本的なツールは不可欠ですが、そのほかの家具や最新機器などは、事業が拡大するまでは不要です。
また、クラウドサービスやレンタルオフィスを活用すれば、物理的なオフィスを持たずに事業を運営することもできます。
広告費をかけずに営業活動する
広告費をかけない営業活動も有効です。特に、ターゲットとなる顧客層に向けた投稿や情報発信ができるSNSを活用したマーケティングは、低コストで多くの人にリーチできるため、効果的に認知度を高めることができるでしょう。
さらに、口コミや紹介によって新規顧客を獲得することも可能です。
CHECK
・開業時はリスクヘッジとして、開業資金はできるだけ抑えるのが重要
・そのためには、自宅をオフィスにする、必要以上の設備を購入しないという方法がある
・初期の営業活動には広告費をかけずにSNSや口コミなどを活用するのもポイント
資金調達方法
開業時の資金を調達する方法はいくつかあります。それぞれメリットと注意点があるので自分に合った方法を選んでください。
お金を貯めて自己資金で独立
まずは開業に必要な資金を自分で貯めて独立する方法です。もっとも基本的な資金の調達手段と言えるでしょう。自己資金であれば返済の必要もなく利息もかかりません。
ただし、自分で用意できる資金には限度があるため、その後の事業計画を踏まえて、ほかの方法と合わせて検討することをおすすめします。
銀行融資・制度融資の活用
銀行融資や制度融資を活用して資金不足を補うことで、事業の安定的な運営が可能となります。銀行融資はもっとも一般的な融資形態。金利や返済条件が企業の信用に応じて異なります。
一方、制度融資は政府や地方自治体が支援する融資で、低金利や返済期間の延長など、企業にとって有利な条件が整っているものも多いでしょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府系金融機関として主に中小企業や創業者に向けて融資を実施しています。特に創業支援や事業拡大を目的とした融資プログラムが豊富で、低金利や返済条件の緩和が特徴です。新たに事業を始める場合は創業支援融資がおすすめです。
また日本政策金融公庫は、創業者向けに必要なノウハウやアドバイスも提供していて、融資だけでなく、ビジネスの成長を支援するためのサービスも充実しています。
地方自治体の創業支援融資
地方自治体が提供する創業支援融資は、地域経済の活性化を目指して、地域内で事業を始める起業家をサポートしています。
金利の低さや返済条件の柔軟性が魅力で、地域によっては、融資に加えてさまざまな支援策を提供している場合もあります。地域とのつながりを強化して事業をスムーズに立ち上げられるのがメリットでしょう。
補助金・助成金の活用
補助金や助成金は、政府や地方自治体が特定の目的に対して無償または低額で提供する資金です。返済の義務がないため、特に資金に余裕がない初期段階においては、事業運営の大きなサポートとなるでしょう。
創業補助金
創業補助金は、新たに事業を始める創業者を支援するためのものです。創業準備や設備投資、マーケティング活動などの初期費用を補助することが目的で、特に中小企業庁などが実施しています。
創業補助金を受けるためには、事業計画書や事業の社会的意義などをまとめた書面を提出して、審査を通過する必要があります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象にした支援制度で、事業の継続や発展を支援するものです。
広告宣伝費やWebサイト作成費、設備導入費など、事業の運営や成長を目的とした投資に対して支給されます。小規模事業者の経営安定化や新規顧客の獲得のために有効です。
ビジネスローン・カードローンの活用は慎重に
資金調達の方法として、ビジネスローンやカードローンの活用がありますが、これらは注意が必要です。
リスクとして、事業が順調でない場合に資金繰りが苦しくなる、仮に返済が滞ると信用情報に悪影響を及ぼしてしまいその後の資金調達が難しくなる、金利負担が高いことなどが挙げられます。
ビジネスローンやカードローンを利用する際は、返済計画をしっかり立てて、事業のキャッシュフローや将来の見通しを慎重に見極める必要があります。
資金計画のポイント・進め方
フリーランスとしての開業時における資金計画のポイントと進め方をお伝えします。開業時には事前にしっかりと資金計画を立て、予想される支出や収入の流れに対応できるよう準備しておくことが事業成功のカギとなります。
開業前の準備期間に必要な設備から初期費用を見積もる
まずは開業のために必要な設備を検討してください。事業に必要なパソコン、オフィススペース、事務機器、専門的なツールなどです。
必要な設備は業種によって異なるほか、初期費用はなるべく抑えるのが大切なので、自分の業務に本当に必要なものか考えましょう。
収入が安定するまでの期間を想定して運転資金を見積もる
キャッシュフローのシミュレーションをして、収入が安定するまでにどれくらいの期間が必要かを考えましょう。そしてその間の運転資金を見積もります。
運転資金にはインターネット・携帯電話などの通信費、税金・保険関連の費用、交通費などが含まれます。毎月どれぐらい必要か、どれぐらいの期間分必要か、しっかり計算しましょう。
最低3カ月分、できれば6カ月分の運転資金を準備する
開業後すぐの事業が不安定な時期も資金不足にならないように運転資金を準備しましょう。
最低でも3カ月分、できれば6カ月分の資金の確保が理想的です。
突発的な支出や収入の遅れに備えて、運転資金に余裕を持たせ、事業の途中で資金繰りに困らないようにすることをおすすめします。
収支計画を立て黒字化までの期間を予測する
事業の売上、経費、利益を月単位で予測して、黒字化できるまでの期間を予測します。できるだけ早い段階での黒字化が理想ですが、無理な計画ではなく、現実的に達成可能なスケジュールを考えましょう。
毎月収支管理をして資金繰りの見通しが立つようにする
事業がスタートしたら、毎月の収入と支出を記録して、予算と実績を比較することで、資金繰りを適切に管理します。
事業を安定的に運営できるよう、定期的にキャッシュフローをチェックして、収支のバランスを見ながら資金繰りに支障がないようにしましょう。
税金や社会保険料の支払いに備えて資金を確保しておく
フリーランスの場合、個人事業主として所得税、消費税、社会保険料などを納める必要があります。これらの支払いが遅れないように、事前に必要額を積み立てておくことが重要です。
場合によっては税金や社会保険料のまとまった支払いが必要になることもあるので、その時に困らないよう、毎月一定額を積み立てておくことをおすすめします。
CHECK
・資金調達は自己資金、融資、補助金や助成金の活用などの方法がある
・ビジネスローンやカードローンは資金繰りに影響する可能性もあるため慎重に検討
・開業から事業の安定運営まで、無理のないキャッシュフローを検討することが重要
フリーランスとして独立するためには、設備などは必要最小限にして、開業資金も抑えてスタートするのがおすすめです。その後は、運転資金を含めて堅実な資金計画を立てて、無理のない資金繰りが事業の安定運営とフリーランスとしての成功のカギとなります。