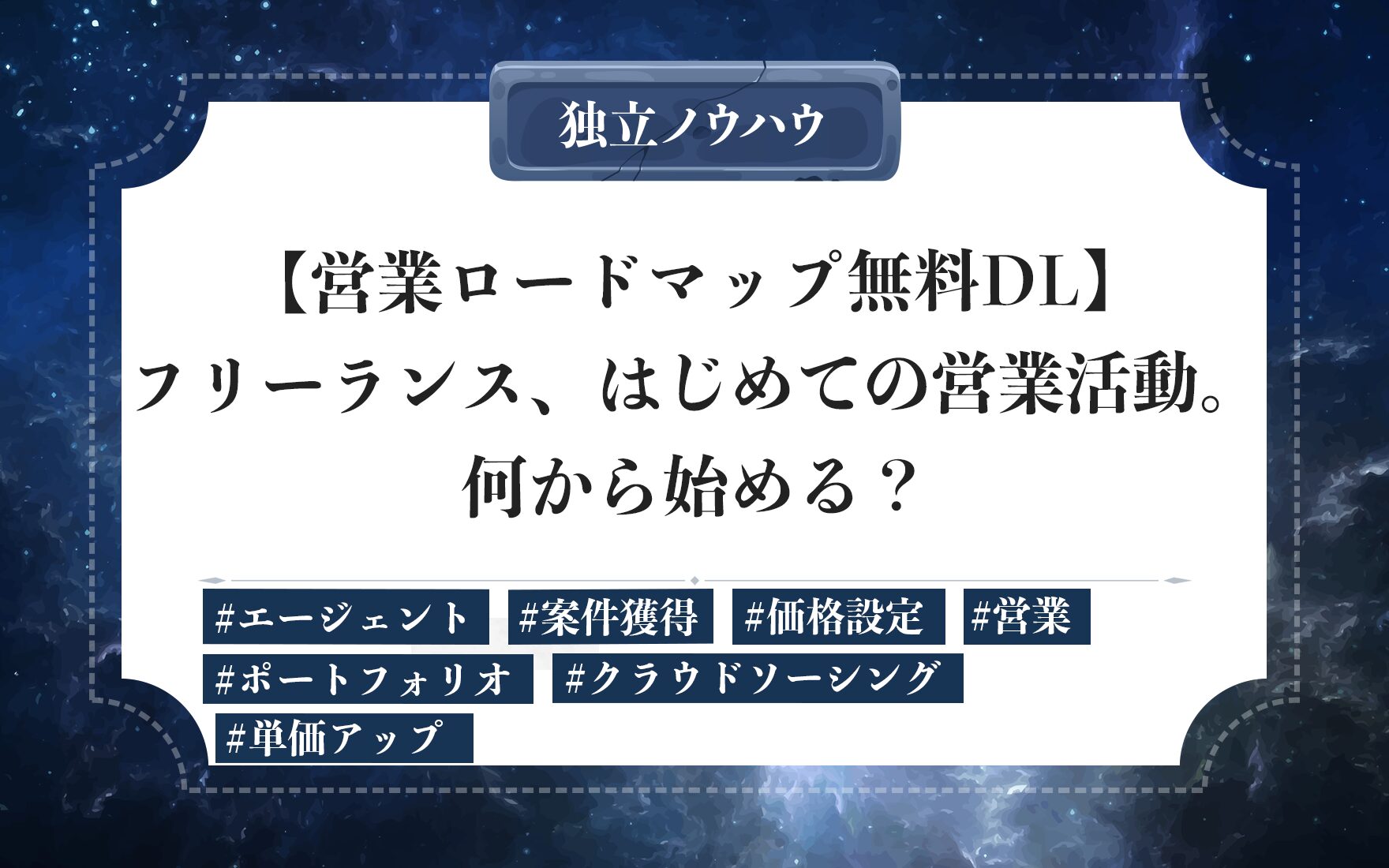フリーランスになったばかりの方が最も悩むのは、「どうやって案件を獲得すればよいのだろう」という点ではないでしょうか。特にスキルやコネクション、実績がないうちは、営業が上手くいかないことも多いものです。
今回は、フリーランスの案件獲得方法について解説します。具体的なプロセスやどういった手段があるのかなど紹介するので、これから仕事をどんどん取りたい方はぜひ参考にしてください。
フリーランスの営業活動。何から始めるべき?
フリーランスになるにあたって、営業は何から始めればよいのでしょうか。結論、フリーランスの営業活動は、案件獲得ルートを整理するところから始めましょう。
ただし、やみくもに努力しても、時間ばかりが過ぎてしまい実際に仕事を得ることはできません。また、ポートフォリオをまとめる作業も必要です。
例えば、デザイナーの方が「明るくポップなデザインが得意です」と伝えても「明るくポップ」の印象は人によって異なります。
しかし、ポートフォリオがあればクライアントは、依頼した場合にどのようなアウトプットを貰うことができるか具体的に想像でき、依頼に繋がります。
フリーランス営業ロードマップ
副業としてフリーランスの案件を獲得するのか、専業の個人事業主としてフリーランスになるのかで獲得できる案件は異なりますが、いずれにせよ実績を積んでいくことは非常に重要です。
多くの案件をこなし、新しいクライアントに提示できる作品を増やしましょう。
具体的には、まず上図の「実績の積み方」にあるように、知り合いや個人での営業活動を通じて案件を獲得しましょう。
また、まずは正社員やアルバイトとして業界に入り、スキルを高めると同時に実績を作る方法もあります。ある程度の実績が生まれたら、「独立・仕事の取り方」を参考にしてください。
フリーランスの案件獲得のプロセス
フリーランスの案件獲得が、どのようなプロセスで進むか解説します。
案件獲得は直営業・直案件が理想
直案件で仕事が得られると、中抜きをされないため高い報酬を得やすくなります。また、間に人が入らずクライアントと直接やり取りができるので、「クライアントはどのような課題を抱えているのか」「どんなニーズを持っているのか」などをくみ取りやすくなります。
「フリーランスが直案件を獲得する営業手法。案件獲得のチャネルの種類や直営業までのステップを解説」にある通り、直接案件を獲得する方法は複数種類あります。
まずは実績となる場数を踏みポートフォリオの材料に
いくつかの案件をこなしたら、作品をポートフォリオの材料にしましょう。
クライアントからしても、口頭でスキルを説明されるより実際に何を作ったかを確認した方があなたの実力を判断しやすいです。
ポートフォリオには、記載するべき項目や制作にあたってのポイントなどがいくつかあるため、「フリーランスの仕事がくるポートフォリオの要点。記載する項目と守るべき権利の範囲を解説」を参考にまとめてみてください。
経験・実績を積むためにも案件マッチングサイトを活用する
駆け出しのフリーランスが案件を獲得するには、マッチングサイトが有効的です。
クライアントと直接やり取りができ、複数の企業に効率的にアプローチできます。また、間に運営が入っているので金銭トラブルを防げる点もメリットです。
「フリーランスの案件マッチングサービスの活用法。案件応募から年収を上げるための案件獲得戦略を解説」にもある通り、クラウドソーシング型やエージェント型などいくつかの種類があるので、まずは2~3個ほど登録してみましょう。
CHECK
・なるべく直営業での案件を獲得すると金銭的なメリットがある
・実績を積んだらポートフォリオにまとめる
・複数のマッチングサイトを使って案件を探すと効率的
駆け出しフリーランスはクラウドソーシング。経験者はエージェントから。
フリーランスとしてまだ実績がない方は、クラウドソーシングを使いましょう。あまり報酬額が高くないものの、未経験でも応募できる案件が多数あります。
経験者の方は、ぜひエージェントを活用してください。高いスキルや豊富なポートフォリオを求められますが、高単価の案件を見つけやすいです。
まずは、1年ほどクラウドソーシングメインで獲得し、少しずつエージェントを活用するとよいでしょう。
フリーランスの仕事が取れるポートフォリオの作り方
フリーランスとしてポートフォリオを作る時には、いくつかのポイントがあります。これから作る方は、以下の3つを抑えましょう。
ポートフォリオは商談相手に即した営業資料としてカスタマイズ
ポートフォリオは一つだけ作って使いまわすのではなく、クライアントに合わせてカスタマイズしましょう。
例えば、フォトグラファーの方が企業のWebサイトに掲載するための写真撮影の案件を獲得するため、個人用に撮影した写真をたくさん見せてもあまり意味がありません。
相手の求めているものとなるべく近い資料を提示してください。
スキルセットベースに何ができる人か汎用的な資料を用意する
ポートフォリオは毎回すべてカスタマイズして作るのではなく、汎用的な部分もあります。
例えば、エンジニアの方であれば、エンジニア歴はどのくらいか、どんな言語が使えるかといった部分はどのクライアント相手にも伝えなくてはなりません。そういった基本情報も、しっかりまとめておきましょう。
実績は定量的な情報として成果と期間を必ず盛り込む
ポートフォリオには、必ず定量的な成果を盛り込みましょう。
例えば、マーケターであれば、「SNS運用を始めて20代からの購入が30%増えた」「コンバージョンが3か月で40%増えた」といった数値が役立ちます。
他にも多数のポイントがあるので、説得力のあるポートフォリオを作るために「フリーランスの仕事がくるポートフォリオの要点。記載する項目と守るべき権利の範囲を解説」を参照してください。
CHECK
・ポートフォリオには汎用的な内容をベースにまとめる
・クライアントによってポートフォリオの内容をカスタマイズする
・定量的な数字を盛り込み説得力のあるポートフォリオにする
クライアントワークの実績の記載には許諾を必ず取る
クライアントワークの実績をポートフォリオとして掲載する場合、必ず許諾を取りましょう。勝手に使ってしまうと、契約違反になり賠償金を請求される可能性もあります。
口頭だけではなく、メールやチャットなどのテキストで許諾の証拠を残しておくとベストです。
フリーランスの最大の悩み。正しい価格設定の手法
フリーランスにとって、正しい価格設定は大きな課題です。適切な金額を受け取り、仕事を良いサイクルでまわしていきましょう。
理由のない値下げ・安売りは誰も幸せにならない
理由もなく値下げしても、仕事量と報酬が見合わなくなるだけです。
ライバルより価格優位性が持てて案件が取りやすくなるので一時的にはよいかもしれませんが、安売りは長く続きません。
相場をチェックし、著しく低い価格にするのはやめましょう。
必要な時間数×付加価値込みの時給単価から価格を設定する
まずは作業内容を確認して、どのくらいの時間がかかるのか明らかにしましょう。
その後、自分ならどんなスキルを活かしてどのような付加価値がつけられるのかを考えて時給を設定すると、時間×時給で価格を設定しやすくなります。
市場価格や案件額の平均値は参考程度で盲信しない
相場を知ることは大切ですが、盲信してはいけません。
相場はあくまで相場なので、その中で自分はどのくらいのバリューを発揮できるか考えてください。
正しい価格をつける方法としては、「フリーランスの適正価格の設定方法。正しい価格設定と交渉のポイントを解説」に詳細があります。値付けに困ったらぜひ参考にしてください。
CHECK
・理由なく安売りしても長期的にメリットがない
・納品までにかかる時間と自分の持っている付加価値から単価を設定する
・相場の確認は必要だが、こだわりすぎずに値付けする
初心者の方は、とにかく仕事を得るために時給数百円程度で請けがちですが、絶対にやめましょう。
そういった案件を得ても、フリーランスとして独立できるほどの稼ぎは得られません。そんなことをする時間があれば、スキルを磨いて適切な価格の案件を受けられる実力をつけてください。
付加価値の作り方は自分のポジションを明確にすること
付加価値をつけていくことは、フリーランスとして活躍する上で重要です。
例えば、人事の方が採用業務だけでなく、研修も担当できるようになれば、単価が上がります。
その中で「自分は採用と研修のどちらもできる」というポジションが確立することも、メリットの一つです。クライアントにとってどのようなポジションでいられるか、改めて考えてみましょう。
フリーランス営業ロードマップ
フリーランスの案件獲得チャンネル
フリーランスとして案件を獲得するには、いくつかのチャネルが活用できます。それぞれ、しっかり使い分けられるようにしましょう。
ビジネスマッチングサイトの活用は基本
ビジネスマッチングサイトには、クラウドソーシング型とエージェント型があります。
駆け出しの方はクラウドソーシング型がおすすめで、LancersやCrowdWorksなどに登録しましょうエージェント型はクロスデザイナーやレバテックフリーランスがおすすめです。
具体的な特徴については「フリーランスの案件マッチングサービスの活用法。案件応募から年収を上げるための案件獲得戦略を解説」をご覧ください。
フリーランスの情報発信にSNSを活用しきる
フリーランスはSNSを活用することで、ブランディングやDM経由の案件獲得といった成果につながります。
また、ポートフォリオを投稿することで自分の実績を多くの方に知ってもらえる点もメリットです。
一方で、注意点もあるので、しっかり準備を整えてから運用を始めましょう。「フリーランスのSNS運用。運用の目的を明確にした正しいSNSの使い方を解説」の記事をぜひ参考にしてください。
オフラインの交流会で仕事仲間から案件を獲得する
オフラインの交流会では、様々な職種のフリーランスと出会えます。
孤独になりがちな働き方をする中で仲間に出会えますし、業界の最新情報を知ることも可能です。新しい案件につながることもあるので、「フリーランスの交流会。情報収集や案件獲得に繋がる交流会の探し方や参加方法を解説」を読んでぜひ一度参加してみてください。
CHECK
・まずはビジネスマッチングサイトを使って案件を探す
・SNS経由で案件を獲得できることもある
・交流会ではフリーランス仲間や新しい案件との出会いがある
継続的な案件受注のために、スキル研鑽のためにセミナーを活用
フリーランス向けのセミナーは、案件獲得方法はもちろん、ポートフォリオの作り方やスキルの伸ばし方など様々なことを学べます。
特に、駆け出しの方は役に立つ情報が多いので、ぜひ参加してみましょう。本当に有益なセミナーを見つけてスキルアップなどにつなげるためにも、「フリーランスはセミナーに行くべき?セミナーを受講するメリット・講座の見極め方やおすすめ検索サイトを紹介」をご確認ください。
独立の成功を実感するタイミングとは?
何をもって独立が成功したとするかは人によりますが、月収は一つの基準となります。
家賃や光熱費など一か月にかかるお金をフリーランスの稼ぎだけで得られれば、最初の成功を果たしたと言えるでしょう。
また、「20代 男性 平均年収」など検索すると目安が出てくるので、その数値を上回ったときに次の成功を納めたと言えるかもしれません。その次は、年収1,000万円を超えた段階でもう一段上の成功をしたと判断できるでしょう。
また、自由な働き方ができると成功を実感できるものです。例えば、フルリモート案件だけを獲得すれば、国内・海外問わずどこにいても仕事をすることができます。実際に、ノマドワーカーとして海外を旅しながら働く方もいます。
働く時間も自由で、「早起きが苦手だけど、無理して起きなきゃ……」「深夜まで働かないと……」と無理する必要はありません。納期さえ守れば、何時に働くかは個人の裁量で決められます。自分の生活しやすいリズムで働けるかどうかも、独立が成功したかどうかを判断できる基準の一つとなるでしょう。
フリーランス営業ロードマップ
フリーランスとして案件を獲得するのは、簡単なことではありません。
特に、駆け出しのころはスキルも実績もなく、クライアントに営業しても上手くいかないことばかりです。
しかし、そこで諦めずにマッチングサイトなどを通じて案件をとり、実績をもとにポートフォリオを作ることで次の案件を獲りやすくなります。
SNSを使ったり交流会に出たりといった方法も含めて、様々な手段で仕事を探していきましょう。