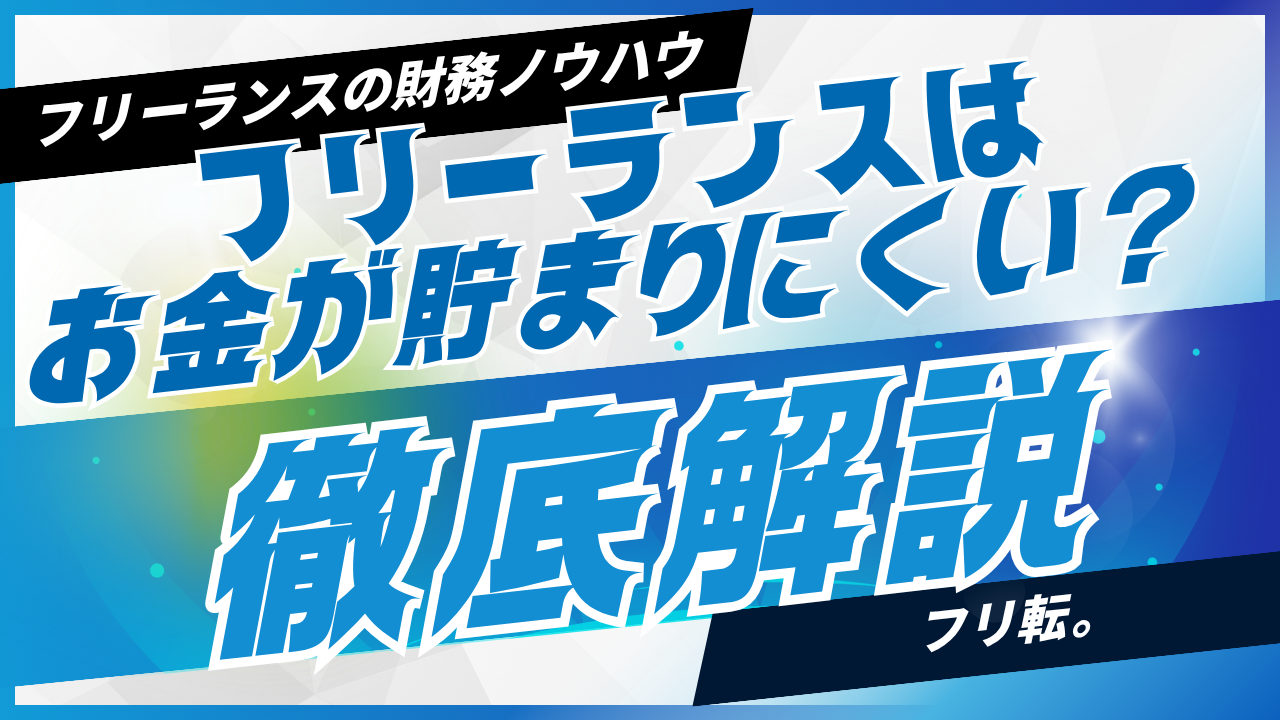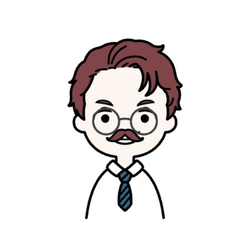フリーランスや自営業として独立したのに、「お金がたまらない」と悩んでいませんか。それは個人事業主特有の“構造的な落とし穴”が原因です。この記事では、最新データをもとにその実態を整理し、今日からできる改善のヒントをお届けします。
お金が貯まらないのには理由があります。数字を理解すれば、貯金も将来の安心も手に入れられます。まずは現状を把握し、そのうえで資金が貯まる仕組みをシステム化すれば、フリーランスであっても着実に貯蓄を増やすことが可能になります。
【データで見る現実】個人事業主の平均貯蓄額と「お金たまらない」実態
個人事業主の多くが抱えるのは、「稼いでいるはずなのにお金が残らない」という悩みです。まずは客観的なデータを見て「お金が貯まらないのは自分だけではない」と理解することから始めましょう。
個人事業主の平均貯蓄額は会社員の半分以下
ライフネット生命の調査では、フリーランスの平均貯金額は431万円という結果が出ています。
フリーランスや自営業者は、同じ年収でも会社員に比べて貯蓄が少ない傾向があります。
| 年収 | 会社員の貯蓄額 | フリーランスの貯蓄額 |
| 300万円台 | 120万円 | 50万円 |
| 500万円台 | 350万円 | 150万円 |
さらに、年収800万円以上でも貯蓄300万円未満の人が4割にのぼるという厳しい現実があります。このデータは、「収入が増えればお金も貯まる」という考えが必ずしも当てはまらないことを示しています。
「貯金ゼロ」個人事業主が全体の3割
ライフネット生命の調査では、フリーランスの約3割が貯金額ゼロと示されています。さらに驚くのは、年収1,000万円を超えていても貯金ゼロが15%存在するということです。コロナ禍では急な収入減で生活資金が枯渇する例も多く、フリーランスの資金基盤の脆弱さが浮き彫りになりました。
「売上100万でも手取り20万以下」になってしまう仕組み
「売上=収入」と思っていませんか?実際は、売上から経費・税金・社会保険料を差し引いた残りが、生活に使えるお金です。
例えば、売上100万円の場合、
- 経費:40万円
- 社会保険料:15万円
- 所得税・住民税:20万円
を差し引くと、手取りは約25万円にまで減少します。
この構造を正しく理解していないために、「稼いでいる感覚」と実際の手取りのギャップによる錯覚が生まれているのです。
CHECK
「収入が増えれば自然にお金が貯まる」という考えは間違い
貯金額ゼロのフリーランスが全体の3割を占めるという現実
売上から経費・税金・社会保険料を差し引いた残りが、生活に使えるお金
なぜお金が残らない?5つの根本原因を徹底診断
お金が貯まらない個人事業主には共通の行動パターンがあります。ここでは代表的な5つの根本的原因を取り上げますので、自分がどれに当てはまるかをチェックしてみましょう。
事業用と生活費の境界線が曖昧になっている
個人事業主が事業用資金と生活費のやり取りを帳簿上で正しく管理する概念として、「事業主貸」と「事業主借」があります。
- 事業主貸:事業から個人へお金を移す:例)事業用口座から生活費として引き出す
- 事業主借:個人のお金を事業に投入する: 例)個人の貯金を事業口座に入金する
事業用口座から生活費を無計画に引き出すと、資金の流れが見えなくなり、キャッシュフロー管理が難しくなる危険があります。そのため、「事業主貸」「事業主借」により事業と生活費を分けて管理することが重要です。
帳簿をつけず「どんぶり勘定」で収支が見えない
帳簿を付けずに収支をざっくり管理していると、月末時点での収支がプラスかマイナスかすら把握できない状態になり、資金繰りのリスクが高まります。
そこで、レシートや領収書は溜め込まず、都度記録・処理することが大切です。この習慣をつけることで、経費の計上漏れを防ぎ、「本来払わなくていい税金」を余計に払うことも防ぐことができます。
売掛金の回収が遅れて慢性的なキャッシュ不足
帳簿上は黒字でも、取引先からの入金が遅れれば現金が手元にない「黒字倒産予備軍」の状態になります。
このリスクを防ぐには、キャッシュ不足を予測し、安定的に資金を回すサイクルを作ることが重要です。具体的には、取引先との支払条件を定期的に見直す、キャッシュフローを優先して管理するといった意識が欠かせません。
税金の知識不足で必要以上に納税している
フリーランスにとって、税金の知識は手取りを大きく左右する重要な要素です。
例えば、青色申告なら65万円、白色申告は10万円といった控除額の差があるため、青色申告をするほうがメリットが大きいです。さらに、小規模企業共済やiDeCoなどの節税制度を活用することで、将来の資産形成と同時に手取りを増やすことが可能です。
また、予定納税(所得税が一定額以上になる見込みの人が税金を前払いする仕組み)を上手に活用すると、年末の資金ショートを防ぎ、計画的な資金管理にも役立ちます。
将来への備えが全くできていない悪循環
日々の資金繰りで精一杯だと、ライフステージの変化や老後の生活資金など、将来の備えができない状態に陥りがちです。フリーランスには会社員のような保障がないため、早い段階から長期的な視点で資金対策を行うことが必要です。
また、将来のための貯蓄だけでなく、緊急時に対応できる資金の準備も同時に行うことで、予期せぬ支出にも落ち着いて対応できる安定した資金基盤を作ることができます。
CHECK
・事業用資金と生活費はきちんと線引きをすること
・キャッシュフローを細かく把握すること
・フリーランスにとって税金の知識は必要不可欠
今すぐできる!お金の流れを見える化する3ステップ
根本原因が分かったら、次は改善行動にうつりましょう。複雑に考えず、まずはシンプルな3ステップでお金の流れを整理することから始めると良いでしょう。
【STEP1】事業用口座とカードを今すぐ分離する
事業と私生活のお金を分けることは、資金管理の第一歩です。事業用口座を開設すれば、生活費と経費を明確に分けられます。開業届と本人確認書類を用意し、銀行窓口やオンラインで申し込みましょう。
さらに、事業に関わる支払いは事業用クレジットカードで行うのが基本です。カード明細がすべて事業経費として記録されるため、確定申告が楽になり、経費の使用状況もシンプルに把握できます。事業用クレジットカードを選ぶ際は、年会費、ポイント還元率、経費管理機能や経費精算アプリとの連携などを考慮します。
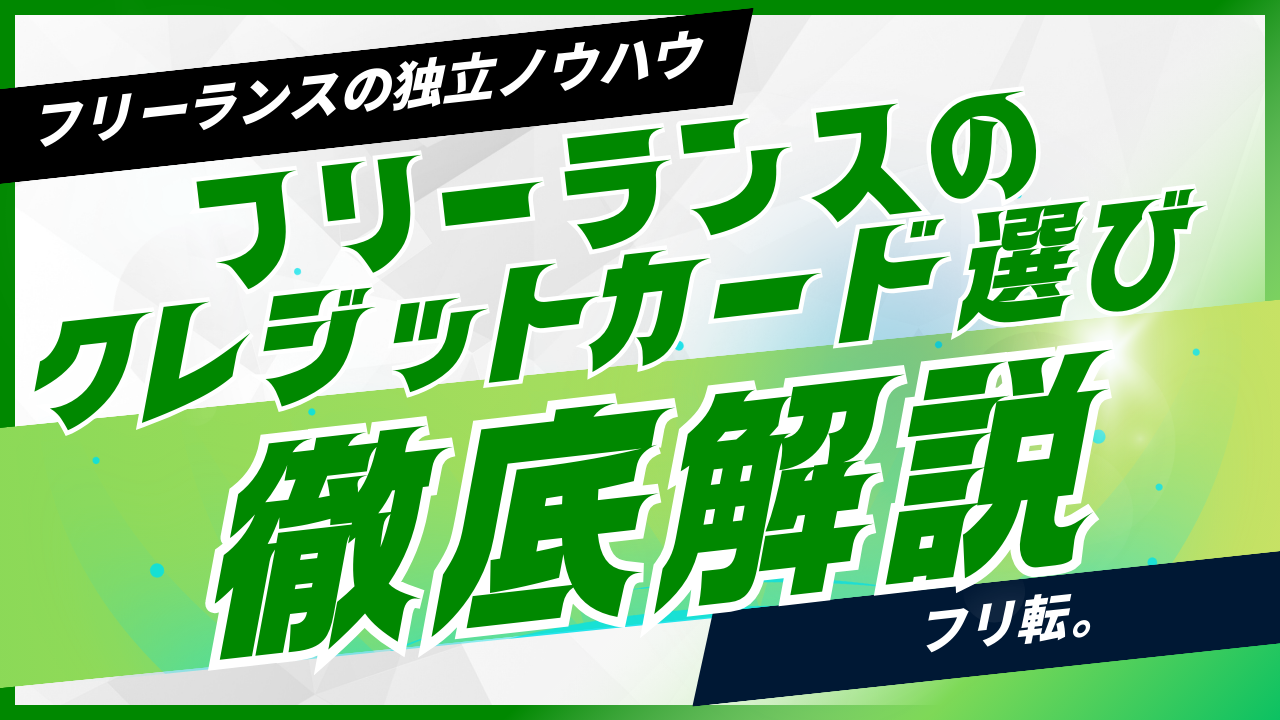
【STEP2】「フリーランス給与制」で生活費を定額化
毎月一定額を生活費として事業口座から移すことで資金管理の安定化に大きく役立ちます。
具体的には、生活費専用の口座を用意し、毎月初めに一定金額を「事業主貸」として移動させます。
- 生活費の目安:売上の20~30%
- 残りの資金:事業投資・税金準備・貯蓄に振り分ける
この仕組みを作ることで、収入の増減に左右されず、安定的に生活費を確保しながら、事業運営や将来の資金対策も計画的に行えます。
月1回15分の「お金の健康診断」を習慣化
毎月末に通帳を用意し「月末残高から月初残高を引く」ことで、その月のキャッシュの増減額が簡単にわかります。さらに、資金が増えた・減った理由をきちんと洗い出しておくと良いでしょう。
会計アプリを活用すれば売上や経費の入力もスムーズになり、数分でキャッシュフローの状況を確認できます。この習慣を継続することで資金管理の意識が高まります。
CHECK
事業用口座とカードを今すぐ分離する
「フリーランス給与制」で生活費を定額化
毎月の「お金の健康診断」を習慣化
将来の安心を作る!個人事業主の賢い資産形成術
次は将来への備えとして、長期的な資産形成に移りましょう。税制優遇を受けながら資産形成できる制度を最大限活用することが重要です。
小規模企業共済で「個人事業主の退職金」を準備
小規模企業共済は個人事業主向けの経営者退職金制度です。
月額1,000円~70,000円で掛金を自由に設定でき、年間最大84万円まで所得控除の対象となるため節税効果があります。廃業や退職時には共済金を受け取ることができ、退職所得控除も適用されます。
さらに、契約者貸付制度を利用すれば緊急時の資金調達も可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後資金を税優遇で積立
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、公的年金に上乗せして老後資金を準備する私的年金制度です。加入者は自分で掛金を拠出し、預金や投資信託などで運用し、原則60歳以降に年金または一時金で受け取ります。
個人事業主は月額68,000円(年額81.6万円)まで拠出でき、その全額が所得控除の対象となるため節税効果が大きく、運用益も非課税です。受取時には退職所得控除や公的年金等控除も活用でき、効率的に老後資金を積み立てられます。
新NISAで流動性を保ちながら資産運用
新NISAは2024年に始まった制度で、旧NISAより非課税投資枠が拡大され、保有期間は無期限、制度も恒久化されています。年間360万円、生涯1,800万円までの非課税投資枠を活用でき、効率的に資産形成が可能です。
つみたて投資枠と成長投資枠を使い分け、自分の運用スタイルに合った商品を選ぶことで、流動性を保ちながら長期的に資産を増やすことができます。
CHECK
長期的な資産形成のためには税制優遇を活用すること
小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用
新NISAも使って賢く資産運用する
個人事業主が「お金が貯まらない」状況から脱出するには、事業用口座と生活費口座を分け、収支を定期的に確認し、節税や資産形成を計画的に取り入れる―この3つを実行することから始めましょう。無理のない範囲で着実に「平均以上」を目指していきましょう。