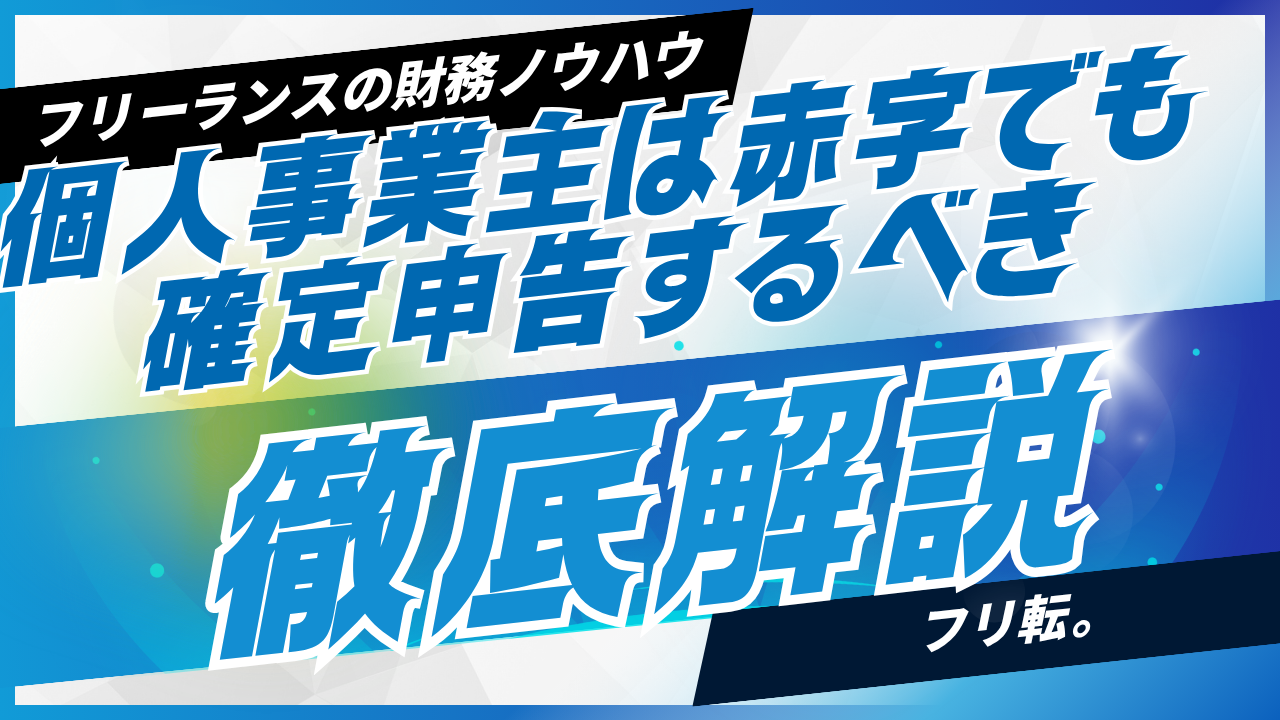赤字でも個人事業主は確定申告すべきです。理由は3つあります。
1. 損失繰越控除:青色申告なら赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺可能
2. 源泉徴収税の還付:すでに天引きされた税金が戻ってくる
3. 保険料・住民税の軽減:翌年度の国保料や住民税が大幅に下がる
この記事は、収入より経費が多く赤字になった個人事業主が確定申告をすべき理由を解説します。青色申告による損失繰越控除や、経費計上・家事按分の正しい判断基準までわかります。
個人事業主が赤字になる3つのパターン
赤字が発生する典型的なパターンと申告の必要性を整理します。開業初期の特性と申告義務の関係を明確にし、リスクを回避する判断基準を示します。
ここでは、開業初期や設備投資の影響で赤字になりやすい状況を踏まえ、申告が必要となる代表的なケースと、申告を怠った場合に生じるリスクを順に解説します。
開業初年度や設備投資年度は赤字になりやすい
開業1〜3年目の個人事業主やフリーランスが赤字になるのは決して珍しいことではありません。事業を軌道に乗せるための初期投資として、パソコンやソフトウェア、広告宣伝費などの経費がかさむ一方、まだ安定した収入が得られていない時期だからです。
ただし、設備投資による赤字を考える際には、減価償却のルールを理解しておく必要があります。
資産の経費計上ルール
| 購入金額 | 処理方法 | 備考 |
| 10万円未満 | 全額即時経費計上可能 | すべての事業者 |
| 10万円以上30万円未満 | 減価償却が原則 | 青色申告者は即時償却特例あり |
| 30万円以上 | 減価償却必須 | 耐用年数で分割 |
計算例:青色申告の即時償却特例を使う場合
- 年間売上:200万円
- 通常経費:150万円
- パソコン購入:20万円(即時償却特例で全額経費化)
- 合計経費:170万円
- 事業所得:30万円の黒字
CHECK
ポイント:青色申告者なら30万円未満の資産は全額その年の経費にできる
一方、100万円の車両を購入した場合は減価償却により数年に分けて経費化するため、当年の経費計上額は一部のみとなります。このように、設備投資の内容と税務上の処理方法によって、実際の赤字額は変わってきます。
赤字でも確定申告が必要な3つのケース
赤字の場合でも確定申告が必要、または強く推奨されるケースがあります。
赤字でも確定申告すべき3つのケース
- 青色申告者 – 損失を最大3年間繰越可能 – 申告しないと節税機会を完全に喪失
- 源泉徴収されている – 報酬から天引きされた税金(10.21%)が還付される – 例)源泉徴収80万円+赤字+他の所得なし → 80万円全額還付
- 国保料・住民税を下げたい – 所得ゼロまたはマイナスの証明により翌年度の負担軽減 – 所得300万円と赤字では保険料に20〜40万円の差
申告しない場合のリスクと機会損失
赤字だからといって確定申告をしないと、複数のデメリットが生じます。
最大のリスクは、青色申告の純損失繰越制度が使えなくなることです。今年の赤字50万円を申告しておけば、翌年黒字100万円になった時に相殺でき、課税所得を50万円に抑えられます。しかし申告しなければこの恩恵は一切受けられません。
また、源泉徴収された税金の還付も受けられません。年間数十万円の源泉徴収税額がある場合、これは大きな損失となります。
さらに、融資を受ける際や補助金申請時に必要となる確定申告書の控えがないため、事業の信用性を証明できず、資金調達の機会を逃す可能性もあります。
青色申告の純損失繰越制度を最大限活用する方法
青色申告の「純損失繰越制度」は、赤字の年にこそ活用価値が高い制度です。損失を翌年以降の黒字と相殺できるため、長期的に見れば大きな節税効果が期待できます。
ここでは、制度の基本的な仕組みから控除を受けるための要件、そして赤字年度に行う申告書の作成手順までをわかりやすく解説します。
純損失繰越控除とは?3年間赤字を持ち越せる制度
純損失繰越控除とは、赤字を「貯金」して将来の黒字と相殺できる青色申告者限定の制度です。
わかりやすい例
今年100万円の赤字 → その赤字を「預けて」おける
翌年150万円の黒字 → 預けていた赤字100万円を引く → 課税対象は50万円だけ
具体的な計算例で見てみましょう。令和5年に50万円の赤字、令和6年に100万円の黒字、令和7年に80万円の黒字だった場合を想定します。
令和5年の赤字50万円を申告しておけば、令和6年の黒字100万円から50万円を差し引き、課税所得は50万円となります。この50万円に対してのみ税金がかかるため、所得税、住民税、国民健康保険料すべてが大幅に軽減されます。
この制度により、事業の初期段階で発生した赤字を後の黒字期間で回収でき、トータルの税負担を最小化できます。
65万円控除を受けるための青色申告の要件
純損失繰越を活用するには青色申告が必須ですが、さらに最大65万円の青色申告特別控除を受けるには3つの条件を満たす必要があります。
一つ目は、複式簿記による記帳です。現在は会計ソフト(やよいの青色申告オンライン、freee、マネーフォワードなど)を使えば、簿記の知識がなくても取引を入力するだけで自動的に複式簿記に対応した帳簿が作成されます。
二つ目は、貸借対照表と損益計算書の提出です。これも会計ソフトを使えば、日々の取引入力から自動的に作成されるため、特別な知識は不要です。
三つ目は、e-Tax(電子申告)による提出です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から申告できます。e-Taxを使わず書面提出の場合、控除額は最大55万円に減額されるため、10万円分の節税効果の差が生まれます。
赤字年度の正しい申告書作成手順
赤字年度の青色申告書作成には、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、売上と経費の集計を正確に行います。売上については、12月末締めで翌年1月入金の請求も当年の売上として計上する必要があります。お金を受け取った日ではなく、仕事を完了して請求した日が基準となるため、計上漏れに注意が必要です。
経費についても同様で、12月に発生した経費は翌年1月払いであっても当年の経費として計上します。ただし、クレジットカード払いの場合は、カード決済日ではなく実際に商品やサービスを受け取った日が基準となります。
会計ソフトに1年分の取引を入力し終えたら、青色申告決算書の「所得金額」欄がマイナス(赤字)になっていることを確認します。このマイナスの金額が「純損失」として翌年以降に繰り越されます。
確定申告書の第四表(損失申告用)にも、繰り越す損失額を記載する必要があります。この手続きを正しく行うことで、翌年以降の申告時に繰越損失を適用できるようになります。
経費計上の正しい判断基準と家事按分のルール
経費として認められるかどうかの判断は、個人事業主にとってもっとも悩ましいポイントの一つです。特に自宅兼事務所のように、私的利用と事業利用が混在する場合は、家事按分の考え方や計算方法を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、経費の判断基準から勘定科目の選び方、家事按分や減価償却の実務的な扱いまで、税務調査で指摘を受けないためのポイントを整理します。
経費になるかならないかの判断基準
「これは経費にできますか?」という質問は非常に多いですが、判断基準はシンプルです。売上に貢献するかどうか、つまり事業に必要な支出かどうかが唯一の基準となります。
たとえばカフェ代を考えてみましょう。クライアントとの打ち合わせや、自分一人で作業をするために利用したカフェ代は会議費または雑費として経費計上できます。しかし、プライベートで友人と会った際のカフェ代は経費になりません。
同じカフェ代でも、その支出の目的によって経費になるかどうかが変わります。
重要なのは、その支出が事業のために必要だったことを客観的に説明できるかどうかです。領収書やレシートに「誰と」「何のために」使ったかをメモしておくと、後で説明する際にも税務調査の際にも安心です。
勘定科目の選び方に悩む必要はない理由
経費計上でもう一つよく聞かれるのが「この支出は何費にすればいいですか?」という勘定科目の質問です。
実は、勘定科目の選択は所得や税額に影響しません。先ほどのカフェ代を「会議費」にしても「交際費」にしても「雑費」にしても、経費であることに変わりはないため、計算される所得税は同じです。
会計ソフトには勘定科目ごとに説明書きがあるため、それを参考に判断すれば問題ありません。重要なのは、一度決めた科目は継続して使うことです。同じような支出を毎回違う科目で処理すると、帳簿が見づらくなり、経営分析もしにくくなります。
ただし、経費のカテゴリーではない科目(資産や負債の科目)を誤って選ぶと所得計算に影響するため、その点だけは注意が必要です。
自宅兼事務所の家事按分の具体的計算方法
自宅を事務所としても使っている場合、家賃や光熱費などの一部を経費として計上できます。これを「家事按分」といいます。
家賃の按分には面積基準を使います。たとえば、全体が100平米の賃貸住宅で、そのうち30平米を事務所専用スペースとして使っている場合、家賃の30%を経費計上できます。月額家賃10万円であれば、月3万円、年間36万円が経費となります。
電気代の按分にはコンセント数や使用時間を基準にします。全体のコンセント数のうち事業用機器で使用している割合や、1日の使用時間のうち仕事をしている時間の割合で計算します。
通信費(インターネット代、スマートフォン代)も使用時間や使用頻度で按分します。1日8時間仕事で使い、残り16時間はプライベートなら、約30〜40%程度を事業用として按分するのが妥当でしょう。
車両関係費用は走行距離で按分します。年間走行距離10,000kmのうち、事業用が3,000kmなら30%を経費計上できます。
重要なのは、按分比率を合理的に説明できる根拠を持っておくことです。極端に高い按分比率(90%以上など)は税務調査で指摘される可能性があるため、実態に即した割合を設定しましょう。
10万円以上の資産と減価償却の扱い
10万円以上の資産を購入した場合、その年に一括で経費計上するのではなく、使用できる期間(耐用年数)で分割して経費化します。これを「減価償却」といいます。
ただし、青色申告者には特例があります。30万円未満の資産であれば、購入した年に全額を経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が適用されます。
たとえば、15万円のノートパソコンを購入した場合、青色申告者なら即時償却を選択でき、購入年度に15万円全額を経費にできます。白色申告や30万円以上の資産の場合は、パソコンの耐用年数4年で分割して経費化する必要があります。
会計ソフトでは、固定資産登録画面で「即時償却」を選択するだけで自動的に処理されるため、複雑な計算は不要です。ただし、この特例には年間合計300万円までという上限があるため、高額な資産を複数購入する場合は注意が必要です。
赤字が国民健康保険料、住民税、事業税に与える影響
赤字申告は「損を出しただけの手続き」と思われがちですが、実は翌年以降の税金や保険料の負担に直結する重要な要素です。
特に国民健康保険料や住民税、個人事業税は所得額を基準に計算されるため、赤字申告によってこれらの負担を軽減できる場合があります。
ここでは、それぞれの制度における具体的な影響と、どの程度の軽減効果が期待できるのかを整理します。
国民健康保険料の算定基準と赤字申告の効果
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されます。所得が低ければ保険料も安くなるため、赤字申告により大きな軽減効果が得られます。
国保料の計算式は自治体によって異なりますが、基本的に「所得割」と「均等割」の合計です。所得割は前年の所得に一定率(7〜10%程度)を乗じて計算されるため、所得がゼロまたは赤字であれば所得割はゼロになります。
国民健康保険料の比較例(東京都の場合):
| 前年所得 | 所得割 | 均等割 | 合計 |
| 300万円 | 約27万円 | 約5万円 | 約32万円 |
| 赤字 | 0円 | 5万円(7割軽減で1.5万円) | 約1.5万円 |
| 差額:約30万円の軽減効果 | |||
さらに、所得が一定額以下の場合、均等割部分も7割、5割、2割の軽減措置が適用されます。赤字申告により、この軽減措置の対象となり、最小限の保険料負担で済みます。
住民税の非課税判定と翌年度への影響
住民税も前年の所得をもとに計算されますが、一定の所得以下であれば非課税となります。
住民税の非課税ラインは、多くの自治体で単身者の場合、合計所得金額45万円以下(給与収入のみの場合は100万円以下)です。ただし、生活保護基準の級地制度により、自治体によって基準額が異なる場合があります(35万円、38万円、42万円、45万円など)。
扶養家族がいる場合は、基準がさらに高くなります。赤字申告をすれば確実に非課税ラインを下回るため、翌年度の住民税はゼロになります。
住民税は所得割(所得の約10%)と均等割(年間5,000円程度)の合計ですが、非課税になればこれらが全額免除されます。たとえば所得300万円なら年間約30万円の住民税が発生しますが、赤字申告をすれば翌年度はゼロになります。
確定申告により、税務署から自治体へ自動的に所得情報が共有されます。別途住民税の申告をする必要はなく、自治体が自動的に非課税判定を行い、6月頃に「住民税非課税決定通知書」が送られてきます。
個人事業税の課税要件と赤字時の扱い
個人事業税は、すべての個人事業主が支払う税金ではありません。課税されるのは「事業所得が290万円を超えた場合」であり、それ以下であれば事業税は発生しません。
個人事業税の計算では、青色申告特別控除は適用されません。事業所得から事業主控除290万円のみを差し引いて計算されます。
たとえば、青色申告特別控除前の事業所得が300万円の場合、300万円−290万円=10万円が課税対象となり、10万円×5%=5,000円の事業税が発生します。
赤字の年は当然290万円の控除額を下回るため、事業税はゼロになります。
事業税の税率は業種によって3〜5%で、多くのフリーランスは5%が適用されます。計算式は「(事業所得−290万円)×5%」となるため、所得が290万円以下なら自動的にゼロです。
住民税と同様、確定申告をすれば都道府県税事務所が自動的に事業税を計算し、8月頃に納税通知書が送られてきます(課税対象の場合のみ)。納付は通常、第1期(8月末期限)と第2期(11月末期限)の2回に分けて行います。
赤字年度は通知自体が来ないか、税額ゼロの通知が届きます。
赤字申告する際の注意点とよくある間違い
赤字申告は節税につながる一方で、手続きや経費計上を誤ると税務調査で不備を指摘されるリスクもあります。特に経費の根拠不足や計上時期のズレ、消費税処理の誤りはよく見られるミスです。
ここでは、赤字申告時に注意すべきポイントと、実務で見落とされがちな間違いを具体的に整理します。
架空経費や過剰な家事按分のリスク
赤字を大きくして節税効果を高めようとして、実際には事業に使っていない支出を経費計上したり、家事按分の割合を不当に高く設定したりすることは絶対に避けるべきです。
税務調査が入った場合、領収書やレシート、通帳の記録、クレジットカードの明細などから支出の実態が詳しく調べられます。事業と無関係な支出が経費に含まれていることが判明すれば、修正申告を求められ、追加の税金に加えて延滞税や加算税が課されます。
特に家事按分は税務調査でよく指摘される項目です。自宅兼事務所で家賃の80〜90%を経費計上しているケースなどは、実態との乖離を疑われやすくなります。
按分比率は常識的な範囲内に抑え、その根拠を明確に説明できるようにしておきましょう。
ATTENTION
不正が悪質と判断された場合、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。そうなれば純損失繰越などの特典も失われ、長期的に大きな不利益を被ることになります。
消費税のインボイス対応と仕入税額控除
2023年10月からインボイス制度が始まり、消費税の課税事業者となった個人事業主も増えています。赤字の場合でも消費税申告が必要なケースがあるため注意が必要です。
赤字でも消費税は別計算
重要:所得税の赤字と消費税の納税は別物です。
計算例:
– 売上200万円(税込220万円、消費税20万円)
– 経費250万円(税込275万円、消費税25万円)
➡ 所得税:50万円の赤字
➡ 消費税:5万円の還付(20万円 − 25万円)
注意:インボイス登録している課税事業者は赤字でも消費税申告が必要
ただし、経費として計上した支出の中に、インボイス(適格請求書)が発行されていない取引が含まれている場合、その部分の消費税は控除できません。令和8年9月30日までは80%の経過措置がありますが、徐々に控除割合は減少していきます。
なお、2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能です(少額特例)。この特例期間終了後は、原則としてインボイスの保存が必要となります。
インボイス登録した小規模事業者向け:2割特例
適用期間:2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間
2割特例とは:
売上の消費税額 × 20% = 納税額(簡易計算)
メリット
- 仕入れ・経費の消費税を計算不要
- インボイスの保存も不要(事務負担大幅軽減)
- 多くの小規模事業者にとって最も有利
対象者:インボイス制度開始を機に課税事業者になった人
これは、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする簡便な計算方法で、簡易課税や原則課税よりも有利になるケースが多くあります。
2割特例を適用すれば、仕入れや経費の消費税を細かく計算する必要がなく、売上の消費税額に0.2を乗じるだけで納税額が算出できます。インボイス登録したばかりの小規模事業者にとって、事務負担が大幅に軽減される制度です。
簡易課税制度を選択している場合は、売上高だけで消費税額が計算されるため、実際の経費や仕入の金額は消費税計算に影響しません。多くのフリーランスにとっては簡易課税や2割特例の方が有利なケースが多いため、制度の選択は慎重に行いましょう。
売掛金と買掛金の計上タイミング
赤字申告で特に注意が必要なのが、売掛金と買掛金の計上タイミングです。お金の入出金日ではなく、取引が確定した日(権利確定主義)で計上する必要があります。
発生主義:お金の動きではなく「取引の確定」が基準
NG例:入金ベースで計上 – 12月請求 → 1月入金 → 1月の売上として計上
OK例:発生ベースで計上 – 12月請求 → 1月入金 → 12月の売上として計上
覚え方:「請求書を発行した月」が売上の月
翌年の申告で修正することになり、純損失繰越の計算も複雑になります。
経費についても同様で、12月に商品を受け取ったが支払いは翌年1月というケースでは、12月の経費として計上します。ただし、クレジットカード払いの場合、カード会社への支払日ではなく、実際に商品やサービスを受け取った日が基準となります。
会計ソフトを使って日々取引を入力していれば、自動的に正しい日付で記帳されますが、12月分の請求書や領収書を後回しにして翌年1月に入力すると、誤った期間に計上してしまう可能性があります。
年末は特に注意して、12月31日までの取引はすべて当年に計上しましょう。
帳簿と通帳残高の一致確認が必須
青色申告で最も重要なチェックポイントの一つが、会計ソフト上の預金残高と実際の通帳残高が一致しているかどうかの確認です。
事業用口座の取引を会計ソフトに入力していく際、入金と出金を一つずつ正確に記録していれば、12月31日時点の帳簿残高と通帳残高は必ず一致します。もし一致していない場合、どこかに入力漏れ、二重計上、金額間違いなどのエラーがあることを意味します。
会計ソフトのメニューには通常「残高照合」や「口座残高確認」といった機能があり、帳簿残高と実際の残高を比較できます。不一致がある場合は、通帳を最初から見直して、入力漏れがないか、金額や日付に誤りがないかを確認する必要があります。
プライベートと兼用の口座を使っている場合も、事業関連の入出金はすべて記帳し、プライベートの入出金は「事業主貸」「事業主借」で処理します。この処理を正しく行えば、帳簿残高と通帳残高は必ず一致するはずです。
残高不一致を放置したまま申告すると、貸借対照表に誤りが生じ、青色申告特別控除65万円が認められない可能性もあります。必ず残高一致を確認してから申告しましょう。
会計ソフトを使った効率的な帳簿作成と申告手順
会計ソフトを上手に使えば、帳簿作成から申告までの作業を大幅に効率化できます。自動仕訳やデータ連携を活用することで、入力ミスを防ぎながら時間も節約できます。
ここでは、目的に合ったソフトの選び方から入力の基本、e-Taxを使った申告手順、納税までの流れを具体的に紹介します。
おすすめ会計ソフトと自動化機能の活用
青色申告を効率的に行うには、会計ソフトの活用が必須です。代表的なソフトとして、やよいの青色申告オンライン、freee、マネーフォワードクラウド確定申告などがあり、いずれも初年度無料または低価格で利用できます。
これらのソフトには「スマート取引取込」や「自動仕訳」といった機能があり、銀行口座やクレジットカード、請求書発行システム(Misoca、マネーフォワード請求書など)と連携できます。一度連携設定をすれば、取引データが自動的に会計ソフトに取り込まれ、仕訳も自動生成されます。
たとえば、事業用のネットバンク口座と会計ソフトを連携させておけば、売上の入金や経費の支払いが自動的に取り込まれます。
最初に数件の仕訳を手動で設定すれば、ソフトがパターンを学習し、以降は同様の取引を自動で仕訳してくれます。
手入力の時間を大幅に削減できるため、日々の記帳作業のハードルが下がり、リアルタイムで経営状況を把握できるようになります。特に取引件数が多い事業者には、自動化機能の活用を強くおすすめします。
売上、経費、預金入力の4つの基本パターン
会計ソフトでの入力は、以下のように大きく分けて4つのパターンに分類できます。このパターンを理解すれば、ほとんどの取引を迷わず処理できます。
| パターン | 内容 | 主な処理方法 | 補足 |
| ①売上代金の入金 | 請求書を発行し、後日入金される取引 | 請求時に「売掛金」を計上し、入金時に「売掛金の回収」として処理。例:12月末の請求は当年の売上、翌年1月の入金は回収。 | 売上計上のタイミングに注意。 |
| ②経費の支払い | 通信費・広告費・消耗品費などを支払う取引 | 預金口座やカードから支払った場合、該当科目で計上。カード払いは利用日を経費計上し、引き落とし時に「未払金の支払い」で処理。 | 経費計上日は「支出日」ではなく「利用日」。 |
| ③事業と関係のない入金 | 資金移動や還付金、預金利息など | 「事業主借」で処理(事業の収益とは無関係な入金)。 | プライベート資金の入金もここに含む。 |
| ④事業と関係のない支出 | 生活費、社会保険料、所得税など | 「事業主貸」で処理(経費にならない支出)。 | 家計用口座との出金時によく発生。 |
プライベート兼用の口座では、パターン③と④の「事業主借」「事業主貸」を頻繁に使うことになります。これらを正しく処理すれば、事業の実態を正確に把握できます。
e-Tax申告の具体的な手順とメリット
e-Tax(電子申告)を利用すれば、税務署に行かずに自宅から申告できるだけでなく、青色申告特別控除が最大65万円になります(書面提出は最大55万円)。
e-Taxに必要なものは、マイナンバーカード、スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応)、パソコン、利用者識別番号です。初回のみe-Taxの利用開始手続きが必要ですが、会計ソフトの案内に従えば簡単に設定できます。
申告手順は次のとおりです。
まず、会計ソフトで1年分の取引入力を完了させ、固定資産や所得控除の情報も入力します。次に「確定申告書作成」メニューから、指示に従って必要事項を入力していきます。
申告書のプレビューで内容を最終確認したら、「e-Taxで提出」ボタンをクリックします。マイナンバーカードをスマートフォンで読み取り、暗証番号を入力すれば送信完了です。通常5〜10分程度で手続きが終わります。
送信後は、e-Taxのメッセージボックスで受付結果を確認できます。社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書などの添付書類は、e-Taxの場合、提出省略できるため保管しておけば大丈夫です。
納税方法の選択と注意点
確定申告で納税額が発生する場合(前年が黒字で今年が赤字でも、源泉徴収税額が少なければ納税が発生する可能性があります)、納税方法は複数あります。
最もおすすめなのが「ダイレクト納付」です。e-Taxのメッセージボックスから手続きでき、指定した預金口座から自動引き落としされます。事前に税務署へのダイレクト納付利用届出が必要ですが、一度届け出れば以降の年も使えます。
次に便利なのが「インターネットバンキング納付」で、ペイジー対応の金融機関であればすぐに利用できます。e-Taxのメッセージボックスに記載されている納付区分番号を使って、ネットバンキングから納付します。
コンビニ納付は税額が30万円以下の場合に利用でき、e-Taxでバーコード付き納付書を発行してコンビニで支払います。
従来型の納付書を使った窓口納付も可能ですが、金融機関や税務署に行く手間がかかるため、できる限りオンライン納付を活用しましょう。
納付期限は確定申告期限と同じ3月15日です。期限を過ぎると延滞税が発生するため、確実に期限内に納付してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.赤字でも青色申告承認申請書は提出できますか?
はい、可能です。青色申告承認申請書は開業日から2か月以内、または青色申告を始めたい年の3月15日までに提出すれば、その年から青色申告できます。
赤字が予想される場合こそ、純損失繰越制度を活用するために青色申告を選択すべきです。
Q2.3年間の繰越期間を過ぎた損失はどうなりますか?
3年を過ぎた損失は消滅し、それ以降の黒字と相殺することはできません。たとえば令和5年の赤字は令和8年まで繰り越せますが、令和9年には使えなくなります。
繰越期間内に黒字化し、損失を有効活用することが重要です。
Q3.プライベート兼用の支出は全額経費にできませんか?
できません。自宅兼事務所の家賃、光熱費、通信費などは、事業で使用している割合のみを経費計上できます。この割合を「家事按分」といい、面積、時間、距離などの合理的な基準で計算する必要があります。
全額を経費にすると税務調査で否認される可能性が高くなります。
Q4.源泉徴収された税金は赤字でも還付されますか?
基本的に還付されます。 ただし条件によります。
全額還付されるケース
- 事業所得が赤字orゼロ
- 他の所得なし
- 所得控除後の課税所得がゼロ
一部還付されるケース
- 他の所得があり、赤字と相殺後も課税所得が残る場合
- 源泉徴収額 − 実際の税額 = 還付額
例:源泉80万円、赤字100万円、他の所得なし → 80万円全額還付
Q5.開業初年度で年の途中から事業を始めた場合の申告はどうなりますか?
開業日から12月31日までの期間で申告します。たとえば10月1日開業なら、10月から12月までの3か月分の売上と経費を集計して申告します。
開業日以前の支出は原則として経費にできませんが、開業準備費用として一部認められる場合もあります。
まとめ:赤字申告で得られる3つのメリット
| メリット | 効果 | 条件 |
| ① 損失繰越 | 最大3年間、赤字を黒字と相殺 | 青色申告必須 |
| ② 税金還付 | 源泉徴収税が戻る | 確定申告必須 |
| ③ 保険料軽減 | 国保料・住民税が大幅減 | 確定申告必須 |
今すぐやるべきこと
- 青色申告承認申請書を提出(期限厳守)
- 会計ソフトを導入して記帳開始
- 領収書・レシートを必ず保管
赤字の年でも確定申告は必ず行うべきです。特に青色申告による純損失の繰越控除は、最大3年間の損失を翌年以降の黒字と相殺でき、長期的な節税効果が非常に大きくなります。
赤字申告により、翌年度の国民健康保険料や住民税の負担も軽減され、源泉徴収された税金の還付も受けられます。ただし、架空経費の計上や過剰な家事按分は絶対に避け、実態に即した正確な申告を心がけましょう。
今日から実践できる4つのアクション
- 青色申告承認申請書の提出
開業日から2か月以内、または青色申告を始めたい年の3月15日までに提出。 - 会計ソフトの導入と自動連携設定
やよいの青色申告オンライン、freee、マネーフォワードのいずれかを選択し、銀行口座と連携。 - 10万円以上の設備投資の記録
購入した資産の金額と日付を記録し、30万円未満なら即時償却を選択。 - 12月31日までの取引を漏れなく計上
12月末締めの請求書、12月購入の経費をすべて当年に計上。
会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても青色申告の要件を満たす帳簿を作成でき、e-Taxで自宅から申告を完了できます。10万円以上の設備投資は減価償却のルールを理解し、青色申告の30万円未満特例を活用しましょう。
個人事業税の計算では青色申告特別控除が適用されない点にも注意が必要です。今年の赤字を将来の節税に変えるため、今日から正しい記帳と申告準備を始めましょう。
出典・参照元
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「青色申告特別控除」
- 国税庁「純損失の繰越控除」
- 国税庁「家事関連費の必要経費算入」
- 国税庁「減価償却資産の償却方法の届出」
- 国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
- 国税庁「消費税の2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
- 総務省「個人住民税の非課税限度額」
- 各都道府県税事務所「個人事業税のあらまし」
- 各自治体「国民健康保険料の算定方法」
※記事内容は2025年10月25日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。