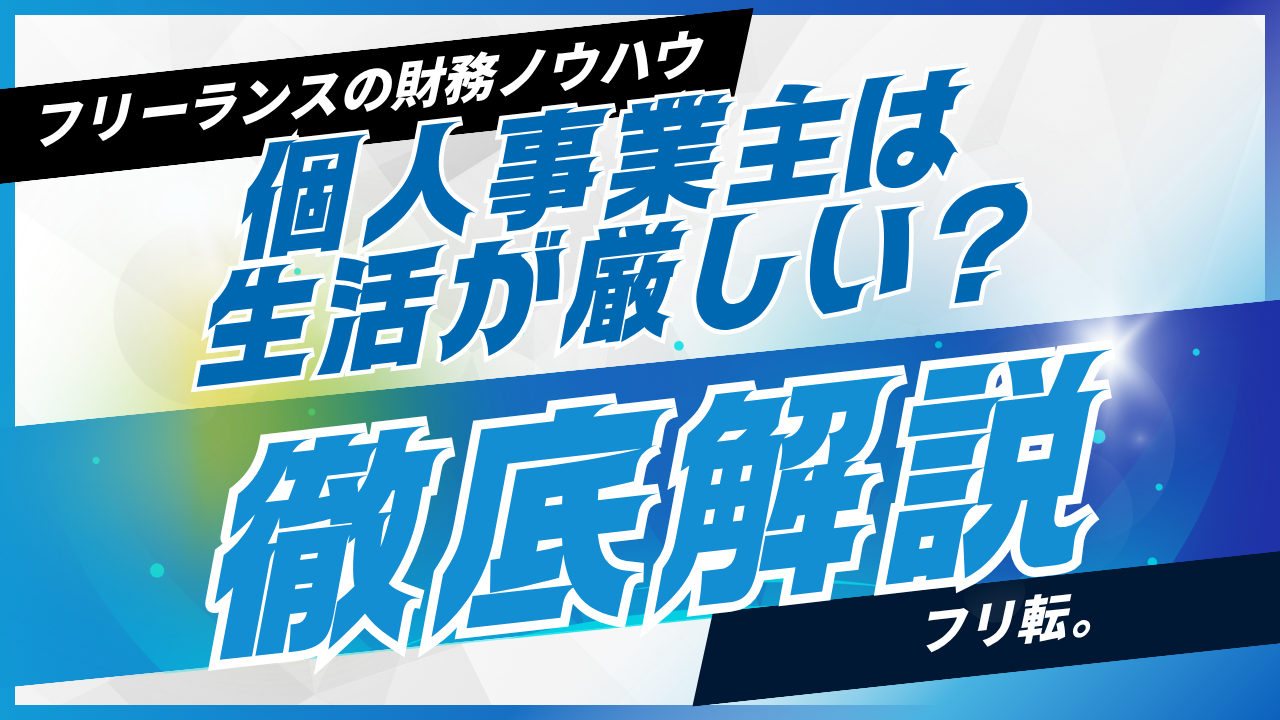個人事業主が「稼いでいるはずなのに生活できない」と感じる原因は、売上と手取りの混同にあります。
売上から経費を引いた所得(利益)から、さらに税金・社会保険料・借入返済・生活費を差し引くと、実際に使える金額は想定よりも少なくなります。
この記事では、個人事業主の所得の仕組みと手元に残らない理由、税金や社会保険料などの「見えない支払い」の実態、手元にお金を残すための具体的な対策とコツを税理士による実例をもとに解説します。
個人事業主の所得の仕組み|売上≠手取りの基本構造
個人事業主が「生活できない」と感じる根本原因は、売上と実際に使える金額の乖離を理解していないことです。給与明細がないため、会社員と異なり手取り額が可視化されません。
所得の計算式を正しく理解する
個人事業主の所得(利益)は、以下の計算式で求められます。
| 売上−経費=所得(利益) |
この所得が税金の計算基準となります。例:売上900万円−経費335万円=所得565万円。さらに青色申告特別控除(65万円)を差し引くと、実質的な所得金額は500万円になります。
この500万円がすべて自由に使えるわけではありません。ここから税金・社会保険料・借入返済などを支払う必要があるため、実際の手取りはさらに減少します。
青色申告決算書で自分の所得を確認する方法
自分の正確な所得を知るには、確定申告時に提出した「所得税青色申告決算書」を見ることが最も確実です。この書類の「所得金額」欄に記載されている数字が、あなたの年間利益です。
この数字を12で割れば月平均の所得が分かります。ただし、ここから税金や社会保険料を引いた額が実際の生活費として使える金額です。多くの個人事業主が、この「所得=使えるお金」と誤解し、資金繰りに苦しむことになります。
手元にお金が残らない理由|見落としがちな5つの支払い項目
所得が500万円あったとしても、実際に自由に使える金額は大幅に減ります。個人事業主が必ず支払わなければならない項目を見落としていることが、「稼いでいるのに生活できない」状態を生み出しています。
税金関係の支払い(所得税・住民税・事業税)
個人事業主は税金を後払いで納付する仕組みです。会社員のように給与から天引きされないため、確定申告後に納税通知が届いて初めて金額が確定します。
所得500万円の場合、おおよその税金額は以下の通りです。
| 税目 | 金額 |
| 所得税 | 約15万円 |
| 住民税 | 約40万円(課税所得の約10%+均等割) |
| 事業税 | 約15万円(業種により異なる) |
| 合計 | 約70万円 |
合計で約85万円の税金を後から支払うことになります。さらに、売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務も発生し、年間40万円〜50万円程度の追加負担が生じます。
この税金を事前に確保していないと、納税時期に資金不足に陥り、生活費を削るか借入に頼らざるを得なくなります。
ATTENTION
【住民税の注意点】
住民税は前年所得に基づいて翌年6月から課税されます。廃業・休業中でも支払義務があるため、納税資金の確保が重要です。さらに年間5,000円程度の均等割も加算されるため、所得税よりも高額になるケースが多くあります。
社会保険料の負担(国民健康保険・国民年金)
個人事業主は社会保険料も全額自己負担です。会社員のように会社が半額負担してくれることはありません。
| 項目 | 金額 |
| 国民健康保険 | 年間30万円〜50万円程度(所得により変動) |
| 国民年金 | 年間約20万円(1人分) |
| 合計 | 約65万円 |
所得500万円の場合、合計で年間約65万円の社会保険料がかかります。扶養家族がいればさらに負担は増加します。
借入返済の影響
事業資金として銀行や日本政策金融公庫から借り入れをしている場合、毎月の返済額も所得から支払います。
月5万円の返済なら年間60万円、複数の借入先がある場合はさらに返済額が増えます。借入返済は経費にならないため、所得に対する実質的な負担が大きくなります。
小規模企業共済・iDeCoなどの積立
節税対策として小規模企業共済やiDeCoに加入している場合、その掛金も所得から支払います。これらは将来への投資ですが、現在の手取りを減らす要因になります。
支払い総額の実例シミュレーション
所得500万円の個人事業主が実際に支払う金額を合計すると、以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
| 所得税 | 約20万円 |
| 住民税 | 約50万円 |
| 事業税 | 約15万円 |
| 国民健康保険 | 約45万円 |
| 国民年金 | 約20万円 |
| 借入返済 | 約60万円 |
| 合計 | 約210万円 |
所得500万円から210万円を差し引くと、残りは290万円です。これを12で割ると、月々使える金額は約24万円です。ここからさらに生活費を支払う必要があるため、実際の余裕はほとんどありません。
生活費の実態|毎月いくら必要なのかを正確に把握する
手元にお金を残すには、自分の生活費が月々いくらかかっているのかを正確に把握することが不可欠です。多くの個人事業主が、事業の収支には敏感でも、自分の生活費を把握していないために資金繰りに苦しんでいます。
固定費と変動費を洗い出す
生活費は「固定費」と「変動費」に分けて考えると管理しやすくなります。
固定費の例
- 家賃・住宅ローン返済
- 光熱費(電気・ガス・水道)
- 通信費(携帯・ネット)
- 保険料(生命保険・自動車保険など)
変動費の例
- 食費
- 日用品費
- 交際費・レジャー費
- 衣服費
これらを月単位で合計し、平均的な生活費を算出します。
住宅ローン・車のローンがある場合の影響
住宅ローンや車のローンがある場合、毎月の返済額が生活費を大きく圧迫します。住宅ローンで月10万円、車のローンで月3万円を支払っている場合、年間で156万円の固定支出が発生します。
これらのローン返済は待ったなしの支出であり、収入が減っても支払いを止めることはできません。
教育費の負担
子どもがいる家庭では、教育費も重要な支出項目です。学校の学費、塾や習い事、部活動費など、子ども1人あたり月3万円〜5万円程度かかることも珍しくありません。
子どもが複数いる場合や、高校・大学進学を控えている場合は、さらに教育費が増大します。
生活費が月24万円では足りない現実
先ほどの例で、所得から税金・社会保険料などを引いた残りが290万円、月々約24万円使えると計算しました。しかし、実際の生活費が月40万円かかっている場合、毎月16万円の赤字が発生します。
この赤字を補填するために、事業用の資金を取り崩したり、貯金を切り崩したりすることになります。最終的には借入に頼らざるを得なくなります。これが「稼いでいるのに生活できない」状態の正体です。
手元にお金を残すための5つの具体的対策
「生活できない」状態から脱却するには、所得と支出のバランスを正確に把握し、計画的な資金管理を行うことが必要です。以下の5つの対策を実践することで、手元にお金を残せるようになります。
対策1:自分の所得と税金額を正確に把握する
まず、過去の確定申告書と納税金額を確認しましょう。過去2年〜3年分の所得と納税額を一覧表にすることで、今年の納税額を予測できるようになります。
予測ができれば、納税資金を事前に確保することが可能になり、納税時期に慌てることがなくなります。
対策2:納税資金を毎月積み立てる
税金は後払いです。しかし、毎月の売上から一定割合を納税資金として別口座に積み立てることで、納税時の資金不足を防げます。
たとえば、所得税・住民税・事業税の合計が年間85万円なら、月々約7.1万円を積み立てておけば安心です。消費税の納税義務がある場合は、売上の約5%〜10%を別途積み立てておくことを推奨します。
消費税は原則として売上が1,000万円を超えた年の2年後から納税義務が発生します。ただし、2023年10月のインボイス制度開始により、売上1,000万円以下でも取引先の要請で課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択するケースが増えています。
インボイス登録をしている場合は、売上規模に関わらず消費税納税の準備が必要です。
事前に分かっているため、余裕を持って準備できます。
対策3:生活費のボーダーラインを設定する
所得から税金・社会保険料・借入返済を引いた残額を12で割り、「毎月これ以上使ってはいけない」というボーダーラインを明確にします。
このボーダーラインを超えないよう、固定費の見直しや変動費の管理を徹底します。家計簿アプリなどを活用して、日々の支出を可視化することも効果的です。
対策4:ビジネスのプール資金を確保する
事業を継続するには、予期せぬ支出に備えた資金が必要です。設備の故障、新しいツールの導入、取引先からの入金遅延など、急な資金需要は必ず発生します。
毎月の利益から、最低でも3か月〜6か月分の運転資金を貯蓄しておくことが理想です。これにより、一時的な売上減少や急な支出にも対応できます。
対策5:売上だけで判断しない
「今月は500万円稼いだから余裕だ」と売上だけを見て財布の紐を緩めるのは危険です。売上が高くても、経費が400万円かかっていれば実質的な利益は100万円しかありません。
判断基準は「売上」ではなく「所得(利益)」です。常に所得ベースで資金管理を行い、感覚的な判断を避けることが重要です。
絶対にやってはいけない2つのNG行動
手元にお金を残すために、以下の2つの行動は絶対に避けてください。これらは一時的には楽に感じるかもしれませんが、長期的には経営と生活を圧迫します。
NG行動1:稼いだ分だけ使う
「今月は売上が良かったから贅沢しよう」という考え方は非常に危険です。個人事業主は収入が不安定であり、来月以降も同じ売上が続く保証はありません。
また、税金や社会保険料は後払いのため、稼いだ分をすべて使ってしまうと、納税時期に支払いができなくなります。必ず一定割合を貯蓄・積立に回す習慣をつけましょう。
NG行動2:ビジネスが軌道に乗った瞬間に生活の質を上げる
売上が増え始めたタイミングで、すぐに家賃の高い物件に引っ越したり、高級車を購入したりするのは危険です。生活の質を一度上げると、下げることは非常に困難です。
ビジネスが安定するまでは、固定費を低く抑え、余剰資金を事業の成長や緊急時の備えに回すことが賢明です。少なくとも2年〜3年間は安定した収益が続いてから、生活水準の向上を検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1.所得500万円なら月々いくらまで生活費として使えますか?
所得500万円から税金・社会保険料・借入返済などで約210万円を差し引くと、残りは290万円です。これを12で割ると月約24万円ですが、実際の生活費がこれを超える場合は赤字になります。
自分の生活費を正確に把握し、ボーダーラインを設定することが重要です。
Q2.消費税の納税義務はいつから発生しますか?
原則として売上が1,000万円を超えた年の2年後から消費税の納税義務が発生します。たとえば2023年に売上が1,000万円を超えた場合、2025年から消費税を納める必要があります。
ただし、2023年10月のインボイス制度開始により、売上1,000万円以下でも取引先の要請で課税事業者を選択するケースが増えています。インボイス登録している場合は、売上規模に関わらず消費税の納税準備が必要です。
事前に分かっていることなので、売上の5%〜10%を毎月積み立てておくことで、納税時に慌てずに済みます。
Q3.税理士に依頼した方が良いのでしょうか?
事業が軌道に乗り、所得が安定してきた段階で税理士に相談することを推奨します。税理士は納税額のシミュレーション、節税対策、資金繰りのアドバイスなど、総合的なサポートを提供してくれます。
特に消費税の申告が始まる前に相談しておくと、納税資金の準備がスムーズになります。
Q4.青色申告の65万円控除を受けるにはどうすればよいですか?
青色申告の65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳、貸借対照表の提出、e-tax(電子申告)での申告が必要です。
クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を利用すれば、複式簿記への対応が自動化され、電子申告もスムーズに行えます。
Q5.生活費が把握できていない場合どこから始めればよいですか?
まず1か月間、すべての支出を記録してみましょう。家計簿アプリやexcelシートを使い、固定費(家賃、光熱費、通信費など)と変動費(食費、日用品、交際費など)に分けて記録します。
これにより、自分が毎月いくら使っているのかが明確になり、削減できる支出も見えてきます。
まとめ|所得の仕組みを理解し計画的な資金管理で生活を安定させる
個人事業主が「稼いでいるのに生活できない」と感じるのは、売上と手取りの違いを正確に理解していないことが原因です。所得から税金・社会保険料・借入返済を差し引いた実質的な手取り額を把握し、生活費のボーダーラインを設定することで、資金繰りは大きく改善します。
特に注意すべきは住民税です。住民税は所得税額の10%ではなく、課税所得に対して約10%が課税されるため、所得税よりも高額になるケースが多くあります。この点を見落とすと、納税時に大きな資金不足を招きます。
今日から実践できる4つのアクション
- 過去の確定申告書を確認する
過去2年分の所得と納税額を一覧表にし、今年の納税額を予測する - 納税資金を別口座に積み立てる
所得税・住民税・事業税の合計を12で割り、毎月積み立てる - 生活費のボーダーラインを設定する
1か月間すべての支出を記録し、固定費と変動費を洗い出す - 3か月〜6か月分の運転資金を確保する(継続)
毎月の利益から一定額を事業用プール資金として貯蓄する
生活費の引き出しを事業主貸で正しく処理することは、基本を押さえれば適切に対応できます。毎月の納税資金を積み立て、生活費を管理する習慣をつけることで、「稼いだお金が手元に残る」状態を作ることができます。
所得の仕組みを理解し、納税資金の積立と生活費管理を習慣化することで、個人事業主の資金繰りは大きく改善します。
出典・参照元
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「消費税のしくみ」
- 国税庁「インボイス制度の概要」
- 総務省「個人住民税」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 中小機構「小規模企業共済制度」
※記事内容は2025年10月25日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。