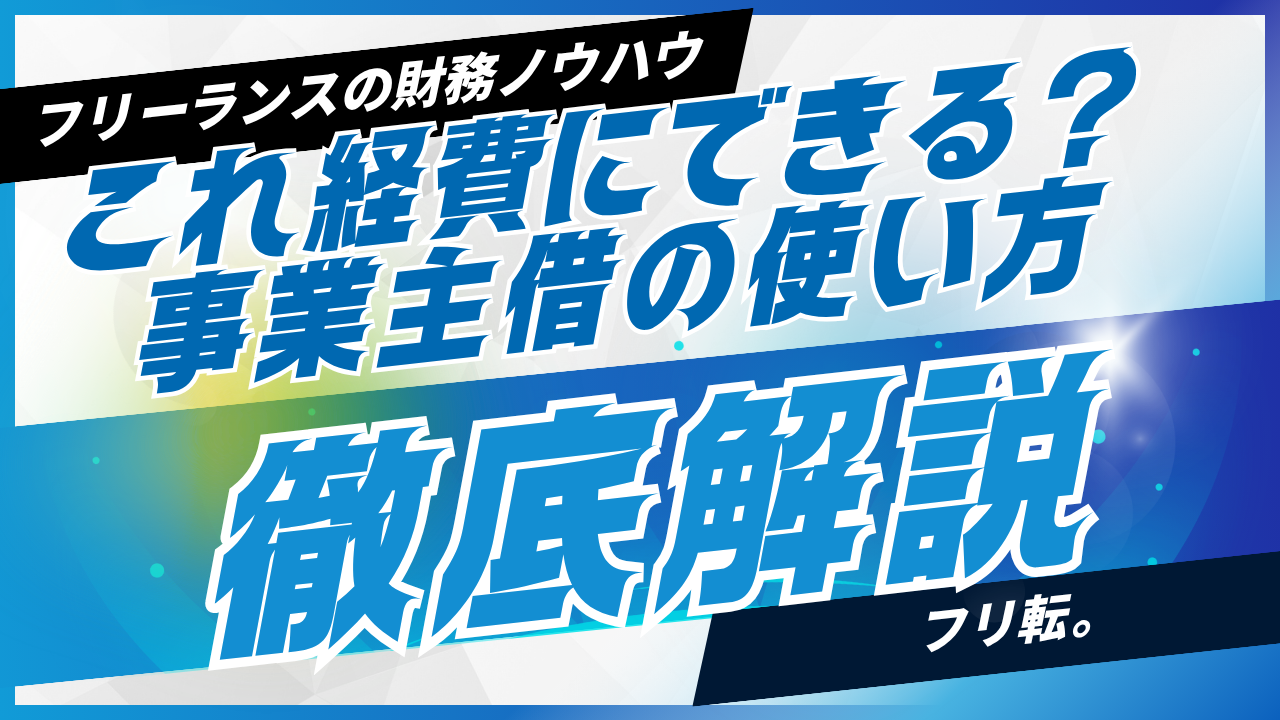個人事業主が確定申告で悩むポイントの一つが「何が経費になって、何が経費にならないのか」という線引きです。
事業主借とは、プライベートのお金を事業に投入したり、個人の財布で事業の経費を立て替えたりしたときに使う勘定科目です。
つまり、事業主借で処理するケースを理解すれば、経費になるもの・ならないものの判断基準が自然と身につきます。
この記事では、事業主借を使う具体的なパターンと仕訳方法、経費にできるもの・できないものの明確な判断基準、税務調査で指摘されないための記帳ルールを解説します。
事業主借とは?基本の意味と使い方
事業主借は個人事業主特有の勘定科目で、プライベート資金と事業資金を明確に区別するために使います。この基本を押さえることで、経費処理の判断ミスを防げます。
事業主借の基本的な意味
事業主勘定は事業の帳簿づけの中で、プライベートや事業所得以外の所得の動きについて使う勘定科目です。「事業主貸」と「事業主借」の2つに分かれます。
では、具体的にどのような場面で事業主借を使うのでしょうか。
事業主借を使う主なケース
プライベート口座から事業用口座への資金移動個人の財布で事業経費を立替払い事業用口座への利息の付与給与所得など事業所得以外の収入の入金
なぜ事業主借を理解すると経費判断ができるようになるのか
必要経費に算入できる金額は、総収入金額に対応する売上原価、および総収入金額を得るために直接要した費用の額です。加えて、その年に生じた販売費、一般管理費、業務上の費用の額も含まれます。
事業主借で処理するものは、基本的に「事業所得の計算に影響しない」取引を指します。事業主借を正しく使えるようになると、事業の支出とプライベートの支出を明確に区別でき、経費計上の判断ミスを防げます。
【パターン別】事業主借を使う具体例と仕訳方法
事業主借を使う代表的な4つのパターンを、実際の仕訳例とともに解説します。
パターン1:資金不足でプライベートから事業用口座へ移した
事業用口座の残高が足りなくなったため、個人のプライベート口座から70,000円を移した場合の仕訳例です。このようなケースでは、以下のように処理します。
仕訳例:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 70,000円 | 事業主借 | 70,000円 |
プライベート口座からでも現金からでも、事業用普通預金が増える場合は相手科目を「事業主借」とします。
パターン2:個人の財布で事業の経費を立て替えた
プリンターのインク代4,000円を個人事業主の財布から支払った場合の仕訳例です。このケースでは、経費科目と事業主借を組み合わせて処理します。
仕訳例:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 4,000円 | 事業主借 | 4,000円 |
個人で使っているクレジットカードで事業に関係する費用を支払ったときも、事業主借で処理します。プライベート用口座からクレジットカード料金が引き落とされる場合、未払金の勘定科目での処理や引き落とし日の記帳は必要ありません。
CHECK
重要ポイント:個人の財布から支払った場合でも、事業に必要な支出であれば経費計上可能です。レシートは必ず保管し、すぐに記帳しましょう。
パターン3:事業用口座に利息がついた
事業用口座に利息150円がついた場合の仕訳例です。利息は事業所得ではないため、事業主借で処理する点に注意が必要です。
仕訳例:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 150円 | 事業主借 | 150円 |
事業用口座の利息は事業収益のように見えますが、所得税法上は「利子所得」に分類されます。事業所得ではないため、事業主借で処理します。
預金利息は源泉分離課税のため、すでに税金が天引きされています。そのため、原則として確定申告に含める必要はありません。
パターン4:副業の給料が事業用口座に振り込まれた
会社員との兼業で、副業の給料が事業用口座に振り込まれた場合も事業主借で処理します。給料は事業所得ではなく給与所得に分類されるため、事業の収入には含めません。
経費にできるもの・できないもの【完全判断基準】
経費として認められるかどうかの判断基準を明確にし、個人事業主が経費計上できる項目とできない項目を具体的に解説します。
経費の判断基準は「事業との関連性」
個人事業主の出費が経費と認められるかの判断軸は、事業に関する支出であるか否かです。よく経費に計上できる費用についても、事業で実際に使用していない場合は、経費にはできません。
CHECK
判断のポイント:その支出は売上を得るために必要だったか事業の運営に直接関係する支出か客観的に見て事業関連性を説明できるか
経費にできないもの一覧
個人事業主本人の給与や年金、各種保険料などは経費として計上できません。個人事業主には「福利厚生」という概念がなく、事業主自身の健康診断・人間ドックなどにかかった費用は、経費として計上できないことになっています。
それでは、具体的にどのような項目が経費にできないのか見ていきましょう。
経費にできない主な項目:
| 項目 | 理由・補足 |
| 1. 個人事業主本人の給与・生活費 | 生活費として事業用口座から引き出したお金は経費になりません。個人事業主には給料という概念がないからです。 |
| 2. 所得税・住民税 | 住民税や所得税はあくまで個人が納める税金となるため、経費として計上できません。ただし、事業税や固定資産税の事業按分分は経費計上可能です。 |
| 3. 国民年金・国民健康保険 | 経費にはならないが、確定申告時に「社会保険料控除」として所得控除が可能です。 |
| 4. 個人事業主本人の生命保険料・医療保険料 | 個人事業主や従業員である家族の生命保険料は、経費としては扱いません。ただし、被保険者や受取人が従業員の生命保険料であれば、経費(福利厚生費)として扱います。 |
| 5. 借入金の元本返済 | 借入金の返済については、たとえ事業に関係のあるものでも、経費にすることができません。ただし、「利息」は経費に計上できます。 |
| 6. 交通違反の罰金 | 事業に関係する車両でも、罰金は経費計上不可です。 |
| 7. プライベートの支出 | 家族や友人との食事代、個人的な旅行費用、趣味のための出費は経費になりません。 |
経費にできるもの(主要な勘定科目)
個人事業主にとって経費は「事業につながる出費」であれば、すべて当てはめることができます。逆に、経費として認められる項目は幅広く存在します。代表的な勘定科目を確認しておきましょう。
経費として認められる主な項目:
| 勘定科目 | 具体例 |
| 租税公課 | 事業税、固定資産税、自動車税など |
| 消耗品費 | 文房具、事務用品、100,000円未満の備品 |
| 水道光熱費 | 事業使用分 |
| 通信費 | 電話代、インターネット料金 |
| 旅費交通費 | 出張費、取引先訪問の交通費 |
| 接待交際費 | 取引先との会食、贈答品 |
| 地代家賃 | 事務所家賃、駐車場代 |
| 給料賃金 | 従業員への給与 |
家事按分:事業とプライベートが混在する経費の扱い方
自宅兼事務所の家賃や水道光熱費など、事業とプライベートで共用する費用の処理方法を解説します。
家事按分とは
プライベートと事業の両方で使用する費用を「家事関連費」といいます。この家事関連費は、事業使用分を合理的に区分できれば、その部分のみ経費計上が可能です。
この家事関連費のうち必要経費として認められるのは、以下の条件を満たす場合のみです。
- 取引の記録などに基づいて明確に区分できること
- 業務遂行上、直接必要であったことが証明できること
- 区分できる金額の範囲内であること
つまり、「事業で使った分」を客観的な基準で証明できれば、その分だけ経費として計上できるということです。
家事按分の対象となる費用
家事按分が必要な主な費用と、その按分方法を以下の表にまとめました。
| 費用項目 | 按分方法 | 具体例 |
| 自宅兼事務所の家賃 | 床面積や使用時間で按分 | 事業使用割合30%の場合、家賃100,000円のうち30,000円を経費計上 |
| 水道光熱費 | 使用量や使用時間で按分 | 電気代の事業使用分を時間や面積で計算 |
| 通信費 | 通話時間やデータ使用量で按分 | 事業用とプライベート用の通話時間の比率で計算 |
| 車両費 | 走行距離や使用日数で按分 | 事業用の走行距離が全体の60%なら、ガソリン代の60%を経費計上 |
家事按分の割合は、合理的かつ客観的に説明できる根拠が必要です。床面積の測定結果、使用時間の記録、走行距離の記録など、税務調査で説明できるよう証拠を残しておきましょう。
家事按分の仕訳例(家賃100,000円、事業使用割合30%の場合):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 地代家賃 | 30,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
| 事業主貸 | 70,000円 | – | – |
税務調査で指摘されないための注意点
税務調査で問題とされないために、日頃から実践すべき記帳ルールと証拠書類の保管方法を説明します。
経費計上の証拠を残す
事業に関連することを証明できる支出のみを経費として計上できます。業務で使用したことを証明できるように、領収証書やレシートの裏にどんな仕事をしたかといったメモを残しておきましょう。
CHECK
証拠書類の保管ルール:レシート・領収書は、青色申告の場合は7年間(前々年分所得が3,000,000円以下の場合は5年間)、白色申告の場合は5年間保管取引内容をメモ(誰と・何のために・いくら)クレジットカード明細も保管
経費率に注意
確定申告の際の必要経費の上限は決められていませんが、業種ごとに「経費率」があるとされています。収入に対して経費の額が大きい場合には、プライベートの費用を事業上の経費と扱っているのではないかと疑われることもあります。
売上に対して経費が極端に多い場合、税務署から問い合わせがくる可能性があります。すべての経費について事業関連性を説明できるよう準備しておきましょう。
事業主貸・事業主借の記録漏れに注意
事業用口座とプライベート口座の間でお金を移動したときは、必ず事業主貸または事業主借で記帳してください。
記録を怠ると、帳簿上の残高と実際の残高がずれてしまい、税務調査で指摘される原因になります。
よくある質問(FAQ)
事業主借や経費処理について、個人事業主から多く寄せられる質問に回答します。
Q1.事業主借で処理したものは経費にできないのですか?
できます。事業主借は資金の出所を示す科目であり、経費になるかどうかは支出の内容で決まります。例えば「消耗品費/事業主借」という仕訳では、消耗品費として経費計上されます。
Q2.国民年金や国民健康保険は経費にできませんか?
経費にはできませんが、支払った全額を確定申告時に「社会保険料控除」として所得控除を受けられます。所得控除により課税所得が減るため、結果的に節税効果があります。
Q3.生活費を事業用口座から引き出した場合、どう処理すればいいですか?
「事業主貸」で処理していただき、仕訳は「事業主貸/普通預金」となります。生活費は経費にならないため、事業主貸という勘定科目で区分します。
Q4.プライベートのクレジットカードで事業の経費を支払った場合は?
支払った時点で「経費科目/事業主借」と仕訳します。引き落とし日の記帳は不要ですが、レシートは必ず保管してください。
Q5.家事按分の割合はどうやって決めればいいですか?
合理的かつ客観的に説明できる割合であれば問題ありません。床面積、使用時間、走行距離など、根拠となる数値を記録しておきましょう。
税務調査で説明を求められた際に答えられることが大切です。
まとめ
経費判断の3つのポイント
- 事業関連性が証明できるか – 売上獲得や事業運営に必要な支出のみ経費計上可能
- プライベートと明確に区分できるか – 家事按分は合理的な基準で
CHECK
証拠書類を保管しているか – レシート・領収書の保管と記帳は必須事業主借・事業主貸を正しく使い分け、税務リスクのない経理処理を実践しましょう。
出典・参照元
- 国税庁「No.2210必要経費の知識」
- 国税庁「No.1350事業所得の課税のしくみ」
- 国税庁「No.1310利息を受け取ったとき」
- 国税庁「No.1130社会保険料控除」
- 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
※記事内容は2025年10月25日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。