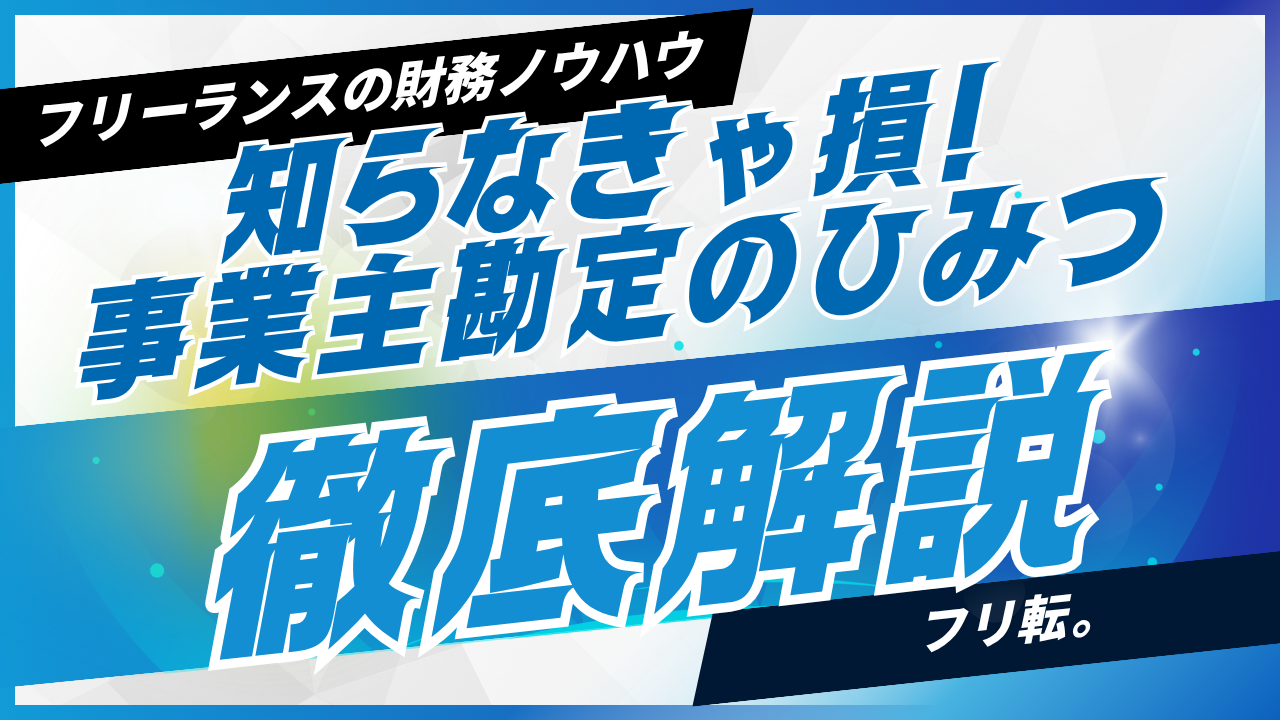事業主借・事業主貸は、確定申告後に自動相殺され、翌期首に0円にリセットされます。差額は元入金に反映されますが、税金には一切影響しません。
この記事では、相殺の仕組みと元入金の計算方法を、具体例を使って解説します。
事業主借・事業主貸とは|基本の定義と使い分け
ここでは、事業主借と事業主貸という勘定科目の基本的な定義を確認した上で、事業主貸と事業主借それぞれの具体的な使用場面を見ていきます。
事業とプライベートを橋渡しする特殊な勘定科目
事業主借と事業主貸は、事業用のお金と個人のお金を区別するために使用する、個人事業主だけが使う勘定科目です。
法人の会計には存在せず、個人事業主特有の処理方法として設けられています。なぜなら、事業を運営していると、事業資金から生活費を引き出したり、逆に個人資金を事業に投入したりする場面が頻繁に発生するからです。こうした資金移動を正確に記録し、事業の損益とプライベートの支出を明確に分けるために、この2つの勘定科目が必要になります。
イメージとしては、左側に「事業用のお金(店舗・口座)」、右側に「個人のお金(生活費・貯金)」があり、その間を行き来するお金の流れを記録する橋のような役割です。具体的には、事業用口座から生活費を引き出せば「事業主貸」、個人資金を事業口座に入金すれば「事業主借」として記録します。
実務では、freeeやマネーフォワード、弥生会計などのクラウド会計ソフトを使っていれば、これらの勘定科目は自動的に選択肢に表示され、仕訳も簡単に入力できます。また、手書きで帳簿をつけている場合でも、この2つの科目を理解しておけば正確な記帳が可能になります。
このように、事業主借と事業主貸は個人事業主の会計処理において欠かせない勘定科目です。
事業主貸の具体的な使用場面
事業主貸は、事業用のお金をプライベートに使った際に記録する勘定科目です。主に以下のような場面で使用します。
| 使用場面 | 具体例 | 仕訳例 |
| 生活費 | 事業用口座から現金引き出し | 事業主貸 100,000 / 普通預金 100,000 |
| 社会保険料 | 国保・国民年金の引き落とし | 事業主貸 35,000 / 普通預金 35,000 |
| 私的支出 | 個人的な買い物・投資・保険 | 事業主貸 ○○ / 普通預金 ○○ |
たとえば、毎月20日に事業用口座から生活費として10万円を引き出している場合、「事業主貸100,000円/普通預金100,000円」と仕訳します。国民健康保険料が月額35,000円自動引き落としされているなら「事業主貸35,000円/普通預金35,000円」です。
また、事業用クレジットカードで誤って家族の食材を購入してしまった場合(8,000円)は、「事業主貸8,000円/未払金8,000円」として処理し、経費から除外します。適用欄には「個人の買い物・○○カード」とメモしておくと、後から見返した際に分かりやすくなります。
つまり、事業に関係のない支出はすべて事業主貸として処理するのが原則です。
事業主借の具体的な使用場面
事業主借は、個人のお金を事業用に移動させた際、または事業以外の収入が事業用口座に入った際に使用する勘定科目です。
主な使用場面は以下の通りです。
| 使用場面 | 具体例 |
| 個人資金の投入 | 個人の貯金から事業用口座へ資金を移動した場合 |
| 利息・配当 | 事業用口座に利息や配当金がついた場合 |
| 個人資金での経費立替 | 事業用の備品や消耗品を個人のお金で購入した場合 |
| 保険金の入金 | 生命保険の満期金や解約返戻金が事業用口座に入金された場合 |
| 給与収入 | 副業の給与収入が事業用口座に振り込まれた場合 |
| 事業外収入 | 不動産収入や雑所得が事業用口座に入った場合 |
たとえば、事業用口座の残高が不足していたため、個人の普通預金から5万円を事業用口座に振り込んだとします。その場合「普通預金50,000円/事業主借50,000円」と仕訳し、適用欄には「個人から入金」と記載します。
また、事業用口座に利息が30円ついた場合も「普通預金30円/事業主借30円」と記載します。預金利息は源泉分離課税(20.315%)により課税が完結しており、事業所得には含まれないためです。
同様に、副業で給与収入がある方が給与振込先を事業用口座に設定している場合も注意が必要です。給与は事業所得ではないため「普通預金250,000円/事業主借250,000円」として明確に区別します。
このように、事業主借は「事業以外のお金が事業用に入ってきた」際の受け皿となる勘定科目です。
事業主借・事業主貸の相殺の仕組み|確定申告後に何が起こるのか
ここでは、事業主借と事業主貸が確定申告後にどのように処理されるかを見ていきます。貸借対照表での記載方法、自動相殺による翌期首の0円リセット、そして元入金への差額反映という一連の流れを、具体的な計算例を使って確認します。
また、元入金がマイナスになった場合でも税務上問題ない理由についても触れます。
貸借対照表での記載と決算時の処理
事業主貸と事業主借は、確定申告書の貸借対照表(青色申告決算書4枚目)に記載されます。1年分の合計金額が表示される仕組みです。
具体的には、貸借対照表の資本の部に「事業主貸」「事業主借」という項目が印刷されており、12月31日時点での累計額を記入します。たとえば、1年間で生活費として240万円引き出し、国民健康保険料・国民年金で60万円支払っていれば、事業主貸は合計300万円になります。一方、個人資金を50万円事業に投入し、利息が1,000円ついていれば、事業主借は501,000円です。
ここで重要なのは、この2つの勘定科目は所得や税金の計算には影響しないという点です。所得金額は「売上-経費」で計算されるため、事業主勘定は関係しません。たとえば、事業主貸が1,000万円でも事業主借が10万円でも、課税所得は変わらず、納税額にも影響しないのです。
実務面では、会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)やe-Taxを使用している場合、これらの金額は取引入力に基づいて自動的に集計され、貸借対照表に反映されます。一方、手書きで申告書を作成している場合は、1年分の事業主貸・事業主借の仕訳をすべて合計して記入する必要があります。
このように、事業主勘定は貸借対照表上の記録であり、損益には関係しない特殊な科目です。
相殺計算と元入金への反映の流れ
確定申告が終わると、事業主貸と事業主借は自動的に相殺されます。翌期首には両方とも0円にリセットされます。
相殺の計算式は非常にシンプルです。「事業主貸-事業主借」の差額が元入金に加減算されます。ここで元入金とは、個人事業主における資本金のような概念で、事業にどれだけの資金が投下されているかを示す科目です。
具体的な計算の流れを見てみましょう。
【相殺の計算例】
▼ 当期末の数字
- 期首元入金:500万円
- 当期純利益:300万円
- 事業主貸:280万円
- 事業主借:50万円
▼ 翌期首の元入金
| 500万円(元入金) + 300万円(利益) – 280万円(事業主貸) + 50万円(事業主借) =570万円 |
→ 事業主貸・事業主借は0円にリセット
この計算により、事業主貸280万円と事業主借50万円は相殺され、翌期の貸借対照表では両方とも0円からスタートします。つまり、差額の230万円(事業主貸の方が多い)は元入金から差し引かれる形になり、純利益300万円と合わせて最終的に570万円の元入金となります。
freeeやマネーフォワード、弥生会計、e-Taxなどのソフトウェアを使用している場合、この相殺処理は完全自動で行われます。ユーザーが手動で仕訳を入力したり計算したりする必要はありません。翌年1月1日の開始残高を確認すると、事業主貸・事業主借が0円になっており、元入金が新しい金額に更新されていることが確認できます。
このように、事業主勘定の相殺は決算の自動処理として組み込まれており、意識せずとも正しく処理されます。
元入金がマイナスになる場合の考え方
元入金の計算結果がマイナスになることもありますが、税務上は問題ありません。
元入金がマイナスになるのは、「事業が生み出した利益よりも、プライベートに引き出した金額の方が多い」状態を意味します。たとえば、当期純利益が200万円だったにもかかわらず、生活費として350万円を引き出していた場合、その差額150万円が元入金から減少します。
【マイナスになる例】
- 期首元入金:100万円
- 当期純利益:200万円
- 事業主貸:400万円
- 事業主借:0円
| 翌期首元入金=100万円+200万円-400万円+0円=△100万円 |
このマイナス100万円は、「事業が個人から100万円借りている状態」を示しています。個人事業主は事業と個人が一体であるため、自分で自分にお金を借りているような状態です。法人であれば「債務超過」として深刻ですが、個人事業主の場合は単なる資金の流れを示すだけで、税務署が問題視することはありません。
実際、子どもの教育費がかさむ時期や、開業初年度で売上が少ない時期などは、元入金がマイナスになるケースは珍しくありません。大切なのは、毎年の所得をきちんと申告し、適正に納税していることです。元入金の金額そのものは税額計算に影響せず、あくまで事業の財政状態を示す参考値に過ぎません。
このように、元入金のプラス・マイナスは税務上の評価とは無関係です。
事業主勘定が多くなる原因と税務上の扱い
ここでは、事業主貸や事業主借の金額が大きくなる主な原因を分析します。
所得を超える生活費の引き出しや、高額資産購入時の個人資金利用という2つのパターンから、金額の大小が税務調査の対象にならない理由、そして初心者が陥りやすい4つの誤解まで、正しい理解を整理していきます。
事業主貸が多額になる2つの主要因
事業主貸の金額が大きくなる主な原因は、以下の2パターンです。
- 所得よりも生活費の引き出しが多い
- 高額資産の購入で個人資金を使用している
1つ目の原因は、1年間で稼いだ事業所得(利益)よりも、生活費として引き出した金額が上回っているケースです。たとえば年間の事業所得が400万円なのに、生活費として毎月40万円(年間480万円)引き出していれば、差額の80万円分は貯蓄や以前の利益から補填していることになります。
このパターンは、子どもが高校・大学に進学して教育費がかさむ時期や、家族の医療費が増えた年などによく見られます。つまり、事業の利益が一定でも、家計支出が増えれば事業主貸の金額は自然に大きくなるわけです。
2つ目の原因は、車両や機械設備など高額な資産を購入する際に、事業用口座だけでは資金が足りず、個人の貯蓄から補填したケースです。たとえば300万円の営業車を購入する際、事業用口座から100万円、個人貯金から200万円を支出した場合、200万円分は事業主借として記録されます。
逆に、個人資金を多く投入していれば事業主借が大きくなります。車両購入で頭金を個人資金から出した、開業時に自己資金を大量に投入したといった場合です。
このように、事業主勘定の金額は事業の成長段階や家計状況によって変動するのが自然です。
金額が大きくても税務調査の対象にはならない理由
事業主貸や事業主借の金額が多額でも、それ自体が税務調査の対象になることはありません。
なぜなら、事業主勘定は所得や税金の計算に影響を与えないからです。所得税は「売上-経費」で計算される事業所得に対して課税されます。事業主貸・事業主借は資金の移動を記録しているだけで、損益計算には含まれません。
税務署が税務調査で確認するのは、「売上が適正に計上されているか」「経費が事業関連性のあるものか」「架空経費はないか」といった点です。つまり、事業主勘定の残高が大きいからといって、それが即座に問題視されることはないのです。
ただし、1点だけ絶対に避けなければならないのは、売上を事業主借で処理して所得から除外する行為です。たとえば、売上50万円が事業用口座に入金されたのに「普通預金500,000円/事業主借500,000円」と仕訳し、売上を隠蔽すれば、これは明確な脱税行為となります。重加算税などの重いペナルティが科されます。
正しい処理は「普通預金500,000円/売上500,000円」です。売上はすべて収入として計上し、その上で必要経費を差し引いて所得を算出するのが正しい会計処理です。事業主勘定は、あくまで事業と個人の資金移動を記録する科目であり、売上や経費の操作に使ってはいけません。
このように、正しく使用している限り、事業主勘定の金額の大小は税務上の問題にはなりません。
初心者が陥りやすい誤解と正しい理解
事業主勘定について、初心者が陥りやすい誤解がいくつかあります。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
| 事業主貸が多いと税金が増える | 事業主貸は税金計算に無関係です。生活費を100万円引き出しても500万円引き出しても、納税額は変わりません。 |
| 元入金がマイナスだと税務署に怒られる | 元入金のマイナスは税務上問題ありません。個人事業主と事業は一体なので、自分が自分に借りているだけです。 |
| 事業主借・事業主貸は手動で相殺しなければならない | 会計ソフトやe-Taxを使っていれば完全自動です。手作業は不要です。 |
| 事業主勘定を使わずに処理できる | 個人事業主は必ず事業主勘定を使う必要があります。生活費や個人資金の移動を適切に記録しないと、正確な財務状況が把握できません。 |
正しい理解は、「事業主勘定は資金の流れを記録するだけの科目であり、損益や税金には影響しない」というものです。会計ソフトが自動で相殺処理してくれるので、適切に使い分けることだけを意識すればよいのです。
最初は仕組みが理解しづらいかもしれません。しかし、実際に1年間記帳を続け、確定申告を経験すると「ああ、こういうことか」と腑に落ちる瞬間が必ず訪れます。
それまでは、事業支出とプライベート支出を明確に区別し、適切な勘定科目を選ぶことに集中しましょう。
青色申告と事業主勘定の関係|節税効果を最大化する基礎知識
ここでは、事業主勘定を正しく使いこなしながら青色申告の節税効果を最大化する方法を見ていきます。
65万円控除を受けるための3つの必須条件、青色申告承認申請書の提出タイミング、そして経費として認められる項目と事業主貸で処理すべき項目の使い分けまで、実務に直結する知識を整理します。
青色申告65万円控除を受けるための3つの必須条件
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、以下の3つすべての条件を満たす必要があります。
| 必須条件 | 具体的な内容 | 対応方法 |
| ①複式簿記での記帳 | すべての取引を複式簿記形式で記録 | 会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計)を使えば自動変換 |
| ②貸借対照表と損益計算書の提出 | 青色申告決算書(4枚)を提出 | 会計ソフトが自動作成 |
| ③e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存 | マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式で電子申告 | 税務署でID・パスワード発行可能 |
CHECK
重要:3条件のうち1つでも欠けると、控除額は55万円または10万円に減額されます。
複式簿記は一見難しそうに見えますが、クラウド会計ソフトを使えば、取引を入力するだけで自動的に複式簿記形式に変換されます。たとえば、売上10万円が銀行口座に入金された場合、ソフトに「普通預金 100,000円 / 売上 100,000円」という仕訳が自動生成されます。決算時には貸借対照表も自動作成されます。
次に、3つ目の条件であるe-Taxでの電子申告について見ていきましょう。電子申告には2つの方法があります。
| 方式 | 必要なもの | 特徴 |
| ①マイナンバーカード方式 | マイナンバーカード+カードリーダーまたはスマートフォン | 事前に準備が必要だが、以降は毎年使える |
| ②ID・パスワード方式 | 税務署で発行されるID・パスワード | マイナンバーカード不要。税務署で即日発行可能 |
いずれの方式も自宅から申告が完結します。
このように、3条件をすべて満たすことで、65万円の所得控除により、所得税率10%の人なら所得税が約65,000円、20%の人なら約130,000円軽減されます。それに加えて住民税は一律10%(約65,000円)軽減され、国民健康保険料も所得に応じて減額されるため、総合的な節税効果はより大きくなります。
青色申告承認申請書の提出タイミング
青色申告を利用するには、事業開始から2か月以内(または適用を受けたい年の3月15日まで)に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届は所得税法で事業開始から1か月以内の提出が定められていますが、罰則規定はありません。実務上は青色申告承認申請と同時に提出するケースも認められています。
ただし、開業届を提出して個人事業主として登録することが前提条件となり、この手続きを怠ると青色申告の特典を受けられません。
たとえば、2025年4月に開業した場合、6月初旬までに両方の書類を提出すれば、その年分から青色申告が適用されます。提出は税務署窓口のほか、e-Taxを利用したオンライン申請も可能です。控えを保管しておくことで後日の確認もスムーズになります。
このように、青色申告は事前準備が必要ですが、一度承認を受ければ継続的に節税メリットを享受できる重要な制度です。
経費計上と事業主貸の使い分け
事業に関係する支出は経費として計上し、プライベートな支出は事業主貸で処理する、という明確な線引きが節税の基本です。
そこで、経費として認められる主な項目は以下の通りです。
| 経費科目 | 具体例 |
| 地代家賃 | 事務所・店舗の賃料、駐車場代 |
| 通信費 | 電話代、インターネット料金、郵送費 |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代(事業使用分) |
| 消耗品費 | 文房具、コピー用紙、10万円未満の備品 |
| 旅費交通費 | 電車代、ガソリン代、宿泊費(事業目的) |
| 接待交際費 | 取引先との飲食代、贈答品代 |
| 広告宣伝費 | Web広告費、チラシ印刷代 |
| 外注費 | 専門家への業務委託費 |
自宅を事業所として使用している場合、家賃や光熱費を事業使用割合に応じて按分計上できます。たとえば自宅の床面積の30%を事業スペースとして使っているなら、家賃の30%を地代家賃として経費にできます。
一方、経費として認められない支出は以下の通りです。
| 支出項目 | 処理方法 | 控除の有無 |
| 生活費 | 事業主貸 | なし |
| 住民税・所得税 | 事業主貸 | なし |
| 国民年金 | 事業主貸 | 社会保険料控除(所得控除) |
| 国民健康保険料 | 事業主貸 | 社会保険料控除(所得控除) |
| 生命保険料 | 事業主貸 | 生命保険料控除(最大120,000円) |
| 私的な交際費 | 事業主貸 | なし |
| 住宅ローン | 事業主貸 | 住宅ローン控除(別途適用) |
これらは事業主貸で処理します。ただし、国民健康保険料や国民年金は経費にはなりませんが、確定申告時に「社会保険料控除」として所得控除の対象になります。
生命保険料も「生命保険料控除」の対象となり、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最大40,000円、合計で最大120,000円(所得税)まで控除可能です。
なお、青色申告者で常時使用する従業員数が500人以下の事業者なら、30万円未満の減価償却資産を一括償却できる特例があります(年間合計300万円まで)。パソコンやカメラなど高額な機材を購入する際は、この特例を活用することで初年度に全額経費計上できます。
このように、経費と事業主貸を正しく使い分けることで、適正な節税と正確な帳簿作成が両立します。
よくある質問(FAQ)
Q1.事業主貸と事業主借の相殺は、いつ、誰が行うのですか?
確定申告の決算処理時に会計ソフトまたはe-Taxが自動的に行います。ユーザーが手動で仕訳を入力する必要はありません。翌期首には両科目が0円にリセットされ、差額が元入金に反映されます。
Q2.元入金がマイナスになっても融資は受けられますか?
金融機関は元入金よりも、事業の収益性・返済能力・事業計画を重視します。元入金がマイナスでも、安定した売上と利益があれば融資の可能性はあります。ただし財務状況の説明は求められるでしょう。
Q3.事業主貸で処理した国民健康保険料は、どこで控除されますか?
確定申告書の「社会保険料控除」欄で所得控除として適用されます。経費ではなく所得控除なので、事業主貸で処理した上で、申告書で別途控除を受ける形になります。国民年金も同様です。
Q4.事業主貸の記帳漏れに後で気づいた場合は?
気づいた時点で「事業主貸 / 普通預金」の仕訳を入力すれば問題ありません。日付は実際の引き出し日に遡るのが理想ですが、決算前であれば12月31日付で一括処理も可能です。
Q5.事業用クレジットカードで私的な買い物をした場合、どう処理すればいいですか?
「事業主貸○○円/未払金○○円」と仕訳し、経費から除外します。適用欄に「個人の買い物」とメモしておくと、後から見返した際に分かりやすくなります。カード明細を確認し、私的支出は必ず事業主貸で処理しましょう。
まとめ
事業主借・事業主貸は確定申告後に自動的に相殺され、差額が元入金に反映される仕組みです。この2つの勘定科目は所得や税金に影響せず、単に事業とプライベート間の資金移動を記録するためのものです。
金額の大小は税務上問題にならず、元入金がマイナスになっても違法ではありません。会計ソフトを使えば相殺処理は完全自動化されるため、日々の記帳では事業支出とプライベート支出を正しく区別することだけに集中しましょう。
【記帳で迷わないための3つのポイント】
- 事業用口座とプライベート口座を分ける
- 生活費は月1回まとめて引き出す
- 会計ソフトで月次確認する習慣をつける
正しい事業主勘定の理解と使用が、正確な帳簿作成と安心な確定申告への第一歩です。青色申告の3条件を満たし、経費と事業主貸を適切に使い分けることで、最大限の節税効果を得ながら、税務リスクのない健全な事業運営を実現できます。
出典・参照元
- 国税庁「青色申告特別控除」
- 国税庁「所得税法第45条(必要経費)」
- 国税庁「租税特別措置法第28条の2(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)」
- 国税庁「所得税法第181条(利子所得の源泉分離課税)」
- 国税庁「生命保険料控除」
- 総務省「個人住民税」
※記事内容は2025年10月25日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。