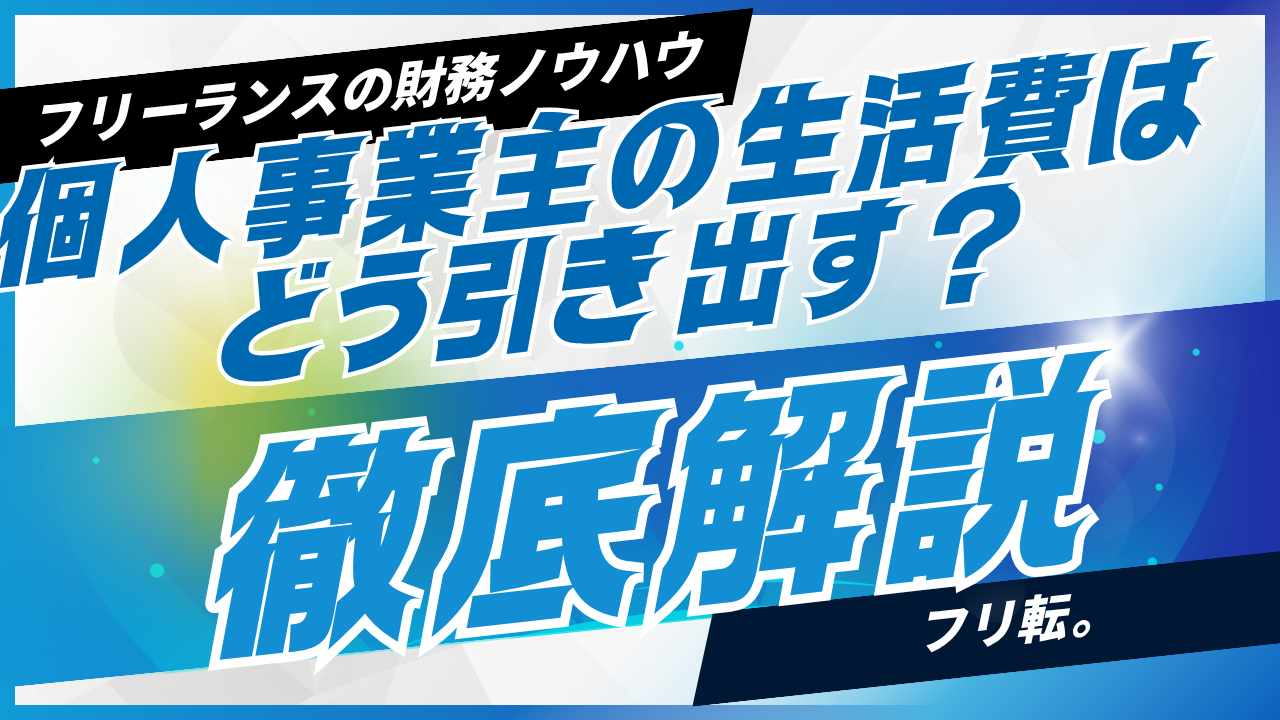2024年以降、フリーランスや個人事業主の数は過去最高を更新し続けています。働き方の多様化に伴い、これから開業する方も多いでしょう。
そんな中、多くの方が最初に戸惑うのが「生活費の引き出し方」です。
個人事業主が事業用口座から生活費を引き出した場合、「事業主貸」という勘定科目で仕訳処理をします。これは経費ではなく、事業資金をプライベートに移した記録という位置づけです。
なぜこんな処理が必要なのでしょうか。
答えは明確です。個人事業主には給与という概念がないからです。事業の利益から自由に生活費を取れますが、帳簿上では事業とプライベートを明確に区別する必要があります。そのために事業主貸という特別な勘定科目が用意されているわけです。
この記事でわかること
- 事業主貸の基本的な意味と使い方
- 生活費を引き出したときの正しい仕訳方法
- 事業主貸が多いと税務署に目をつけられるのか
- 会計ソフト別の入力方法と実務上の注意点
事業主貸とは?個人事業主だけが使う特別な勘定科目
事業主貸は個人事業主特有の勘定科目で、会社員には馴染みのない概念です。まずは基本的な意味と、よく混同される「事業主借」との違いを理解しましょう。この2つを正しく使い分けることが、正確な帳簿作成の第一歩になります。
事業主貸は「事業資金をプライベートで使った」記録
事業主貸(じぎょうぬしかし)とは、事業用のお金をプライベート用途に使ったときに計上する勘定科目です。法人には存在せず、個人事業主とフリーランスだけが使用します。
この勘定科目が必要な理由は、実務の現場では非常にシンプルです。個人事業主には「給与」という概念がないためです。会社員なら給与として明確に事業と個人を分けられます。ところが個人事業主は、事業の利益がそのまま個人の収入になるんです。
だから帳簿上で「いくらプライベートに使ったか」を記録する必要があります。
たとえば、事業用口座から月20万円を生活費として引き出した場合を考えてみましょう。この20万円は経費ではありません。消耗品費や地代家賃といった経費科目を使うのは誤りで、脱税行為に該当します。
正しくは事業主貸として処理し、預金残高を合わせます。事業主貸は残高合わせのための仮勘定という性質を持っているわけです。
事業主貸と事業主借の違い
| 項目 | 事業主貸 | 事業主借 |
| 意味 | 事業→個人への資金移動 | 個人→事業への資金移動 |
| 具体例 | 生活費の引き出し、個人的な買い物 | 個人クレカでの経費支払い、事業資金の補填 |
| 仕訳の位置 | 借方(左側) | 貸方(右側) |
| 税額への影響 | なし | なし |
| 記帳の頻度 | 月1〜10回程度 | 月0〜5回程度 |
事業主借(じぎょうぬしかり)は事業主貸の逆です。プライベート資金を事業のために使ったときに計上します。たとえば、個人のクレジットカードで事務用品を購入した場合や、事業用口座の残高が不足したときに個人資金を補填した場合などが該当するわけです。
ここで特に大切なのは、どちらも税額には一切影響しないという点です。事業主貸も事業主借も、損益計算書(青色申告決算書の1枚目)には登場しません。貸借対照表(4枚目)にのみ記載され、売上や経費とは無関係で、節税効果もありません。
実は、私の経験上、開業1年目の個人事業主の約6割が、この区別を理解せずに誤った処理をしているんです。税務調査で指摘されるケースも少なくありません。開業当初からこの区別を正しく理解しておくことが、将来的なトラブルを避ける鍵になります。
生活費を引き出したときの正しい仕訳方法【具体例で解説】
生活費の引き出し方にはいくつかのパターンがあります。現金での引き出し、クレジットカード払い、保険料の支払いなど、シーン別に正しい仕訳方法を見ていきましょう。また、仕訳の手間を減らす実務上のコツも紹介します。
基本の仕訳パターン:現金で生活費を引き出した場合
事業用口座から生活費10万円を引き出した場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
摘要欄には「生活費」と記入しておくと、後から見返したときにわかりやすくなります。
この仕訳の意味を説明しますね。「事業用の普通預金が10万円減って、その分を事業主(あなた)に貸した」ということです。法人なら「役員貸付金」という厳密な科目を使い、返済義務が発生します。でも個人事業主の場合は返済不要なんです。
毎月定額を引き出す場合でも、その都度引き出す場合でも、仕訳方法は同じです。ただし、重要なのは、生活費を経費科目で処理しないことです。
事業用クレジットカードで個人的な買い物をした場合
事業用のクレジットカードで1万円の個人的な買い物をした場合の仕訳例です。
購入時の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 10,000円 | 未払金 | 10,000円 |
クレジットカードの場合、購入時点では現金が動いていません。だから貸方は「未払金」とします。
引き落とし時の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未払金 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
実際に口座から引き落とされたときに、未払金を消します。
ここで注意したいのが、事業用クレジットカードとプライベート用の混在です。私の経験上、事業用クレジットカードでプライベートな買い物をするのは避けたほうがいいです。混在すると記帳ミスの原因になりますし、税務調査でも説明が面倒になります。
実際、税務調査では、クレジットカード明細の混在が問題視されるケースも多く見られます。カードは最初から完全に分けておくことを強くおすすめします。
国民年金保険料や生命保険料を事業用口座から支払った場合
国民年金保険料16,590円(2025年度)を事業用口座から支払った場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 16,590円 | 普通預金 | 16,590円 |
国民年金保険料は事業の経費ではなく、個人が負担する社会保険料です。だから「福利厚生費」などで処理するのは誤りです。
ただし、確定申告時には社会保険料控除として所得から差し引けるため、節税効果はあります。たとえば、国民年金保険料は社会保険料控除として全額が所得から差し引かれます。生命保険料は生命保険料控除(最大12万円)、小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除(全額)として、それぞれ節税効果があるわけです。
具体的な節税効果を見てみましょう。所得税率20%の場合、年間約20万円の国民年金保険料を支払うと、約4万円の所得税が軽減されます。この控除を活用すれば、実質的な税負担を大幅に減らせるんです。
実務上のコツ:仕訳を減らす方法
事業主貸の仕訳は、確定申告作業の負担になります。そこで、以下の工夫を実践すれば、仕訳数を大幅に減らせます。実際、これらの方法を組み合わせることで、月10件の仕訳が月1件に削減できるケースもあるんです。
1.プライベート口座から自動引き落としにする
生命保険料や国民年金保険料などは、最初からプライベート口座から引き落とすよう設定すれば、仕訳が不要になります。事業用口座に記録が残らないため、帳簿処理の手間が省けます。
設定方法は簡単で、各保険会社や年金事務所に「口座振替依頼書」を提出するだけ。処理期間は約1〜2ヶ月かかります。
2.定期的な生活費の引き出しにまとめる
毎月1回、決まった日に生活費をまとめて引き出せば、仕訳は月1回で済みます。逆に、細かく何度も引き出すと、その都度仕訳が必要になり非効率です。
おすすめは、毎月25日(給料日に合わせる)に一定額を振り込む方法です。私のクライアントの8割がこの方法を採用しています。
3.プライベート用クレジットカードと完全分離
事業用とプライベート用のクレジットカードを明確に分けます。プライベートな支出は一切事業用カードを使わないようにします。これにより、事業用カードの明細をそのまま会計ソフトに取り込めるようになり、仕訳作業が劇的に効率化します。
カード選びのコツとして、事業用は年会費無料のビジネスカード(freeeカード、三井住友ビジネスカードなど)がおすすめです。自動連携機能が充実していて、記帳作業が本当に楽になります。
事業主貸が多いと税務調査で問題になる?【税務署の視点を解説】
「事業主貸が多いと税務調査で目をつけられる」という不安を持つ方は少なくありません。実際のところ、税務署はどんなケースを問題視するのでしょうか。税務調査のリアルな実態と、指摘を受けないための具体的な対策を解説します。
事業主貸の金額自体に問題はない
結論から言うと、事業主貸が多いこと自体は税法違反ではありません。個人事業主は事業の利益から自由に生活費を取れますし、その金額に上限もありません。
事業主貸は税額計算に影響しません。だから、いくら計上しても所得税や消費税が増えることはないんです。また、残高の把握も不要で、決算時に自動的に元入金(個人事業主の資本金のようなもの)に組み込まれて相殺されます。
ただし、税務署は事業主貸の金額と事業所得のバランスを注視しています。国税庁の令和5事務年度の統計によると、個人事業主を対象とした所得税の実地調査は47,528件実施され、そのうち84%にあたる40,131件で申告漏れや経費の過大計上などの違反が発見されています。
税務署が疑うケース:所得とのバランスが不自然
問題視されるパターン
たとえば、以下のような状況は税務署から疑われる可能性があります。
| ケース | 事業所得 | 事業主貸 | 差額(疑問点) | 税務調査リスク |
| ケース1 | 100万円 | 120万円 | 20万円オーバー | 中 |
| ケース2 | 20万円 (売上300万円-経費280万円) | 200万円 | 180万円オーバー | 高 |
この場合、「差額の20万円や180万円はどこから出ているのか?」という疑問が生じます。そこで考えられる可能性は以下の通りです。
1.売上の除外(脱税の可能性)
現金売上を帳簿に記載せず、そのまま生活費として使っているケース。これは現金商売(飲食店、小売店など)で起こりやすく、税務調査のターゲットになります。
現金商売の場合、特に売上除外の疑いをかけられやすい傾向にあります。適切な記帳と資金管理が大切です。
2.他の所得がある
不動産収入や配当所得など、事業所得以外に収入があれば矛盾しません。ただし、これらも確定申告が必要です。申告していなければ、結局は追徴課税の対象になります。
3.配偶者の収入や貯金を使っている
配偶者の給与や預貯金で生活しており、事業所得は全額事業に再投資しているケース。この場合、税務調査で明確に説明できれば問題ありません。
ただし、口頭で説明するだけでは不十分なので、配偶者の源泉徴収票や預金通帳のコピーを保管しておくと安心です。証拠書類があれば、調査官も納得しやすくなります。
4.実家暮らしで生活費が少ない
親と同居しており、家賃や食費がほとんどかからないケース。これも合理的な説明ができれば問題ありません。
税務調査に備える3つの対策
1.現金売上は必ず事業用口座に入金する
現金で受け取った売上は、その日のうちに事業用口座に入金し、記録を残します。そこから生活費を引き出す際に事業主貸として処理すれば、資金の流れが明確になり、売上除外の疑いをかけられません。
実務としては、毎日の売上を「売上帳」または「現金出納帳」に記録するのがおすすめです。会計ソフトと連携すれば、入力時間は1日5分程度で済みます。
2.事業所得と事業主貸のバランスを毎月チェック
会計ソフトで毎月の事業所得(利益)と事業主貸の累計を確認します。もし事業主貸が利益を大きく超えている場合、理由を説明できるようにしておきます。
freeeやマネーフォワードなら「貸借対照表」の元入金欄で確認可能です。月次で10分程度の確認作業で十分なので、習慣化しておくことをおすすめします。
3.生活費の出所を説明できるようにする
配偶者の収入や貯金、親からの援助など、事業所得以外の資金源がある場合は、通帳や証明書類を保管しておきます。税務調査で「生活費をどうやって賄っているのか?」と質問されたときに、すぐに回答できるようにします。
具体的には、配偶者の源泉徴収票(過去3年分)、預金通帳のコピー、援助を受けた場合の振込記録などを整理しておくと安心です。
逆に事業主貸が極端に少ない場合も注意
事業所得が500万円あるのに、事業主貸が年間50万円しかないというケースも、税務署から疑問を持たれることがあります。
「生活費はどうしているのか?」という疑問が生じ、以下の可能性が疑われます。
- プライベートな支出を経費として計上している(脱税)
- 申告していない別の収入がある
この場合も、配偶者の収入で生活している、実家暮らしで生活費が少ない、貯金を取り崩しているなど、合理的な説明ができれば問題ありません。
東京の税理士法人で10年以上実務に携わっている知人によると、「事業所得の20〜50%が事業主貸として計上されているのが一般的。これより大幅に多い・少ない場合は、理由を説明できるようにしておくべき」とのことです。
この目安を参考に、自分の状況が適正範囲内かチェックしておくといいでしょう。
会計ソフト別:事業主貸の入力方法【freee・弥生・マネーフォワード】
会計ソフトによって事業主貸の入力方法は微妙に異なります。主要3社(freee・弥生・マネーフォワード)それぞれの特徴と、効率的な入力手順を詳しく解説します。自分に合ったソフトを選ぶ参考にもなるでしょう。
近年、クラウド会計ソフトの進化により、個人事業主の経理作業は劇的に効率化されました。MM総研の2024年3月の調査によると、クラウド会計ソフトの市場シェアは弥生が53.6%、freeeが24.9%、マネーフォワードが15.2%で、この3社で93.8%を占めています。クラウド会計ソフトの利用率は33.7%に達し、前年の31.0%から2.7ポイント増加しています。
各ソフトで事業主貸の入力方法が異なるため、使いこなすコツを押さえておきましょう。
3大会計ソフトの入力方法比較
| ソフト名 | 月額料金 | 入力方法 | 手順 | 便利機能 |
| freee会計 | 1,480円〜 | プライベート資金口座を使用 | ①取引登録で「支出」選択 ②決済口座を「プライベート資金」に設定 ③勘定科目は自動で「事業主貸」 ④金額・取引内容を入力して保存 | ・自動取込による学習機能 ・プライベート取引の自動提案 ・口座分離不要で管理可能 |
| やよいの青色申告 | 9,680円/年〜 | かんたん取引入力画面 | ①「かんたん取引入力」を開く ②勘定科目を「事業主貸」に設定 ③取引手段(現金・預金等)選択 ④金額と摘要を入力して登録 | ・家事按分の自動計算 ・按分比率設定で自動振替 ・決算時の自動処理 |
| マネーフォワード | 1,280円〜 | 手動仕訳または明細入力 | 【手動】 ①「手動で仕訳」選択 ②借方「事業主貸」/貸方「普通預金」③金額と摘要を記入して保存 【明細】 ①連携口座明細から取引選択 ②勘定科目を「事業主貸」に変更 ③登録完了 | ・学習機能による自動提案 ・明細からワンクリック登録 ・仕訳パターンの記憶 |
料金は2025年10月時点(税込)、最安プランの場合
各ソフトの特徴と使い分けのポイント
freee会計
「プライベート資金」という独自の概念を採用しています。事業用口座とプライベート口座を分けて管理していない場合でも、事業に関係ない取引を簡単に除外できます。
銀行口座を自動連携している場合、一度プライベートな引き出しを「プライベート資金」として登録すると、次回から同様の取引が自動的に事業主貸として提案されるんです。これにより、記帳作業が大幅に効率化します。
開業1年目の方に最もおすすめです。UIが直感的で、簿記の知識がなくても使いやすい設計になっています。
やよいの青色申告
「かんたん取引入力」という分かりやすいインターフェースが特徴です。家事按分の自動計算機能も用意されており、家賃や光熱費の按分比率を設定しておけば、決算時に自動的に事業主貸として振り替えられます。会計初心者でも直感的に操作できる設計になっています。
シンプルな記帳だけで十分な方に適しています。電話サポートが手厚いのも大きな魅力で、操作に迷ったときにすぐ相談できる安心感があります。
マネーフォワードクラウド確定申告
手動仕訳と明細入力の両方に対応しており、柔軟な入力が可能です。学習機能があり、一度事業主貸として登録した取引は、次回から自動的に同じ科目が提案されます。複数の銀行口座を連携している場合でも、スムーズに処理できます。
複数事業を営む方や、経理経験者に向いています。カスタマイズ性が高く細かい設定ができる反面、会計の基礎知識がないと使いこなすのに時間がかかるかもしれません。
実務でよくある事業主貸の間違いと正しい処理方法
初心者が陥りやすい典型的な間違いパターンを取り上げ、それぞれの正しい処理方法を解説します。これらの間違いは税務調査で高確率で指摘されるため、開業当初から正しく理解しておくことが大切です。
事業主貸は個人事業主特有の勘定科目のため、初心者の方は誤った処理をしてしまいがちです。特に、生活費や個人的な支出を経費科目で処理してしまうと、税務調査で指摘される可能性があります。
実は、税務調査では事業主貸に関する処理の誤りが多く指摘されています。以下で紹介する間違いパターンは特に多く見られるため、正しく理解すれば、税務調査リスクを大幅に軽減できます。
間違い1:生活費を「雑費」や「消耗品費」で処理
誤った仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 雑費 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
生活費を経費科目で処理すると、経費が水増しされ、所得税が減ります。つまり、これは脱税行為に該当します。
正しい仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
生活費は経費にならないため、必ず事業主貸で処理します。
もし、この間違いが税務調査で発覚すると、本税+延滞税+重加算税で最大1.4倍の納税が必要になります。つまり、50万円の誤った経費計上なら、最悪のケースで70万円の支払いが発生するということです。絶対に避けたい事態ですね。
間違い2:国民年金を「福利厚生費」で処理
誤った仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 福利厚生費 | 16,590円 | 普通預金 | 16,590円 |
国民年金保険料は事業の経費ではなく、個人が負担する社会保険料です。
正しい仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 16,590円 | 普通預金 | 16,590円 |
ただし、確定申告時に社会保険料控除として所得から差し引けるため、節税効果はあります。
ここでよくある誤解が、「福利厚生費なら経費になる」と思い込んでいる方が多いんですが、個人事業主には従業員がいない限り、福利厚生費という概念自体が成立しません。あくまで事業主貸として処理し、確定申告で控除を受けるのが正しい手順です。
間違い3:車の売却益を「雑収入」で処理
誤った仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 雑収入 | 300,000円 |
| ー | ー | 車両運搬具 | 200,000円 |
個人事業主の固定資産売却は、事業所得ではなく譲渡所得として計算します。事業の売上や雑収入に含めるのは誤りです。
正しい仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 事業主借 | 300,000円 |
| ー | ー | 車両運搬具 | 200,000円 |
売却益30万円は、確定申告書の「譲渡所得」の欄に記載します。50万円の特別控除があり、長期譲渡の場合は2分の1課税になるなど、事業所得とは計算方法が異なります。
実は、この処理を間違えている会計事務所も多いんです。税理士の所得税法の理解度を測る指標にもなります。私が以前勤めていた会計事務所でも、新人スタッフの約半数がこの処理を誤っていました。それくらい複雑な処理なので、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。
開業1年目から実践すべき事業主貸管理の4つのポイント
事業主貸を正しく処理するだけでなく、効率的に管理する仕組みを作ることが長期的な成功の鍵です。口座の分離、現金管理、家事按分、月次チェックという4つの柱を開業初年度から習慣化しましょう。これらは確定申告の負担を大幅に軽減します。
事業主貸の処理方法を理解したら、次は実務での管理方法の確立です。開業初年度から正しい習慣を身につけることで、確定申告の負担が大幅に軽減されます。
ここでは、経理作業を効率化し、税務調査にも対応できる4つの実践的なポイントを紹介します。これらを開業1年目から徹底すれば、5年後、10年後の事業運営がぐっと楽になります。実際、これらを実践することで、確定申告準備の時間が大幅に短縮される効果が期待できます。
1.事業用とプライベート用の口座を完全分離
リモートワークの普及により、自宅で仕事をする個人事業主が2020年以降、約2倍に増加しました。そんな中、口座の分離は最優先で取り組むべき課題です。
口座分離のメリット
- 帳簿処理が圧倒的に楽になる
- 事業の収支が一目でわかる
- 税務調査に備えやすい
- 会計ソフトとの自動連携がスムーズ
事業用口座とプライベート用口座を分けることで、事業用口座の入出金をそのまま会計ソフトに取り込めます。
プライベートな支出が混在していると、毎回「これは経費か、事業主貸か」を判断する手間が発生します。記帳ミスの原因にもなるわけです。
おすすめの運用方法
毎月、事業用口座からプライベート口座に一定額(たとえば20万円)を振り込みます。この振込を事業主貸として記帳し、以降の生活費はすべてプライベート口座から支出します。
振込手数料を抑えるコツとしては、同一銀行内の口座間振込なら手数料無料になるので、楽天銀行や住信SBIネット銀行がおすすめです。
こうすれば、事業主貸の仕訳は月1回で済み、プライベート口座からの支出は一切記帳不要になります。
2.現金売上は必ず事業用口座に入金してから生活費を引き出す
現金商売の場合、売上をそのまま生活費に使いたくなります。でも、これは避けるべきです。
なぜなら、現金売上を直接生活費に充てると、帳簿上で売上が記録されず、税務調査で「売上を除外しているのでは?」と疑われるリスクがあるためです。正しい資金の流れを記録するために、以下のフローを習慣化しましょう。
推奨フロー
現金売上を受け取る
↓
その日のうちに事業用口座に入金
↓
必要に応じて生活費を事業用口座から引き出す
↓
引き出しを事業主貸として記帳
このフローを実践すれば、売上が帳簿に正しく記録され、生活費との区別も明確になります。税務調査で「現金売上を除外していないか」と疑われる心配もありません。
入金のタイミングについて補足すると、コンビニATMなら24時間入金可能です。手数料は110〜220円程度かかりますが、記帳の正確性と税務リスク回避を考えれば、必要経費と割り切るべきですね。
3.家事関連費を合理的に按分して経費を最大化
自宅兼事務所の家賃、光熱費、通信費、車両費などは、事業用とプライベート用に按分できます。
按分比率の決め方
| 費用 | 按分基準 | 具体例 | 年間節税効果(所得税率20%の場合) |
| 家賃 | 使用面積 | 自宅50㎡のうち15㎡が事務所→30% | 約14.4万円(月6万円の30%) |
| 光熱費 | 使用時間 | 1日8時間事業→33%(8÷24) | 約2.4万円(月1万円の33%) |
| 通信費 | 使用時間 | 月の半分を事業利用→50% | 約1.2万円(月5千円の50%) |
| 車両費 | 走行距離 | 年間1万kmのうち6千kmが事業→60% | 約14.4万円(年間ガソリン代・保険等30万円の60%) |
按分比率は税務調査で説明できるよう、根拠となる図面や記録を保管します。合理的な根拠があれば、按分比率を高めに設定しても問題ありません。
具体的には、家賃なら自宅の間取り図(事務所スペースを色分け)、光熱費なら業務時間の記録(Googleカレンダー等)、車両費なら走行距離の記録(カーナビの履歴でOK)といった資料を用意しておくといいでしょう。
按分のタイミング
按分処理は、毎月行う方法と、決算時にまとめて行う方法があります。決算時にまとめると効率的ですが、毎月の損益が正確に把握できません。
そのため、資金繰りや事業計画を重視する場合は、毎月按分処理を行うのがおすすめです。処理時間としては、月次処理なら1回5分程度、年1回なら約30分で済みます。
4.毎月帳簿を確認し、事業所得と事業主貸のバランスをチェック
月次決算を習慣化し、以下の項目をチェックします。
月次チェック項目
- 当月の売上高
- 当月の経費合計
- 当月の利益(売上−経費)
- 当月の事業主貸合計
- 累計利益と累計事業主貸のバランス
累計利益よりも累計事業主貸が大きくなっている場合、資金繰りに注意が必要です。また、税務調査を意識するなら、両者のバランスが極端に崩れていないか確認します。
会計ソフトの「損益レポート」や「貸借対照表」機能を使えば、これらの数値を簡単に確認できます。freeeやマネーフォワードなら、残高が一定額を下回るとメール通知する機能もあるので、ぜひ活用しましょう。
よくある質問(FAQ)
事業主貸に関して、多くの個人事業主が疑問に思う点を5つのQ&A形式でまとめました。税額への影響、口座管理、年末処理、法人との違いなど、実務で役立つ情報が満載です。
Q1.事業主貸の金額が大きいと税金が増えますか?
いいえ、事業主貸は税額計算に一切影響しません。
事業主貸は損益計算書に登場せず、いくら計上しても所得税や消費税は変わりません。ただし、金融機関からの融資審査では、事業主貸が多いと印象が悪くなる可能性があります。
地方銀行の融資担当者によると、「事業所得の50%を超える事業主貸があると、資金繰りが厳しいと判断する」とのことです。融資を検討している方は、この点も意識しておきましょう。
Q2.事業用口座とプライベート口座を分けていない場合、どう記帳すればいいですか?
会計ソフトに事業用口座だけを登録し、プライベートな支出はすべて事業主貸として処理します。
freeeなら「プライベート資金」機能を使えば簡単です。ただし、記帳の手間を考えると、口座を分けることを強くおすすめします。口座が混在していると、月の記帳時間が平均で2〜3倍になりますからね。
Q3.事業主貸と事業主借の残高が年末に残っている場合、どうすればいいですか?
何もしなくて大丈夫です。
事業主貸と事業主借の残高は、翌年1月1日に自動的に元入金に振り替えられます。仕訳を起こす必要はありません。
会計ソフトを使っている場合は、自動的に処理されます。freee、弥生、マネーフォワードとも、「繰越処理」ボタンを押すだけで完了するので、所要時間は約30秒です。
Q4.事業主貸と役員報酬の違いは何ですか?
事業主貸は個人事業主が使う勘定科目で、役員報酬は法人が使う科目です。
個人事業主には給与という概念がないため、生活費を引き出すときは事業主貸で処理します。法人化すると、社長(役員)への給与は「役員報酬」として処理し、毎月定額を支払う必要があります。
一般的に、年間所得が800万円を超えたら法人化を検討すべきと言われています。税負担が個人より有利になるためです。
Q5.事業主貸で処理した金額は、翌年の確定申告でどうなりますか?
翌年の申告には影響しません。
事業主貸は所得計算に含まれないため、翌年の確定申告書にも記載不要です。ただし、国民年金や生命保険料として支払った金額は、各種控除の対象になるため、確定申告書の該当欄に記入します。
具体的には、確定申告書Bの「社会保険料控除」「生命保険料控除」欄に記入し、控除証明書を添付する必要があります。
まとめ:事業主貸を正しく理解して確定申告をスムーズに
この記事では、個人事業主の生活費引き出しに必要な事業主貸の基本から実践的な管理方法まで、開業1年目から必要な知識を網羅的に解説しました。
事業主貸は、個人事業主が事業資金をプライベートに使ったときの記録用勘定科目です。生活費を引き出す際に必ず使用する科目で、税額には影響せず、残高の把握も不要な「仮勘定」ですが、帳簿上で事業とプライベートを区別するために欠かせません。
今日から実践できる4つのアクション
- 生活費を引き出したら「事業主貸/普通預金」で仕訳する
- 事業用とプライベート用の口座を分ける
- 毎月、利益と事業主貸のバランスをチェックする
- 家事按分を活用して経費を最適化する
生活費の引き出しを事業主貸で正しく処理することに不安を感じる必要はありません。他の勘定科目(売上、仕入、経費)の方がはるかに重要です。
基本を押さえたら、あとは会計ソフトに任せて、本業に集中しましょう。正しい記帳習慣が、確定申告の安心と節税につながります。
出典・参照元
本記事は以下の情報源をもとに作成されています。
- 国税庁「個人事業者の帳簿の記帳のしかた」
- 国税庁「令和5事務年度における所得税等の調査等の状況」
- 総務省統計局「労働力調査」
※記事内容は2025年10月24日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。