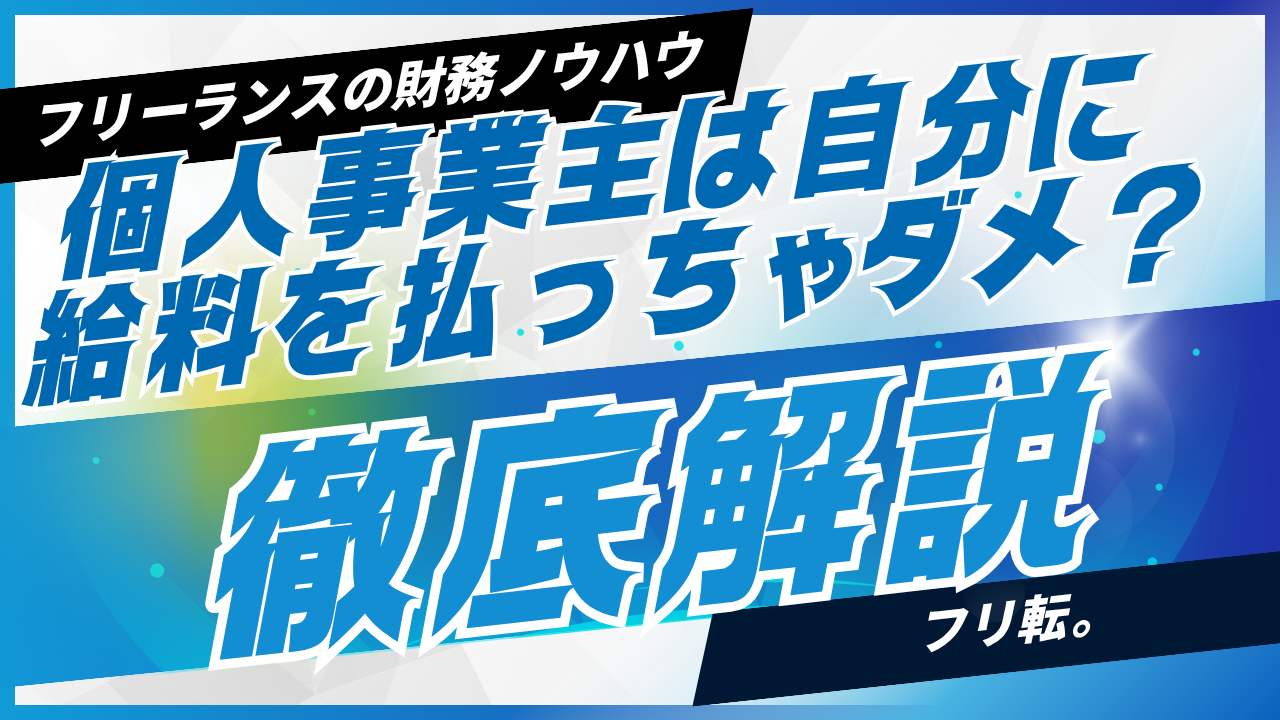個人事業主には「給料」という概念がありません。生活費は事業の利益から自由に引き出せますが、経費にはならず「事業主貸」で処理します。
この仕組みを知らないと、帳簿が混乱し、税務調査で指摘されるリスクがあります。本記事では、生活費の正しい引き出し方、家族への給与支払いのルール、法人化の判断基準まで、税理士監修のもと解説します。
個人事業主に「給料」という概念がない理由
個人事業主には「給料」という概念がありません。事業の利益=本人の所得となり、税法上は「事業所得」として扱われます。
ここでは、会社員との根本的な違いから、税法上の位置づけ、そして所得の考え方までを整理します。
会社員と個人事業主の根本的な違い
会社員の場合、雇用主である会社から「給与」が支払われ、その給与から所得税・住民税・社会保険料が源泉徴収されます。給与は会社にとって「人件費(経費)」として処理され、給与所得者である会社員は「給与所得控除」を受けられます。
一方、個人事業主は「雇用される側」ではなく、自ら事業を営む「事業主」です。事業から得た収入から経費を差し引いた残りが「事業所得」となり、これが事業主の取り分です。
税法上の取り扱い
所得税法第37条(必要経費)では、「自己の労務の対価」は必要経費に算入できないと定められています。個人事業主が自分自身に支払う「給料」は、税務上の経費として認められません。
具体例
| 項目 | 会社員 | 個人事業主 |
| 給与の扱い | 会社から支給 | 概念なし(事業所得から引き出し) |
| 税務上の処理 | 給与所得 | 事業所得 |
| 経費計上 | 可能(会社側) | 不可(事業主貸で処理) |
個人事業主の所得の考え方
個人事業主の所得は以下のように計算されます。
| 事業所得=収入-必要経費 |
この事業所得から、さらに以下が差し引かれます。
- 青色申告特別控除(最大65万円または55万円)
- 各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など)
最終的な課税所得に対して所得税・住民税が課されます。事業主が生活費として引き出す金額は、この計算に一切影響しません。
事業主貸と事業主借の基本
「事業主貸」と「事業主借」は、個人事業主特有の勘定科目です。どちらも事業とプライベートの資金のやり取りを整理するためのもので、経費や収入とは性質が異なります。
ここでは、それぞれの意味と使い方、そして両者の関係をわかりやすく解説します。
事業主貸とは
事業主貸(じぎょうぬしかし)は、事業用の資金を事業主個人の生活費や私的な支出に使った場合に使用する勘定科目です。
たとえば、以下のような場合に使います。
- 事業用口座から生活費を引き出したとき
- 事業用のクレジットカードで個人的な買い物をしたとき
- 所得税・住民税・国民健康保険料を事業用口座から支払ったとき
- 事業用資金で個人的な旅行代を支払ったとき
事業主貸は経費ではなく、事業所得の計算に影響しません。 あくまで事業資金を個人用途に移動させただけであり、事業所得の計算に影響しません。
事業主借とは
一方、事業主借(じぎょうぬしかり)は、事業主個人の資金を事業用に使った場合に使用する勘定科目です。
たとえば、以下のような場合に使います。
- 個人の預金から事業資金を追加した
- 個人のクレジットカードで事業用の経費を支払った
- 開業時に個人の貯金を事業資金として投入した
- 事業用口座の残高が不足したため、個人資金で補填した
事業主借も「収入」ではありません。事業所得の計算に影響せず、単に資金の出入りを記録するだけです。
事業主貸と事業主借の関係
年度末(12月31日)には、事業主貸と事業主借の残高は相殺され、「元入金(もといれきん)」という資本金に相当する科目に振り替えられます。
| 計算式:翌年の元入金=当年の元入金+事業所得-事業主貸+事業主借 |
この仕組みにより、毎年の事業資金の増減が自動的に調整されます。
生活費の引き出し方と記帳方法
生活費を事業用口座から引き出すときは、経費ではなく「事業主貸」として処理するのが基本です。事業と私生活のお金を明確に分けておくことで、帳簿の整合性が保たれ、税務上のトラブルも防げます。
ここでは、引き出しの流れや具体的な仕訳例、金額の考え方、理想的な資金管理の方法を紹介します。
生活費を引き出す基本的な流れ
個人事業主が生活費を引き出す際の手順は以下の通りです。
①事業用口座から引き出し
ATMで現金を引き出すか、個人口座へ振込を行います。
引き出した時点で事業用資金が減少します。
②記帳する
勘定科目は「事業主貸」、摘要は「生活費」「個人使用」などとします。
会計ソフトに必ず入力しましょう。
③証拠を残す
通帳記帳・取引明細を保管します。
領収書がなくても通帳記録で十分です。
「事業主貸」は”経費にならない支出”を明確にするための勘定科目です。
家計と事業のお金を分けておけば、損益の実態がはっきり見えるようになります。
具体的な仕訳例
実際の仕訳では、「誰に支払い、何の目的で出金したか」を明確に記録することが重要です。以下は典型的な3パターンです。
【例1】事業用口座から生活費20万円を引き出した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 事業主貸 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 | 生活費引き出し |
【例2】事業用クレジットカードで個人的な飲食費5,000円を支払った
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 事業主貸 | 5,000円 | 未払金(クレジット) | 5,000円 | 個人的飲食費 |
【例3】所得税30万円を事業用口座から納付した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 事業主貸 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 | 所得税納付 |
所得税や社会保険料など、事業と無関係な支出はすべて「事業主貸」で処理します。経費扱いにしてしまうと、税務上の誤りとして修正を求められることがあります。
引き出し額に制限はあるか
法律上、引き出し額に上限はありません。事業資金が潤沢であれば、いくらでも引き出せます。ただし、以下の点に注意が必要です。
| 注意点 | 内容 | リスク/対策 |
| 資金繰りの悪化 | 事業資金が不足し、経費や仕入れの支払いが困難に | 月次で残高を確認し、引き出し上限を設定する |
| 記帳の正確性 | 「事業主貸」で処理漏れがあると、資金の使途が不明に | 会計ソフトで自動登録・照合を活用 |
| 計画的な引き出し | 月次利益に基づいて無理のない範囲で設定 | 将来の納税資金(所得税・住民税・保険料)を確保 |
「いくら引き出してもいい」とは言っても、引き出し=事業資金の減少です。安定的な運転資金を維持するためには、計画的に生活費を設定するのが賢明です。
理想的な資金管理
資金の流れを整理することで、帳簿の信頼性が格段に高まります。次の方法を実践すると、生活費の出金と事業運営のバランスを保ちやすくなります。
| 管理項目 | 実施内容 | 目的・効果 |
| 口座の完全分離 | 事業用:売上・経費専用 個人用:生活費専用 | 資金の流れを明確にし、誤記を防ぐ |
| 定期的な資金移動 | 例:毎月20日に30万円を個人口座へ振込 | 「給料日」を自分で設定し、生活費を安定化 |
| 納税資金の確保 | 所得税・住民税・消費税の概算額を別口座で積立 | 納税時の資金不足を防止 |
| 資金繰りチェック | 月次で収支・残高を確認 | 赤字化や資金不足を早期に発見できる |
「事業主貸」は、事業と生活の境界線を明確にするためのツールです。一方で「事業主借」は、個人資金を事業に投入したときに使います。
この2つを正しく使い分けることで、資金の流れを可視化し、健全な経営判断がしやすくなります。
家族への給与は可能か?
家族に支払う給与は、原則として「実際に働いている場合」に限り認められます。ただし、青色申告と白色申告では扱いが大きく異なるため、正しい手続きを理解しておくことが重要です。
特に青色申告では「青色事業専従者給与」として経費計上できる一方、白色申告では上限や按分ルールがあり、自由に経費化できません。
ここでは、家族従業員への給与の基本ルールから、青色・白色それぞれの制度の違い、そしてどちらが有利かを具体的に解説します。
家族従業員への給与の基本ルール
個人事業主本人は自分に給与を支払うことができませんが、生計を一にする家族(配偶者・親・子など)に対しては条件付きで支払い可能です。
ただし、その家族が実際に業務に従事しており、対価として妥当な額であることが前提となります。
| 区分 | 内容 |
| 対象 | 生計を一にする配偶者・親族(15歳以上) |
| 前提 | 実際に事業に従事していること |
| 注意 | 個人事業主本人には「給与」という概念はない(事業の利益=所得) |
| ポイント | 税務上は「通常の従業員」と異なり、専用のルールが適用される |
家族に仕事を手伝ってもらう場合、「給与」として経費計上できるかどうかが節税に大きく影響します。
青色申告の場合:青色事業専従者給与
青色申告では、条件を満たせば実際に支払った給与を全額経費に計上できます。届出と金額設定の妥当性がポイントです。
| 項目 | 内容 |
| 主な条件 | ・青色申告者であること ・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出 (期限:3月15日まで/新規開業は開業日から2か月以内) |
| 専従者の要件 | ・15歳以上で、生計を一にする配偶者または親族 ・年のうち6か月超その事業に専ら従事している |
| 給与額の基準 | 「労務の対価として相当であると認められる金額」 (同業他社の水準・業務内容・事業規模などを参考に) |
| 留意点 | 極端に高額な給与は税務調査で否認される可能性あり |
実際の仕訳は次のとおりです。
配偶者に月20万円の給与を支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 専従者給与 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 | 配偶者給与(○月分) |
「青色事業専従者給与」は実際の支払いが必要です。帳簿上だけの処理では認められません。また届出を忘れると、その年分は経費にできないので注意しましょう。
白色申告の場合:事業専従者控除
白色申告では、給与を実際に支払わなくても控除として認められる仕組みがあります。ただし、上限額が設定されており、青色申告に比べて節税効果は限定的です。
| 項目 | 内容 |
| 専従者の要件 | 青色申告と同様 ・15歳以上であること・事業主と生計を一にしていること・その事業に年間6か月を超えて従事していること |
| 控除額の上限 | 配偶者:最大86万円 その他の親族:最大50万円 |
| 実際の控除額 | 上限額または「事業所得÷(専従者数+1)」のいずれか低い方 |
| 給与支払い | 不要(帳簿上の控除のみ) |
控除額の計算例を見てみましょう。
| ケース | 事業所得 | 専従者数 | 控除額 |
| ①配偶者1人・所得600万円 | 600万円 | 1人 | min(86万円,600万÷2)=86万円 |
| ②配偶者1人・所得100万円 | 100万円 | 1人 | min(86万円,100万÷2)=50万円 |
給与の支払いが不要なため、社会保険や源泉徴収の事務も発生しません。ただし、控除額が低いため節税効果は限定的です。
青色と白色、どちらが有利か
青色申告と白色申告では、「手続きの手間」と「節税効果」がトレードオフの関係にあります。どちらを選ぶかで、届出の有無・経費化の範囲・社会保険の扱いが変わるため、事前に仕組みを理解しておくことが重要です。
まずは両者の違いを整理してみましょう。
| 項目 | 青色申告(専従者給与) | 白色申告(専従者控除) |
| 事前届出 | 必要(厳格) | 不要 |
| 給与額 | 相当な金額なら制限なし | 最大86万円(配偶者) |
| 実際の支払い | 必要 | 不要 |
| 社会保険 | 給与所得として社会保険料負担 | 控除のみで負担なし |
| 有利なケース | 高額の給与を支払いたい場合 | 少額または手続きを簡略化したい場合 |
表を見るとわかる通り、青色申告は手続きが煩雑な反面、経費計上の自由度が高く節税効果も大きいのが特徴です。
一方で、白色申告は控除額が限られるものの、手続きが簡単で、事務負担を抑えたい人に向いています。
年間200万円以上の給与を支払う場合
- 青色申告が有利年間100万円以下の手伝い程度
- 白色申告でも十分配偶者を社会保険の扶養内に残したい場合
- 白色申告(控除のみ)のほうが有利なことも
どちらを選ぶべきかは、支払う給与額や家族の勤務状況によって変わります。上記のような目安を参考にしてみてください。
これらを判断する際には、「家族の働き方」と「税・社会保険のバランス」をセットで考えるのがポイントです。
法人成りを検討すべきタイミング
個人事業として事業が軌道に乗ると、次のステップとして「法人化(法人成り)」を検討する段階に入ります。法人化することで、税金面・信用面でのメリットが得られる一方、コストや事務負担も増えます。
ここでは、法人化を考える際の基本的な判断軸と手続きの流れを整理します。
個人事業と法人の違い
法人化を行うと、事業主本人は「代表取締役」などの役員となり、給与(役員報酬)を受け取る形に変わります。
つまり、「事業の利益=自分の所得」だった関係から、会社と個人が明確に分離されるのが特徴です。この変化が、税金・社会保険・信用力のすべてに影響します。
法人化のメリット
法人化を検討する最大の理由は、節税や信用向上など、個人事業では得られない仕組み的な優位性があるためです。
| 区分 | 内容 |
| 節税効果 | ・個人所得税(最高45%)と法人税(約23.2%)の税率差を活用可能 ・役員報酬による給与所得控除 ・法人と個人の所得分散で累進課税を軽減 |
| 社会的信用の向上 | ・取引先・金融機関からの信頼アップ ・融資や取引条件の改善 ・人材採用に有利 |
| 経費の範囲拡大 | ・生命保険料の一部 ・役員退職金の積立 ・社宅家賃の一部などが経費対象に |
| 事業承継・相続対策 | ・株式を通じて承継が可能 ・個人資産と事業資産を分離できる |
節税目的だけでなく、「取引の信頼性」「経営の継続性」という視点でも法人化は大きな意味を持ちます。
法人化のデメリット
法人化には、コストや事務負担などの現実的なデメリットもあります。設立費用や社会保険料の増加、決算処理の複雑さなど、維持コストにも注意が必要です。
| 区分 | 内容 |
| 設立・維持コスト | ・株式会社:約25万円〜/合同会社:約10万円〜 ・税理士報酬 ・社会保険料の増加 |
| 事務負担の増加 | ・法人税・消費税の申告 ・社会保険・労働保険の届出 ・決算公告の義務 |
| 赤字でも税金発生 | ・法人住民税均等割(年約7万円)は必ず発生 |
法人化を検討すべきタイミング
ここまでで「何が変わるか」を整理しました。次は、いつ法人化すべきかという現実的な判断に移りましょう。
節税メリットが出るかどうかは、所得額や家族構成、社会保険負担などの要素によって異なります。
| 判定目安 | 検討のポイント |
| 年間事業所得が700万円を超える場合(目安) | 税率差による節税効果が出始める |
| 取引先の信用を高めたい | 契約・融資の条件改善が見込める |
| 家族へ給与を支払っている | 所得分散による節税がしやすくなる |
| 事業拡大や雇用を予定している | 組織化しやすく社会保険制度も整う |
所得金額だけでなく、「社会保険料の増加」や「事務負担の増減」を含めて総合判断が必要です。詳細は税理士に法人化シミュレーションを依頼し、損益を比較することをおすすめします。
シミュレーション時の確認事項
税理士に相談する際は、以下の情報を提供しましょう。
- 事業所得の見込み額(今期・来期)
- 家族構成(配偶者・扶養家族の有無)
- 社会保険の加入状況
- 将来の事業計画(売上拡大の見込み、従業員雇用の予定)
- 個人資産の状況(不動産、金融資産など)
“所得が増えてきたから”だけでなく、「今後どんな事業規模にしていきたいか」という中長期視点も大切です。
法人化の手続きの流れ
検討の方向性が固まったら、次は実際の手続きです。法人化には、定款作成・登記・税務届出など複数のステップがあります。
全体像を把握しておくことで、準備の抜け漏れを防げます。
| 手順 | 内容 |
| ①法人形態の選択 | 株式会社または合同会社を選択 |
| ②定款作成・認証 | 株式会社の場合、公証役場で認証(約5万円) |
| ③資本金の払い込み | 最低1円〜(実務上は数十万円以上が一般的) |
| ④登記申請 | 法務局で商業登記を実施 |
| ⑤税務・自治体届出 | 法人設立届、青色申告申請、給与支払事務所届など |
| ⑥社会保険の手続き | 健康保険・厚生年金の加入、労働保険(雇用ありの場合) |
書類準備から登記完了まで約1〜2か月程度。開業準備と並行して進めるとスムーズです。
法人化後の給与の取り扱い
法人化が完了すると、事業主は「会社の役員」となり、給与として役員報酬を受け取ります。この段階で、個人と法人の税務上の扱いが明確に分かれます。
ここでは、役員報酬の基本ルールと仕訳例を整理します。
役員報酬の決め方
役員報酬は法人の経費となりますが、税務上は一定のルールを満たす必要があります。
特に「金額の決め方」と「支払いタイミング」が重要です。
| 区分 | 内容 |
| 定期同額給与 | 毎月同額で支給(年度途中の変更は原則不可) |
| 決定方法 | 株主総会などで事業年度開始3か月以内に決定 |
| 適正額の基準 | 高すぎると会社の利益圧迫/低すぎると生活資金や保険料に影響 |
| 注意点 | 社会保険料は役員報酬額に応じて増減する |
役員報酬は「節税のための調整弁」として使われることもありますが、生活資金と会社経営のバランスを考慮することが前提です。
法人化後の仕訳例
役員報酬の設定と処理を適切に行うことで、法人としての経理と個人の所得管理を明確に分けられます。
【例】役員報酬50万円を支払った
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 役員報酬 | 500,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
| – | – | 預り金(源泉税) | 50,000円 |
| – | – | 預り金(社会保険料) | 50,000円 |
役員報酬は「経費」として法人の所得から控除され、個人は「給与所得」として所得税が課されます。
よくある質問(FAQ)
生活費や家族給与、申告方法の扱いを正しく理解すれば、無駄な税負担を防げます。迷ったときは早めに専門家へ確認し、安心して事業を続けましょう。
Q1.生活費を引き出したタイミングで税金が発生しますか?
いいえ、発生しません。税金は「事業所得の金額」に対して課されるため、生活費をいつ・いくら引き出しても課税額には影響しません。
ただし、事業資金が減少するため資金繰りには注意が必要です。
Q2.「事業主貸」と「事業主借」の残高は毎年リセットされるのですか?
はい、年度末(12月31日)に両者の差額が「元入金」に振り替えられ、翌年は残高ゼロからスタートします。これにより毎年の事業資金の増減が自動的に調整される仕組みです。
Q3.青色事業専従者給与の届出を忘れた場合、遡って経費にできますか?
できません。届出は適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に提出する必要があり、期限を過ぎると翌年からの適用となります。
給与を実際に支払っていても経費にはなりません。
Q4.配偶者を青色事業専従者にすると、配偶者控除は使えなくなりますか?
使えなくなります。青色事業専従者給与を適用すると、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
そのため、給与額が少額の場合は控除を受けたほうが有利なケースもあります。
Q5.法人化すると個人事業時代の「事業主貸」はどうなりますか?
法人化時点で個人事業は廃業となり、事業資産・負債を法人へ引き継ぎます。
「事業主貸」「事業主借」などの勘定科目は消滅し、代わりに法人の「資本金」や「代表者からの借入金」などに置き換わります。
まとめ:個人事業主の「自分の給料」は“取り分”として管理する
個人事業主には、会社員のような「給料」という仕組みはありません。事業で得た利益そのものが事業主の所得であり、生活費として引き出す場合は「事業主貸」で処理します。
これは経費ではなく、あくまで自分の取り分を移動させる記録です。生活費を計画的に引き出すことで、資金繰りや納税に余裕が生まれます。そのために今日からできる4つの実践は次のとおりです。
今すぐできる4つの実践ポイント
- 事業用口座と個人口座を完全に分離する
混在を防ぎ、記帳を簡素化。税務調査での説明も容易になる - 月1回の生活費振替ルールを作る
給料日感覚で定期振替を設定。計画的な資金管理が可能になる - 納税資金を別口座で積み立てる
所得税・住民税・消費税の概算額を毎月積み立て。突然の納税に慌てない - 会計ソフトで記帳を自動化する
銀行口座と連携し、仕訳を自動作成。確定申告書も自動生成される
「給料」ではなく「取り分」として管理する姿勢が、健全な資金運営の第一歩です。不明点があれば、税理士など専門家に相談して確定申告を確実に進めましょう。
参考資料・出典
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」(タックスアンサーNo.2075)
- 国税庁「事業所得の課税のしくみ」(タックスアンサーNo.1350)
- 国税庁「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」「所得税法(e-Gov法令検索)」
- 法務局「商業・法人登記の手数料」
- 中小企業庁「法人成りガイドライン」
※記事内容は2025年10月25日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。